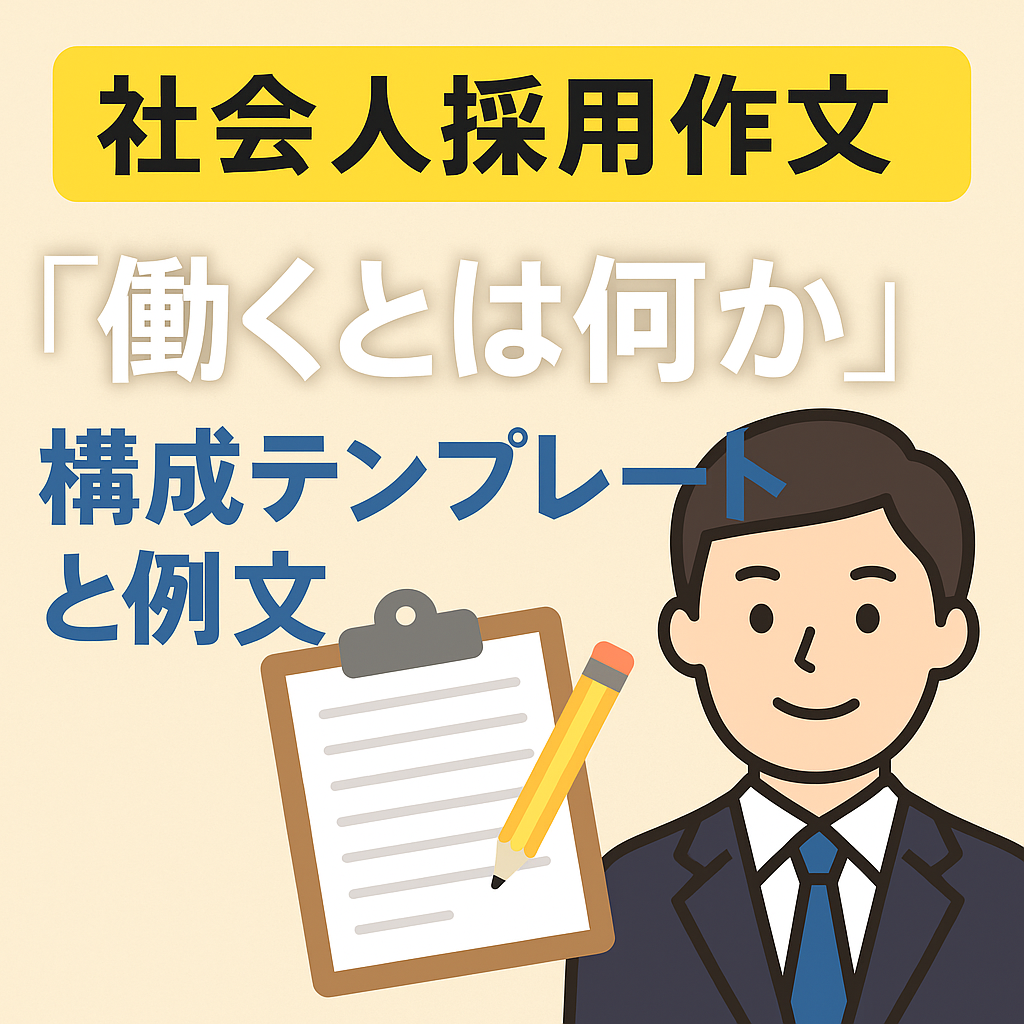
社会人採用(中途採用・キャリア採用)の試験で、「働くとは何か」というテーマは最頻出です。銀行、商社、メーカー、公務員——業界を問わず、毎年出題されています。
企業がこのテーマで見極めたい3つのポイント
1. 仕事に対する価値観
- 仕事をどう捉えているか(お金のため?成長のため?社会貢献?)
- その価値観が企業の理念と合致するか
- 長期的に働き続けられる動機があるか
2. 自己認識の深さ
- 自分の経験を振り返り、意味づけできるか
- 表面的な理解ではなく、深い自己理解があるか
- 失敗や困難から学ぶ姿勢があるか
3. 組織適応力
- 組織の中でどう貢献できるか
- 他者と協働する姿勢があるか
- 前向きで建設的な考え方ができるか
つまり、このテーマは「この人を採用して大丈夫か」を総合的に判断するための試金石なのです。
「働くとは何か」を問うテーマの本質
採用担当者の本音
表面的には「働くとは何か」と聞いていますが、実は以下を知りたがっています。
✅ この人は仕事に対して主体的か、受動的か? ✅ 困難があっても前向きに取り組めるか? ✅ 個人プレーか、チームで働けるか? ✅ 短期的な視点か、長期的なキャリアビジョンがあるか? ✅ 自社の価値観と合うか?
よくある誤解
❌ 誤解1:「正解」を書けばいい → 正解はありません。自分の経験に基づいた「あなたなりの答え」が求められています。
❌ 誤解2:立派なことを書けばいい → 美辞麗句より、リアルで誠実な内容が評価されます。
❌ 誤解3:仕事への情熱を語ればいい → 情熱だけでなく、冷静な自己分析と具体性が必要です。
作文の基本構成:三段構成+PREP法
基本の三段構成
| 段落 | 内容 | 文字数の目安(800字) | 割合 |
|---|---|---|---|
| 序論 | 働くことの定義・問題提起 | 200字前後 | 25% |
| 本論 | 具体的経験・気づき・学び | 400字前後 | 50% |
| 結論 | まとめ・今後の姿勢・志望動機 | 200字前後 | 25% |
PREP法で説得力を高める
PREP法とは?
- Point(結論・主張)
- Reason(理由)
- Example(具体例)
- Point(結論の再確認)
「働くとは何か」での活用例
【P】私は、働くとは「自己実現と社会貢献の両立」だと考える。
【R】なぜなら、自分の成長だけを追求しても満足感は得られず、
他者への貢献を実感できてこそ、仕事の意義を感じられるからだ。
【E】前職で新規プロジェクトを任された際、当初は自分の実績作りに
必死だった。しかし、顧客の課題を真摯に聞き、チームで解決策を
考える中で、「誰かの役に立つ喜び」を知った。結果として、
プロジェクトは成功し、顧客から感謝の言葉をいただいた。
この経験が、私の働く意味を変えた。
【P】働くとは、自分を磨きながら、他者や社会に価値を提供すること。
この信念を持って、貴社でも貢献したい。
序論(導入)の書き方:3つのパターン
序論は「つかみ」の部分。読み手の関心を引き、自分の主張を明確に示します。
パターン1:定義提示型
特徴:最もオーソドックスで安全 使い方:自分なりの「働く」の定義を最初に示す
例
私は、働くとは「自分の能力を社会に還元し、同時に自己を成長させる行為」だと考える。単なる生活の糧を得る手段ではなく、自分と社会をつなぐ架け橋である。
パターン2:問いかけ型
特徴:読み手を引き込みやすい 使い方:疑問を投げかけてから、自分の答えを示す
例
「働くとは何か」——この問いに、かつての私は明確に答えられなかった。しかし、社会人として10年のキャリアを積む中で、働くとは「他者との関係の中で自分の価値を見出すこと」だと気づいた。
パターン3:社会背景型
特徴:時事性があり、視野の広さを示せる 使い方:現代社会の変化を踏まえて自分の考えを述べる
例
AI技術の進化やリモートワークの普及により、働き方は大きく変化している。しかし、どんなに技術が発達しても、働くことの本質は変わらない。私は、働くとは「人と人をつなぎ、新しい価値を創造すること」だと考える。
本論(展開)の書き方:「経験→気づき→学び」の流れ
本論は作文の核心部分。ここで差がつきます。
本論の黄金パターン
1. 具体的な経験(エピソード)
2. その時の課題・困難
3. どう考え、どう行動したか
4. 何に気づいたか(転機)
5. そこから何を学んだか
6. 今どう活かしているか
効果的なエピソードの選び方
✅ 良いエピソード
- 具体的で、情景が浮かぶ
- 困難や葛藤がある(成長のプロセスが見える)
- 自分の変化・成長が分かる
- 今の仕事観につながっている
❌ 避けるべきエピソード
- 抽象的で何があったか分からない
- 成功体験だけ(苦労がない)
- 他人の話(自分の経験ではない)
- 今の価値観と無関係
エピソードの書き方例
❌ 悪い例(抽象的)
前職では色々な困難があったが、乗り越えることで成長した。
✅ 良い例(具体的)
前職の営業部門で、新規開拓を担当していた頃、3ヶ月連続で目標未達となった。焦りから闇雲に訪問数を増やしたが、成果は出なかった。上司から「顧客の課題を聞いているか?」と問われ、ハッとした。それまで自分の商品説明に終始し、相手のニーズを理解しようとしていなかったのだ。以降、徹底的にヒアリングに時間をかけ、顧客ごとに提案内容をカスタマイズした。結果、4ヶ月目から受注が増え始め、半年後には部門トップの成績を収めた。
結論(まとめ)の書き方:3つの要素
結論は「締めくくり」。印象に残る終わり方をしましょう。
結論に必須の3要素
1. 働くことの定義の再確認 序論で述べた定義を、別の言葉で言い換えて強調
2. 今後の行動・姿勢 学びを今後どう活かすかを具体的に
3. 志望動機への接続(可能なら) 「だからこそ貴社で〜したい」と自然につなげる
結論の例
パターンA:行動宣言型
働くとは、自分の能力を最大限に発揮し、他者や社会に貢献することだと確信している。今後も、チームの一員として責任を果たし、顧客の期待を超える価値を提供し続けたい。そのために、日々学び、成長する姿勢を持ち続ける。
パターンB:志望動機接続型
働くとは、自己実現と社会貢献を両立させる行為である。貴社の「顧客第一主義」という理念は、私の働く意味と完全に一致する。この経験と信念を活かし、貴社の発展に貢献したい。
パターンC:展望型
働くことの意味は、キャリアの各段階で深化していくものだと思う。これまでの経験を糧に、次のステージでは、より広い視野と深い専門性を持って、組織と社会に貢献できる人材になりたい。
「働くとは何か」の切り口:6つの視点
自分なりの答えを見つけるために、以下の視点から考えてみましょう。
視点1:自己実現・成長
定義:働くとは、自分の可能性を広げ、成長する機会である
こんな人に向いている
- キャリアアップを重視
- 学ぶことが好き
- 挑戦志向
例文での表現
働くとは、自分の限界に挑戦し、できることを増やしていく過程である。
視点2:社会貢献・他者への奉仕
定義:働くとは、自分の力を他者や社会のために使うことである
こんな人に向いている
- 人の役に立ちたい
- 社会的意義を重視
- 公共性の高い仕事志望
例文での表現
働くとは、自分のスキルや時間を、誰かの幸せのために捧げることである。
視点3:つながり・協働
定義:働くとは、人と人をつなぎ、共に価値を創造することである
こんな人に向いている
- チームワークを重視
- コミュニケーション力がある
- 調整役が得意
例文での表現
働くとは、多様な人々と協力し、一人では成し遂げられないことを実現することである。
視点4:対価・経済的自立
定義:働くとは、自分の労働に対する正当な対価を得て、経済的に自立することである
こんな人に向いている
- 実利的な考え方
- 責任感が強い
- 家族を養う立場
例文での表現
働くとは、自分と家族の生活を支え、経済的に自立するための手段であると同時に、社会への参加でもある。
注意:金銭面だけを強調すると印象が悪いので、必ず社会性も付け加える
視点5:自己表現・創造
定義:働くとは、自分の個性や価値観を表現し、新しいものを生み出すことである
こんな人に向いている
- クリエイティブ職
- 独創性がある
- 自分らしさを大切にする
例文での表現
働くとは、自分の感性やアイデアを形にし、世の中に新しい価値を提供することである。
視点6:責任・義務
定義:働くとは、社会の一員としての責任を果たすことである
こんな人に向いている
- 真面目で堅実
- 責任感が強い
- 伝統的価値観
例文での表現
働くとは、社会に生きる人間としての責任を果たし、自分の役割を全うすることである。
よくある失敗パターンと改善策
失敗パターン1:お金が第一の印象
❌ NG例
働くとは、お金を稼いで生活することである。給料が高ければモチベーションも上がる。
なぜダメか?
- 金銭的動機のみで、社会性がない
- 「給料が高い他社に行くのでは?」と思われる
- 仕事への誇りや情熱が感じられない
✅ 改善例
働くとは、自分の労働に対する正当な対価を得ることで経済的に自立し、同時に社会に貢献することである。生活の糧を得ることは重要だが、それ以上に、自分の仕事が誰かの役に立っているという実感こそが、働く意義だと考える。
失敗パターン2:ネガティブな表現
❌ NG例
働くことは正直つらいが、生きていくためには仕方がない。
なぜダメか?
- 後ろ向きで、一緒に働きたいと思えない
- ストレス耐性が低そう
- すぐ辞めそう
✅ 改善例
働くことには困難も多い。しかし、その困難を乗り越えた先に、達成感や成長がある。私は、チャレンジを恐れず、前向きに取り組む姿勢を大切にしたい。
失敗パターン3:抽象的で根拠がない
❌ NG例
働くとは、夢を実現することである。夢があれば頑張れる。
なぜダメか?
- 具体性がない
- どんな経験から来た考えか不明
- 実現可能性が感じられない
✅ 改善例
働くとは、目標に向かって努力し、それを達成する過程である。私は学生時代から〇〇の分野に興味を持ち、前職で△△プロジェクトに携わった。困難もあったが、チームで乗り越えたことで、目標達成の喜びを知った。今後もこの経験を活かし、より大きな目標に挑戦したい。
失敗パターン4:自分語りだけで組織への視点がない
❌ NG例
働くとは、自分のスキルを磨き、キャリアアップすることだ。常に上を目指し、成長し続けたい。
なぜダメか?
- 個人主義的で、チームワークが感じられない
- 組織への貢献意識が見えない
- 「自分のためだけに働く人」と思われる
✅ 改善例
働くとは、自分のスキルを磨きながら、組織やチームに貢献することである。個人の成長は重要だが、それを組織の目標達成にどう活かすかが真の価値だと考える。前職では、自分の専門知識を後輩に伝えることで、チーム全体のレベルアップに貢献した。
失敗パターン5:経験と結論がつながっていない
❌ NG例
前職では営業として頑張った。働くとは楽しいことだ。
なぜダメか?
- 経験と結論の論理的つながりがない
- なぜそう思ったのかのプロセスが不明
- 説得力がない
✅ 改善例
前職の営業で、当初は成果が出ず苦しんだ。しかし、顧客の課題に真摯に向き合い、解決策を提案する中で、「誰かの役に立つ喜び」を知った。この経験から、働くとは、困難を乗り越えながら他者に価値を提供することだと気づいた。
レベル別例文集
【例文1】基本レベル(600字)|飲食店アルバイトの経験
働くとは、他者の役に立つことで自分も成長することだと私は考える。
学生時代、飲食店でアルバイトをしていた頃、私は仕事を効率的に「こなす」ことばかり考えていた。しかしある日、常連のお客様から「あなたがいると安心する」と声をかけられた。自分の行動が誰かの安心や満足につながると実感し、働くことの意味が変わった。
それからは、同僚が困っていれば声をかけ、店全体の雰囲気づくりを意識するようになった。結果として売上も向上し、チームで表彰を受けた。個人の成果以上に、みんなで達成する喜びが印象に残っている。
社会人となった今も、この姿勢は変わらない。自分の業務に責任を持ちつつ、他者の立場に立って考えることで、より良い成果を生み出せると信じている。働くとは、単なる労働ではなく、人と人との信頼を築く行為である。
【例文2】標準レベル(800字)|営業職の経験
私は、働くとは「自己実現と社会貢献の両立」だと考える。
前職で営業を担当していた頃、新規開拓に苦戦し、3ヶ月連続で目標未達となった。焦りから訪問件数を増やしたが、成果は出なかった。上司から「顧客の課題を聞いているか?」と問われ、ハッとした。それまで自社商品の説明に終始し、相手のニーズを理解しようとしていなかったのだ。
以降、徹底的にヒアリングに時間をかけ、顧客ごとに提案内容をカスタマイズした。ある中小企業では、社長の「人手不足で業務が回らない」という悩みに対し、業務効率化のシステムを提案した。導入後、残業時間が月50時間削減され、社長から「おかげで従業員が笑顔になった」と感謝された。この時、働くことの本質を理解した。
働くとは、自分の能力を発揮することだけでなく、それが誰かの課題解決につながり、喜びを生み出すことだ。自分の成長と他者への貢献が重なった時、最も大きな充実感を得られる。
今後も、顧客の真のニーズを捉え、期待を超える価値を提供し続けたい。そして、チームの一員として、組織の目標達成にも貢献したい。働くとは、自分と他者、そして社会をつなぐ架け橋である。この信念を持って、貴社でも全力で取り組みたい。
【例文3】応用レベル(1000字)|プロジェクトリーダーの経験
「働くとは何か」——この問いに対する私の答えは、社会人としてのキャリアの中で変化し、深化してきた。現在、私は働くとは「個人の成長・チームの成功・社会への貢献が交わる点を見出すこと」だと考えている。
新卒で入社した当初、私は働くことを「自分のスキルを磨く場」としか捉えていなかった。上司の指示を完璧にこなし、評価を得ることが目標だった。しかし5年目、初めてプロジェクトリーダーを任された時、この認識は大きく揺らいだ。
そのプロジェクトは、新システム導入による業務効率化を目指すものだった。私は綿密な計画を立て、メンバーに指示を出したが、プロジェクトは停滞した。メンバーからは「なぜこのやり方なのか分からない」という声が上がり、チームの雰囲気は悪化した。自分一人で完璧を目指すあまり、メンバーの意見を聞かず、目的も共有していなかったのだ。
転機となったのは、上司からの一言だった。「リーダーの仕事は、自分が輝くことじゃない。メンバー全員が力を発揮できる環境を作ることだ。」ハッとした。それからは、週次ミーティングで各自の意見を丁寧に聞き、なぜこのプロジェクトが必要なのか、成功すれば顧客や社会にどんな価値を提供できるのかを、繰り返し共有した。
メンバーの一人が「この仕組みができれば、現場の残業が減る。それって、働く人の生活の質を上げることですよね」と言った時、チームの空気が変わった。単なる業務ではなく、意義のあるプロジェクトだと、全員が腹落ちしたのだ。以降、メンバーは自発的にアイデアを出し、互いにサポートし合うようになった。結果、プロジェクトは成功し、顧客企業の残業時間は30%削減された。
この経験から、働くことには三つの軸があると気づいた。第一に「個人の成長」。困難に挑戦し、新しいスキルや視点を得ること。第二に「チームの成功」。一人では成し遂げられないことを、協力して実現すること。第三に「社会への貢献」。自分たちの仕事が、誰かの生活をより良くすること。この三つが重なった時、働くことの最も深い意義を感じられる。
もちろん、働くことには経済的側面もある。生活を支え、家族を養うことは重要だ。しかし、それだけでは長く働き続けるモチベーションにはならない。自分の仕事が誰かの役に立ち、社会に価値を生み出しているという実感こそが、困難を乗り越える原動力になる。
今後、私はこの三つの軸を常に意識しながら働きたい。個人としては、専門性を深めつつ、視野を広げる。チームでは、メンバーの強みを活かし、互いに高め合う関係を築く。そして社会に対しては、自分たちの仕事がどんな価値を生むのかを常に問い続ける。
貴社の「顧客価値の最大化」という理念は、私の働く意味と完全に一致する。これまでの経験と、働くことへの深い理解を活かし、貴社の発展に貢献したい。働くとは、自分・チーム・社会をつなぐ行為である。その信念を胸に、全力で取り組む覚悟だ。
採点者が見ている5つのポイント
社会人採用の作文で、採点者は何を評価しているのでしょうか?
評価の5つの観点
| 観点 | 評価内容 | 配点目安 |
|---|---|---|
| 価値観の明確さ | 働くことをどう捉えているか、自分の言葉で語れているか | 20点 |
| 具体性 | 抽象論ではなく、実体験に基づいているか | 20点 |
| 論理性 | 経験→気づき→学びの流れが論理的か | 20点 |
| 前向きさ | ポジティブで建設的な姿勢が感じられるか | 20点 |
| 組織適応力 | チームや組織への貢献意識があるか | 20点 |
高得点を取るポイント
✅ オリジナリティ:他人の受け売りではなく、自分の経験と言葉で ✅ バランス:個人と組織、理想と現実のバランス ✅ 具体性:「いつ・どこで・何が・どうなった」が明確 ✅ 成長性:失敗や困難から学ぶ姿勢 ✅ 一貫性:序論・本論・結論で主張がブレない
書く前の準備:自己分析の3ステップ
ステップ1:自分の経験を棚卸しする
以下の質問に答えてみましょう:
仕事での成功体験
- 最も達成感を感じた仕事は?
- なぜそう感じたか?
- 何が良かったか?
仕事での失敗・困難
- 最も苦しんだ経験は?
- どう乗り越えたか?
- 何を学んだか?
転機となった出来事
- 仕事観が変わった瞬間は?
- 誰の言葉や行動が影響したか?
ステップ2:自分の価値観を言語化する
以下から、自分に最も近いものを選びましょう:
- [ ] 成長・自己実現
- [ ] 社会貢献・他者への奉仕
- [ ] チームワーク・協働
- [ ] 経済的自立・責任
- [ ] 創造・自己表現
- [ ] 安定・継続性
ステップ3:志望企業の理念と照らし合わせる
- 企業理念・ビジョンは?
- 求める人物像は?
- 自分の価値観と合致する点は?
提出前チェックリスト
作文を書き終えたら、以下を確認しましょう。
内容のチェック
- [ ] 働くことの定義が明確に示されているか
- [ ] 具体的な経験(エピソード)があるか
- [ ] 経験から何を学んだかが書かれているか
- [ ] 今後どう行動するかが示されているか
- [ ] ネガティブな表現がないか
構成のチェック
- [ ] 序論・本論・結論の構成になっているか
- [ ] 各段落が適切な長さか(序論・結論は200字前後、本論は400字前後)
- [ ] PREP法を意識しているか
- [ ] 論理的なつながりがあるか
表現のチェック
- [ ] 「だ・である調」で統一されているか
- [ ] 誤字脱字がないか
- [ ] 一文が長すぎないか(60字以内が目安)
- [ ] 同じ言葉の繰り返しがないか
- [ ] 具体的で分かりやすい表現か
よくある質問(FAQ)
Q1. アルバイト経験しかない場合は?
A. 問題ありません。アルバイトでも、責任を持って取り組んだ経験、困難を乗り越えた経験があれば十分です。重要なのは、そこから何を学び、今後どう活かすかです。
Q2. 転職回数が多い場合、どう書けばいい?
A. 転職の事実を隠す必要はありません。各職場で何を学び、どう成長したかを示しましょう。「様々な環境で多様な経験を積んだ」とポジティブに捉えることもできます。
Q3. 志望企業について触れるべき?
A. 可能なら、結論部分で自然に触れると良いでしょう。ただし、無理に入れる必要はありません。全体の流れを優先してください。
Q4. 失敗談を書いても大丈夫?
A. むしろ推奨します。失敗から何を学んだかを示すことで、成長性や謙虚さをアピールできます。ただし、深刻すぎる失敗(会社に大損害など)は避けましょう。
Q5. 文字数が足りない場合は?
A. 以下を追加しましょう:
- エピソードの詳細(状況・行動・結果)
- 学びの深掘り(なぜそう気づいたか)
- 今後の具体的な行動計画
まとめ:「働くとは何か」は人生観を問う深いテーマ
「働くとは何か」というテーマは、単なる作文課題ではありません。あなたの人生観、価値観、そしてこれからのキャリアビジョンを問う、深い問いです。
成功する作文の3要素
1. 自分の言葉 誰かの受け売りではなく、自分の経験から導き出した答え
2. 具体性 抽象論ではなく、リアルなエピソードに基づく
3. 未来志向 過去の振り返りだけでなく、今後の行動・貢献を示す
最後に:働くことの意味は進化し続ける
働くことの意味は、一つの答えに固定されるものではありません。キャリアの各段階で、新しい経験を積むたびに、深化し、変化していくものです。
今のあなたなりの答えを、誠実に、具体的に、前向きに語ってください。その姿勢こそが、採用担当者の心を動かします。
働くとは、自分と社会をつなぐ架け橋である。 あなたなりの架け橋を、作文の中で描いてください。
関連記事
- 【2025年最新】大学1年生必見!教授が高評価する実践的レポート作成完全マニュアル
- 大学生・社会人の必須文章! レポートの書き方と基本テクニック(ひな型・テンプレート付き)
- 【初心者向け】レポート・論文に使える情報源&資料の探し方まとめ
- レポート・論文の作成に役立つ「テキスト批評」とは
この記事が役に立ったら、ブックマークして転職活動にお役立てください!

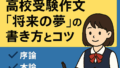
コメント