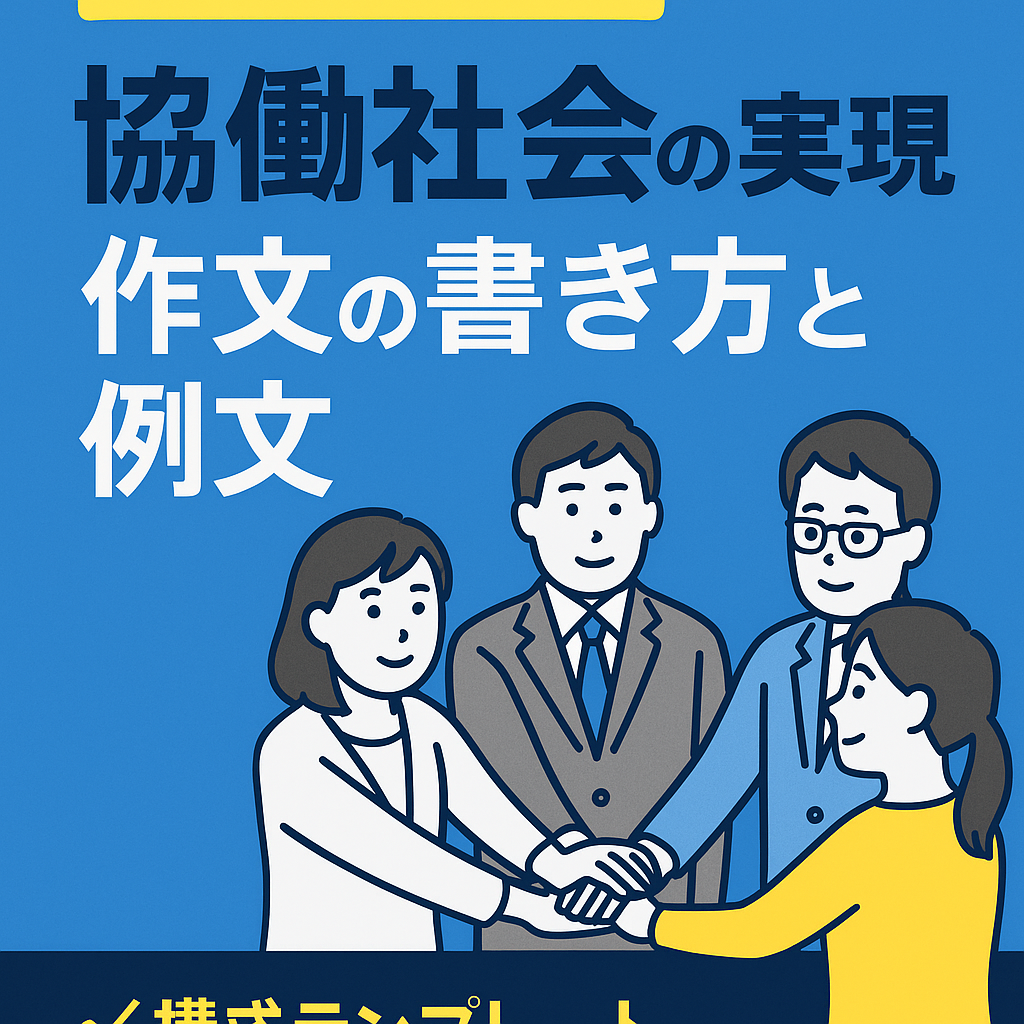
公務員試験の作文・論文テーマの中で、「協働社会の実現」は最頻出テーマの一つです。国家公務員・地方公務員を問わず、毎年必ずと言っていいほど出題されています。
協働社会が重視される3つの理由
1. 行政運営の基本方針だから 現代の行政は、「行政だけで問題を解決する」時代から「多様な主体と協力して解決する」時代へと転換しています。これは、国の基本方針や自治体の総合計画にも明記されています。
2. 現代的課題への対応に不可欠だから 少子高齢化、防災、環境問題、地域活性化——これらはすべて行政だけでは解決できません。住民、企業、NPO、大学などとの協働が必須です。
3. 公務員に求められる資質を測るテーマだから 協働社会について書くには、以下の能力が必要です:
- 課題認識力(何が問題か)
- コミュニケーション能力(どう協力するか)
- 調整力(意見の違いをどう乗り越えるか)
- 主体性(自分はどう行動するか)
つまり、協働社会のテーマは、公務員としての適性を総合的に評価できる最適なテーマなのです。
「協働社会」とは何か?定義を正しく理解する
作文の冒頭で定義を示す際、曖昧な理解では説得力に欠けます。正確な定義を押さえましょう。
協働社会の定義
協働社会とは、行政・住民・企業・NPO・大学などの多様な主体が、それぞれの特性や強みを活かしながら、対等な立場で共通の目的に向かって協力し、地域や社会の課題を解決していく社会のこと。
「共働」と「協働」の違い
多くの受験生が混同する概念です。明確に区別しましょう。
| 用語 | 読み | 意味 | 重要な点 |
|---|---|---|---|
| 共働 | きょうどう | 単に一緒に働くこと | 目的が別々でもOK |
| 協働 | きょうどう | 同じ目的に向かって協力すること | 共通目的が前提 |
例で理解する
- 共働:同じ職場で働いているが、担当業務は別々
- 協働:防災訓練を実施するため、行政・自治会・消防団が役割分担して準備する
協働社会のキーワード
作文で使える重要概念を整理しましょう。
基本概念
- 多様な主体の参画
- 対等なパートナーシップ
- 共通目的・目標の共有
- 相互理解と信頼関係
- それぞれの強みの活用
具体的な仕組み
- 住民参加・市民参加
- 協議会・審議会
- パブリックコメント
- ワークショップ
- 官民連携(PPP: Public-Private Partnership)
協働社会が求められる背景を理解する
なぜ今、協働が必要なのか?背景を理解することで、作文に深みが出ます。
1. 社会構造の変化
少子高齢化の進行
- 人口減少により税収減少
- 行政サービスの担い手不足
- 高齢者支援ニーズの増大
地域コミュニティの希薄化
- 核家族化、単身世帯の増加
- 近隣関係の弱体化
- 孤立・孤独の問題
2. 行政の限界
財政的制約
- 限られた予算
- 効率的な資源配分の必要性
専門性の限界
- すべての分野を行政がカバーできない
- 民間の専門知識・技術の必要性
3. 多様化するニーズ
画一的サービスの限界
- 個人のニーズの多様化
- きめ細かな対応の必要性
地域特性への対応
- 地域ごとに異なる課題
- 地域住民の知見の重要性
4. 新しい公共の概念
「新しい公共」とは? 2010年代以降、国が推進している考え方。「公共」は行政だけのものではなく、住民・企業・NPOなど多様な主体が担うという理念。
作文の基本構成:3段階+PREP法
協働社会のテーマは抽象的なので、明確な構成が評価を左右します。
基本の3段構成
| 段階 | 内容 | 文字数の目安(800字) | 割合 |
|---|---|---|---|
| 序論 | 定義・背景・問題提起 | 200字前後 | 25% |
| 本論 | 現状分析・課題・具体例・自分の考え | 400字前後 | 50% |
| 結論 | まとめ・公務員としての姿勢・展望 | 200字前後 | 25% |
PREP法で論理的に書く
PREP法とは?
- Point(結論・主張)
- Reason(理由)
- Example(具体例)
- Point(結論の再確認)
協働社会での活用例
【P】協働社会の実現には、行政の姿勢転換が不可欠である。
【R】なぜなら、従来の「サービスを提供する側」から「共に考えるパートナー」
への意識改革が必要だからだ。
【E】例えば、地域防災計画の策定において、行政が一方的に計画を作るのではなく、
住民参加型ワークショップで意見を集め、地域の実情に合った計画を共に作ることで、
実効性が高まる。
【P】したがって、公務員には住民と対等な立場で対話し、信頼関係を築く姿勢が
求められる。
作文で差がつく5つのポイント
ポイント1:理想論だけでなく課題も書く
❌ 浅い作文
協働すればすべてうまくいく。みんなで協力すれば地域は良くなる。
✅ 深い作文
協働には、意見の対立、責任の所在の曖昧さ、時間的コストなどの課題もある。これらを乗り越えるために、行政職員には丁寧な調整力とファシリテーション能力が求められる。
ポイント2:具体例は身近で現実的なものを
❌ 抽象的
協働によって地域が活性化する。
✅ 具体的
私の住む地域では、空き家を活用した子育て支援施設を、自治体・NPO・地元商店街が協働で運営している。行政が場所と初期費用を提供し、NPOが運営ノウハウを提供し、商店街が地域情報を発信することで、多世代交流の場が生まれている。
ポイント3:「自分が何をするか」を明確に
❌ 他人事
行政は住民の声を聞くべきだ。
✅ 主体的
私は公務員として、まず住民の声を丁寧に聞く「傾聴力」を磨きたい。そして、多様な意見を調整し、共通の目標を見出す「調整力」を発揮し、協働の橋渡し役になりたい。
ポイント4:「自助・共助・公助」の視点を入れる
防災分野でよく使われる概念ですが、協働社会全般にも応用できます。
- 自助:個人や家庭での取り組み
- 共助:地域コミュニティでの助け合い
- 公助:行政による支援
作文での使い方
協働社会では、自助・共助・公助のバランスが重要だ。行政が何でも担う「公助」偏重ではなく、住民同士の「共助」を促進し、それを「公助」で支える仕組みが必要である。
ポイント5:時事的な視点を入れる
最近の動向に触れることで、現代的な問題意識を示せます。
使える時事トピック
- Society 5.0と地域課題解決
- SDGsと協働
- デジタル技術を活用した住民参加
- コロナ禍で見えた地域の絆の重要性
- 関係人口・交流人口の創出
よくある失敗パターンと改善策
失敗パターン1:協働=ボランティアと誤解
❌ 誤り
協働社会の実現には、住民がボランティアに参加することが大切だ。
なぜダメか? 協働は単なるボランティア活動ではなく、対等なパートナーシップに基づく課題解決のこと。
✅ 改善
協働社会では、住民は単なるボランティアではなく、行政と対等な立場で地域づくりに参画する主体である。
失敗パターン2:行政主導の発想から抜けていない
❌ 誤り
行政が住民を指導し、協力してもらうことが協働である。
なぜダメか? これは従来の「上から目線」の行政。協働は対等な関係が前提。
✅ 改善
協働社会では、行政は「指導する側」ではなく「共に考えるパートナー」としての姿勢が求められる。
失敗パターン3:美化しすぎて課題に触れない
❌ 誤り
協働すればすべての問題は解決できる。
なぜダメか? 現実には、意見対立、利害調整の難しさ、時間がかかるなどの課題がある。それを認識していないと浅い。
✅ 改善
協働には、意見の対立や調整の難しさという課題もある。しかし、丁寧な対話と相互理解の努力により、これらは乗り越えられる。
失敗パターン4:「私も協力したい」で終わる
❌ 誤り
私も地域の協働に協力したいと思う。
なぜダメか? 抽象的で、具体的な行動が見えない。
✅ 改善
私は公務員として、住民との対話の場を積極的に設け、多様な意見を丁寧に聞く姿勢を大切にしたい。そして、それぞれの強みを活かした役割分担を提案し、協働のコーディネーター役を担いたい。
失敗パターン5:定義がない・間違っている
❌ 誤り
協働とは、みんなで仲良く働くことだ。
なぜダメか? 定義が曖昧・間違っている。
✅ 改善
協働とは、行政・住民・企業・NPOなどが対等な立場で、共通の目的に向かって協力し、地域課題を解決していくことである。
使えるキーワード・フレーズ集
作文で自然に使える「行政らしい言葉」を分類別に紹介します。
協働の基本概念
- 多様な主体の参画
- 対等なパートナーシップ
- 双方向のコミュニケーション
- 共通目標の共有
- 相互理解と信頼関係
- それぞれの強みの活用
- 持続可能な仕組み
行政の役割・姿勢
- 情報共有・情報公開
- 住民参加の促進
- プラットフォームの提供
- コーディネート機能
- 対話の場づくり
- 傾聴の姿勢
- ファシリテーション
住民・地域
- 主体的参加
- 地域コミュニティ
- 自治会・町内会
- 地域資源の活用
- 地域の実情に応じた
- 顔の見える関係
- 自助・共助・公助
企業・NPO
- CSR(企業の社会的責任)
- 専門性の活用
- ノウハウの提供
- 官民連携
- 包括連携協定
- 社会貢献活動
公務員としての姿勢
- 調整力
- コミュニケーション能力
- 柔軟な発想
- 課題解決意識
- 信頼構築
- 寄り添う姿勢
- 橋渡し役
レベル別例文集
【例文1】基本レベル(600字)|地域防災
近年、自然災害の頻発により、地域防災の重要性が高まっている。行政だけでなく、住民・企業・NPOなどが協力して防災力を高める「協働社会」の実現が求められている。
協働社会とは、多様な主体が対等な立場で、共通の目的に向かって協力し、地域課題を解決していく社会のことである。防災分野では、行政が防災計画を作り、住民に周知するという一方向の関係ではなく、住民の意見を反映した計画を共に作り、訓練を共に実施することが重要だ。
私の住む地域では、自治会・消防団・行政が協働で防災訓練を実施している。行政が場所と資機材を提供し、消防団が指導を担当し、自治会が住民への呼びかけを行う。このように役割分担することで、より実効性の高い訓練が実現している。
私は公務員として、住民の声を丁寧に聞き、地域の実情に合った防災体制を共に作りたい。信頼関係を築くことが、いざという時の助け合いにつながると考える。
【例文2】標準レベル(800字)|高齢者支援
近年、少子高齢化の進行により、高齢者の孤立や介護負担の増大が深刻化している。行政だけでこれらの課題に対応することは困難であり、住民・企業・NPOなどが協力して支える「協働社会」の実現が必要である。
協働社会とは、行政・住民・企業・NPOなどの多様な主体が、それぞれの強みを活かしながら、対等な立場で共通の目的に向かって協力し、地域課題を解決していく社会のことである。従来の「行政がサービスを提供する」という一方向の関係から、「共に考え、共に担う」双方向の関係への転換が求められている。
高齢者支援の分野では、自助・共助・公助のバランスが重要だ。個人や家庭での「自助」を基本としつつ、地域での見守りや助け合いという「共助」を促進し、それを行政の「公助」が支える仕組みが効果的である。
私の住む地域では、自治会と市が協働で高齢者見守り活動を行っている。行政が対象者の情報を提供し、民生委員や地域住民が定期的に訪問する。この活動により、孤立の防止や緊急時の早期発見につながっている。
一方で、協働には課題もある。意見の対立、責任の所在の曖昧さ、時間的コストなどである。これらを乗り越えるには、行政職員の調整力とコミュニケーション能力が不可欠だ。
私は将来、公務員として住民の声に耳を傾け、対話を重ねながら信頼関係を築きたい。そして、それぞれの強みを活かした役割分担を提案し、協働のコーディネーター役を担いたい。協働社会の基盤は信頼であり、その積み重ねが誰もが安心して暮らせる地域づくりにつながると考える。
【例文3】応用レベル(1000字)|まちづくり全般
現代社会は、少子高齢化、地域コミュニティの希薄化、財政制約など、複雑で多様な課題に直面している。これらの課題は、行政の力だけでは解決できない。住民・企業・NPO・大学など多様な主体が、それぞれの特性を活かして協力する「協働社会」の実現が不可欠である。
協働社会とは、行政・住民・企業・NPOなどが対等なパートナーシップのもとで、共通の目標に向かって協力し、地域や社会の課題を解決していく社会のことである。ここで重要なのは「対等な関係」という点だ。従来の行政運営では、行政が主導し住民が従うという上下関係があった。しかし協働社会では、行政は「指導する側」ではなく「共に考えるパートナー」としての姿勢が求められる。
協働が求められる背景には、三つの要因がある。第一に、社会構造の変化だ。人口減少により税収が減少し、行政サービスの維持が困難になっている。第二に、ニーズの多様化だ。画一的なサービスではなく、地域や個人の状況に応じたきめ細かな対応が求められている。第三に、新しい公共の概念だ。「公共」は行政だけが担うものではなく、多様な主体が担うという認識が広がっている。
協働の具体例として、私の地域での空き家活用プロジェクトを挙げたい。増加する空き家を地域資源として活用するため、自治体・NPO・地元商店街が協働で子育て支援施設を開設した。行政が空き家の情報提供と改修費用の一部を負担し、NPOが運営ノウハウと人材を提供し、商店街が地域情報の発信と利用者の呼び込みを担当した。この協働により、子育て世代の交流の場が生まれ、商店街の活性化にもつながっている。
しかし、協働には課題もある。第一に、意見や利害の対立である。立場が異なれば、目指す方向も異なることがある。第二に、責任の所在の曖昧さである。役割分担が不明確だと、問題が生じた際に責任の押し付け合いになる恐れがある。第三に、時間的コストである。合意形成には時間がかかり、スピード感が損なわれることもある。
これらの課題を乗り越えるために、行政職員には高度なスキルが求められる。まず、傾聴力である。住民や関係者の声を丁寧に聞き、真のニーズを把握する姿勢が必要だ。次に、調整力である。多様な意見を整理し、共通の目標を見出し、合意形成に導く能力が不可欠だ。さらに、ファシリテーション能力である。対話の場をデザインし、建設的な議論を促進する技術が求められる。
私は将来、公務員としてこれらの能力を磨き、協働社会の実現に貢献したい。具体的には、第一に、住民参加の機会を積極的に設ける。ワークショップや意見交換会を開催し、多様な声を政策に反映させたい。第二に、情報を積極的に公開・共有する。協働の前提は情報の共有であり、透明性の高い行政運営を心がけたい。第三に、失敗を恐れない姿勢を持つ。協働は試行錯誤の連続であり、失敗から学ぶ柔軟性が必要だ。
協働社会は、一朝一夕には実現しない。しかし、一人ひとりの公務員が住民と真摯に向き合い、信頼関係を一つひとつ積み重ねることで、必ず実現できると信じている。私はその一翼を担える公務員になりたい。
分野別の協働事例
作文で使える具体例を分野別に整理しました。
防災分野
- 地域防災計画への住民参加
- 自主防災組織と行政の連携
- 避難所運営の協働体制
- 防災訓練の共同実施
福祉分野
- 高齢者見守りネットワーク
- 子育て支援の官民協働
- 障がい者就労支援
- 地域包括ケアシステム
環境分野
- ごみ減量・リサイクル活動
- 公園や河川の清掃活動
- 環境教育プログラム
- 再生可能エネルギー事業
まちづくり分野
- 空き家活用プロジェクト
- 商店街活性化
- 公共施設の運営参加
- 地域イベントの企画運営
教育分野
- 学校運営協議会
- 地域住民による学習支援
- キャリア教育での企業連携
- 放課後子ども教室
採点者が見ているポイント
公務員試験の作文で、採点者は何を評価しているのでしょうか?
評価の4つの観点
1. 理解度(25点)
- 協働社会の概念を正しく理解しているか
- 背景や必要性を説明できているか
2. 論理性(25点)
- 主張と根拠が論理的につながっているか
- 構成が明確で読みやすいか
3. 具体性(25点)
- 抽象論だけでなく具体例があるか
- 実現可能な提案ができているか
4. 主体性(25点)
- 自分がどう行動するかが明確か
- 公務員としての姿勢が示されているか
高得点のポイント
✅ 課題認識が深い:理想だけでなく、現実の困難も理解している ✅ 具体例が適切:身近で説得力のある事例を挙げている ✅ 主体的な姿勢:「私は〜したい」と明確に書いている ✅ 公務員らしい表現:適切な用語・フレーズを使っている
書く前の準備チェックリスト
作文を書き始める前に、以下を確認しましょう。
内容の準備
- [ ] 協働社会の正しい定義を理解している
- [ ] なぜ協働が必要なのか(背景)を説明できる
- [ ] 具体例を1〜2つ用意している
- [ ] 協働の課題も理解している
- [ ] 自分がどう行動するかを考えている
構成の準備
- [ ] 序論・本論・結論の構成を決めている
- [ ] 各段落で何を書くか決めている
- [ ] PREP法を意識している
- [ ] 文字数配分を決めている
表現の準備
- [ ] 使いたいキーワードをリストアップ
- [ ] 「〜だ・である調」で統一
- [ ] 公務員らしい丁寧な表現を意識
よくある質問(FAQ)
Q1. 協働社会と共生社会の違いは?
A.
- 協働社会:多様な主体が協力して課題解決する社会
- 共生社会:多様な人々が互いの違いを認め合い共に生きる社会
協働は「課題解決の方法」、共生は「社会のあり方」という違いがあります。
Q2. 具体例が思いつかない場合は?
A. 以下のような一般的な例でOKです:
- 地域防災訓練
- 高齢者見守り活動
- 公園清掃活動
- 子育て支援イベント
自分の体験でなくても、「〜という取り組みがある」と書けば問題ありません。
Q3. 文字数が足りない場合は?
A. 以下を追加しましょう:
- 協働の課題とその解決策
- 複数の具体例
- 自分の行動の具体化
- 背景の詳しい説明
Q4. 「協働」以外に似たテーマはある?
A. はい、以下は関連テーマです:
- 住民参加
- 市民協働
- 官民連携
- パートナーシップ
- コミュニティの再生
基本的な考え方は同じです。
Q5. 面接で協働について聞かれたら?
A. 作文と同じ考え方で答えましょう:
- 協働の定義を簡潔に
- なぜ必要かを説明
- 具体例を挙げる
- 自分がどう行動するかを述べる
まとめ:協働社会は「対等なパートナーシップ」がカギ
協働社会の作文で最も重要なのは、「行政と住民が対等な立場で共に課題を解決する」という視点です。
押さえるべき3つのポイント
1. 正しい定義 協働 = 多様な主体が対等な立場で、共通目的に向かって協力すること
2. 現実的な課題認識 理想だけでなく、意見対立や調整の難しさも理解する
3. 主体的な行動宣言 「私は公務員として〜したい」と具体的に書く
構成の鉄則
序論:定義+背景(200字)
↓
本論:現状+具体例+課題+解決策(400字)
↓
結論:公務員としての姿勢+展望(200字)
この構造を守り、PREPを意識すれば、説得力のある作文になります。
協働社会の実現は、一人ひとりの公務員の姿勢から始まります。住民の声に耳を傾け、信頼関係を築き、共に地域をつくる——その覚悟と具体的な行動を、作文で示しましょう。
関連記事
- 【2025年最新】大学1年生必見!教授が高評価する実践的レポート作成完全マニュアル
- 大学生・社会人の必須文章! レポートの書き方と基本テクニック(ひな型・テンプレート付き)
- 【初心者向け】レポート・論文に使える情報源&資料の探し方まとめ
- レポート・論文の作成に役立つ「テキスト批評」とは
この記事が役に立ったら、ブックマークして試験対策にお役立てください!
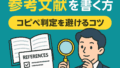
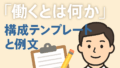
コメント