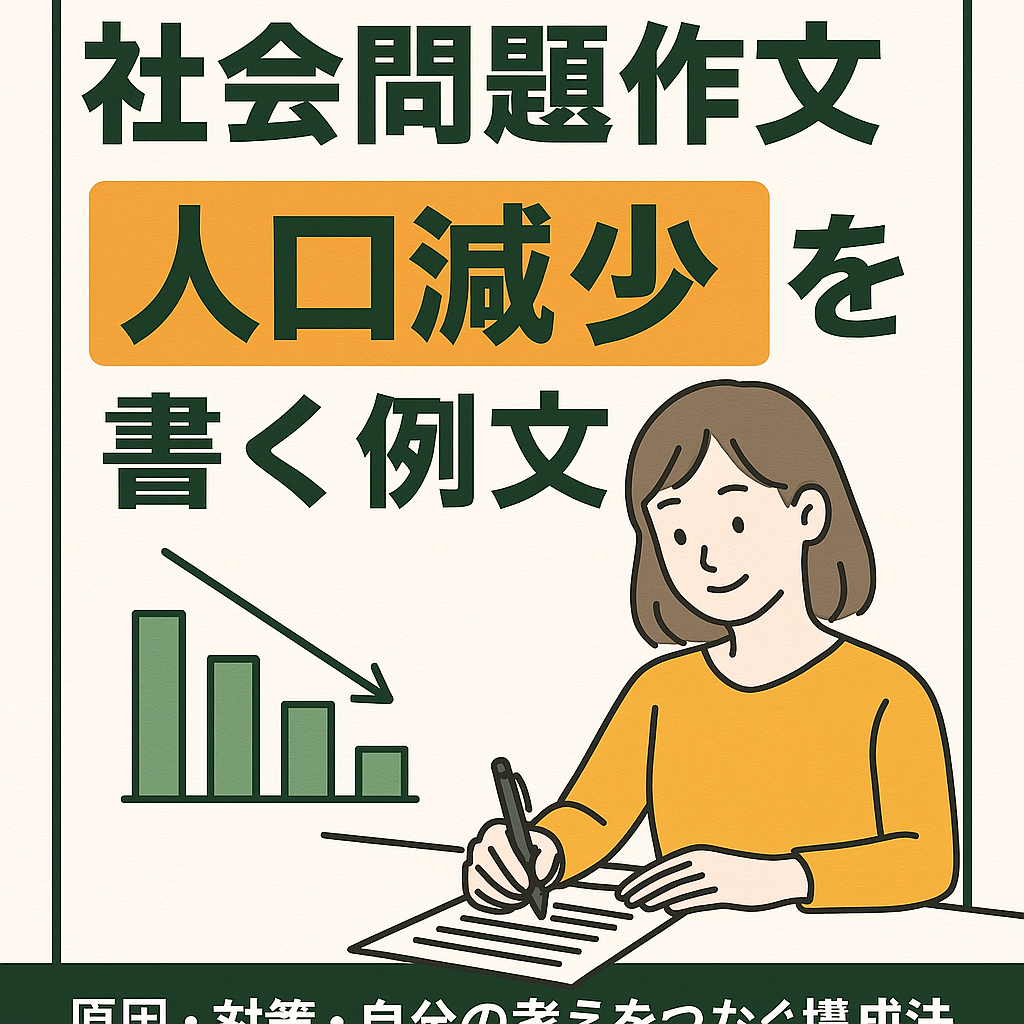
「人口減少」は、高校入試、大学入試、公務員試験で最も出題頻度が高い社会問題テーマの一つです。
人口減少が重視される3つの理由
1. 日本社会の最重要課題だから
- 2008年をピークに日本の人口は減少し続けている
- 2050年には人口が1億人を割ると予測されている
- 経済、社会保障、地域社会のすべてに影響する
2. 多角的な思考力を測れるから
- 原因分析力(なぜ起きているか)
- 影響理解力(何が問題か)
- 解決提案力(どうすればいいか)
- 自分との関連づけ(どう行動するか)
3. 受験生の社会への関心度を見られるから
- ニュースや新聞を読んでいるか
- 社会問題を自分事として考えられるか
- 将来の社会を担う意識があるか
採点者が見ているポイント
✅ 問題の本質を理解しているか 単なる「人口が減る」ではなく、少子化・高齢化・地方衰退など、多面的に捉えられているか
✅ 原因を論理的に分析できるか 「なぜそうなるのか」を、表面的でなく構造的に説明できるか
✅ 具体的な対策を提案できるか 抽象論ではなく、実現可能で具体的な解決策を示せるか
✅ 自分の立場から考えられるか 社会問題を自分事として捉え、自分にできることを述べられるか
人口減少の基礎知識:書く前に押さえるべき事実
作文を書く前に、基本的な事実を理解しておきましょう。
日本の人口減少の現状
数字で見る人口減少
- 2008年:1億2808万人(ピーク)
- 2023年:1億2435万人(約373万人減少)
- 2050年:約9700万人(予測)
- 2100年:約5000万人(予測)
少子高齢化の進行
- 合計特殊出生率:1.26(2022年)→人口維持には2.07必要
- 高齢化率(65歳以上の割合):29.1%(2023年)
- 2040年には3人に1人が高齢者に
人口減少の原因
1. 少子化(出生率の低下)
- 晩婚化・未婚化の進行
- 子育てにかかる経済的負担
- 仕事と育児の両立の困難
- 価値観の多様化
2. 高齢化(平均寿命の延び)
- 医療技術の進歩
- 生活環境の改善
- 健康意識の向上
3. 地方からの人口流出
- 若者の都市部への集中
- 地方の雇用機会の減少
- 教育・医療・商業施設の不足
人口減少の影響
経済への影響
- 労働力不足
- 経済規模の縮小
- 市場の縮小
- 税収の減少
社会保障への影響
- 年金・医療・介護の負担増
- 現役世代の負担増加
- 社会保障制度の維持困難
地域社会への影響
- 過疎化の進行
- 公共サービスの維持困難
- コミュニティの衰退
- 空き家・耕作放棄地の増加
作文の基本構成:三段構成
人口減少をテーマにした作文は、以下の三段構成が基本です。
基本構成テンプレート(600字の場合)
| 段落 | 内容 | 文字数の目安 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 序論 | 問題提起・現状の説明・問題意識 | 150字前後 | 25% |
| 本論 | 原因分析・影響の説明・対策の提案・自分の考え | 350字前後 | 58% |
| 結論 | まとめ・自分の行動・将来への展望 | 100字前後 | 17% |
各段落の書き方:詳細解説
序論(第1段落):問題提起と現状説明
序論の役割
- 人口減少という問題を提示する
- 現状や深刻さを示す
- 自分がどの視点から論じるかを示す
書き方のパターン
パターン1:数字で示す
日本の人口は2008年をピークに減少し続けており、2050年には1億人を割ると予測されている。少子高齢化が進む中で、この問題は日本社会の持続可能性に関わる重要な課題である。私はこの問題を、「次世代が安心して暮らせる社会をどう作るか」という視点から考えたい。
パターン2:地域の実感から入る
私の住む地域では、小学校の統廃合が進み、商店街にはシャッターが目立つ。これらは人口減少がもたらす現実である。人口が減ることで、地域の活力が失われ、生活の質が低下している。この問題にどう向き合うかが、私たちの世代に問われている。
パターン3:将来の影響から始める
2050年、私たちが40代になる頃、日本の人口は今より2000万人以上減少していると予測されている。働く人が減り、支えられる高齢者が増える社会で、私たちはどう生きていけばよいのか。この問いに向き合うことが、今を生きる私たちの責任だと考える。
本論(第2〜3段落):原因・影響・対策
本論の構成パターン
【パターンA:原因→対策→自分の考え】
1. なぜ人口が減少しているのか(原因分析)
2. どうすれば解決できるか(対策提案)
3. 自分はどう考え、どう行動するか
【パターンB:影響→原因→対策】
1. 人口減少が何をもたらすか(影響の説明)
2. なぜそうなっているのか(原因分析)
3. 解決に向けて何ができるか(対策と自分の行動)
【パターンC:問題の多面性を示す】
1. 経済面での問題
2. 社会面での問題
3. 地域面での問題
4. それぞれへの対策と自分の関わり
原因を書くときのポイント
✅ 複数の原因を示す 「一つの原因は〜、もう一つは〜」と多角的に
✅ 身近な視点を入れる 「私の母も〜」など、実感を伴う説明
✅ 構造的に説明する 表面的な原因だけでなく、その背景にあるものも
対策を書くときのポイント
✅ 具体的な提案をする 「支援を増やす」ではなく「〇〇という制度を導入する」
✅ レベル分けをする 国・自治体・地域・個人など、複数のレベルで考える
✅ 実現可能性を示す すでに成功している事例があれば触れる
本論の例文
例1:原因分析重視型
人口減少の最大の原因は、少子化の進行にある。その背景には、経済的不安、子育て環境の不足、価値観の変化など、複数の要因が絡み合っている。
私の両親の世代は、3人きょうだいが普通だったと聞く。しかし今は、子ども一人を育てるのに数千万円かかると言われ、経済的負担が重い。また、待機児童問題や長時間労働により、仕事と育児の両立が困難な状況もある。さらに、「結婚や出産が人生の必須条件ではない」という価値観も広がり、ライフスタイルが多様化している。
これらの問題に対しては、児童手当の拡充、保育所の増設、企業の働き方改革など、総合的な対策が必要だ。特に、男性の育児参加を促す制度の充実は、女性が仕事と子育てを両立しやすくするために重要だと考える。
例2:地域の視点重視型
人口減少は、特に地方で深刻な問題となっている。私の祖父母が住む田舎では、若者が都市部に流出し、高齢者だけが残される「限界集落」化が進んでいる。
夏休みに祖父母の家を訪れると、かつて賑わっていた商店街は閑散とし、学校は統廃合されていた。若者が地元を離れる理由は、仕事がないことだ。農業だけでは生活が成り立たず、都市部に出るしかない現実がある。
この問題を解決するには、地方に雇用を創出することが不可欠だ。例えば、リモートワークの普及により、地方でも都市部の仕事ができる環境を整える。また、地域の特産品を活かした観光業や、再生可能エネルギー事業など、新しい産業を育てることも重要だ。私は、将来地元に戻り、地域活性化に関わる仕事がしたいと考えている。
結論(最終段落):まとめと自分の行動
結論の役割
- 自分の主張を再確認
- 自分がどう行動するかを示す
- 前向きで希望のある締めくくり
書き方のポイント
✅ 悲観的に終わらない 問題は深刻だが、「だからこそ〜」と前向きに
✅ 自分の行動を具体的に 「頑張りたい」ではなく「〇〇をしたい」
✅ 社会への願いも添える 個人の行動と社会の変化を両方示す
結論の例文パターン
パターン1:個人の行動重視
人口減少は深刻な問題だが、悲観するだけでは何も変わらない。私は、まず自分の家族や地域を大切にし、支え合いの輪を広げたい。そして将来は、子育てしやすい社会を作る仕事に関わりたいと考えている。一人ひとりの小さな行動が、社会を変える力になると信じている。
パターン2:社会への提言重視
人口減少問題の解決には、国や自治体の政策転換が不可欠だ。しかし、政策を待つだけでなく、私たち自身が地域で支え合うことも重要だ。私は、ボランティア活動や地域行事に積極的に参加し、世代を超えたつながりを作りたい。人口が減っても、温かいつながりのある社会を、共に作っていきたい。
パターン3:将来世代への責任
人口減少がもたらす課題は、私たちの世代が必ず直面する現実だ。だからこそ、今から準備し、行動することが大切だ。私は、社会問題に関心を持ち続け、将来は政策立案に関わる仕事がしたいと考えている。次の世代が希望を持てる社会を残すことが、私たちの責任だと思う。
レベル別・視点別の例文集
【例文1】基本レベル(600字・高校入試向け)|子育て支援の視点
日本では少子高齢化が進み、人口が減少しています。このままでは、働く人が減り、経済や地域の活力が失われてしまう恐れがあります。私はこの問題を、「次の世代が安心して暮らせる社会をどう作るか」という視点から考えたいと思います。
人口が減少する原因の一つは、子育てにかかる負担の大きさにあります。保育所が不足しているため、仕事と育児の両立が難しい家庭が多くあります。また、教育費も高く、経済的な不安から子どもを持つことをためらう人もいます。私の母も、仕事と家事の両立に苦労しており、家族で協力することの大切さを実感しました。
この問題を解決するには、社会全体で子育てを支える仕組みが必要だと思います。例えば、保育所を増やすこと、児童手当を充実させること、企業が育児休暇を取りやすくすることなどです。また、地域で子どもを見守る活動も、親の負担を減らすことにつながります。
私は将来、社会の一員として、家族や地域を支えられる人になりたいです。人口が減っても、みんなが笑顔で支え合える社会を作ることが、私の願いです。
【例文2】標準レベル(800字・大学入試向け)|地方創生の視点
日本の人口は2008年をピークに減少を続けており、2050年には1億人を割ると予測されている。特に地方では、若者の流出により過疎化が深刻化し、地域社会の存続が危ぶまれている。私は、この問題を「地方の活力をどう維持するか」という視点から考察したい。
人口減少の要因は複数あるが、地方に焦点を当てると、雇用機会の不足が最大の原因である。私の祖父母が住む地域では、主要産業だった農業の担い手が減少し、若者は都市部に職を求めて流出している。結果として、高齢者だけが残り、商店街は閑散とし、公共交通機関も縮小されている。この悪循環が、地方の衰退を加速させている。
また、教育や医療などの生活インフラの不足も、若い世代が地方を離れる理由となっている。子育て世代にとって、質の高い教育環境や医療機関へのアクセスは不可欠だが、地方ではこれらが不十分な場合が多い。
この問題に対して、私は二つの対策が重要だと考える。第一に、地方に新しい雇用を創出することだ。リモートワークの普及により、地方に住みながら都市部の企業で働くことが可能になった。自治体は、高速インターネット環境の整備や、サテライトオフィスの誘致を進めるべきだ。また、地域資源を活かした観光業や、再生可能エネルギー事業など、新産業を育成することも有効である。
第二に、生活環境の魅力を高めることだ。自然豊かな環境、ゆとりある生活空間、温かいコミュニティなど、地方ならではの価値を発信する。実際に、移住支援制度を充実させた自治体では、若い世代の移住が増加している事例もある。
私自身、将来は地元に戻り、地域活性化に関わる仕事がしたいと考えている。人口減少は避けられない現実だが、それを前提とした上で、質の高い生活ができる地域社会を作ることは可能だ。都市と地方がそれぞれの特性を活かし、人々が自由に選択できる社会を目指したい。
【例文3】応用レベル(1000字・公務員試験向け)|多角的分析
日本の人口減少は、経済、社会保障、地域社会のすべてに影響を及ぼす、日本社会が直面する最大の構造的課題である。2008年の1億2808万人をピークに減少を続け、2050年には9700万人程度になると予測される。この変化は、単なる人数の減少ではなく、社会システム全体の再構築を迫るものである。
人口減少の要因を分析すると、少子化と高齢化という二つの側面がある。合計特殊出生率は1.26(2022年)と、人口維持に必要な2.07を大きく下回っている。この背景には、経済的要因、社会構造的要因、価値観の変化が複雑に絡み合っている。
経済的要因として、子育てにかかる費用の高さが挙げられる。内閣府の試算によれば、子ども一人を大学卒業まで育てるのに約3000万円かかるとされる。非正規雇用の増加や所得の伸び悩みにより、経済的不安が出産をためらわせている。
社会構造的要因として、仕事と育児の両立の困難さがある。長時間労働が常態化し、育児休業制度があっても取得しにくい職場環境が、特に女性のキャリア形成を阻害している。待機児童問題も依然として解決していない。
価値観の変化も重要な要因だ。個人の自由や自己実現を重視する価値観が広がり、結婚や出産が「当然の選択」ではなくなっている。これ自体は否定されるべきことではないが、多様な生き方を認めつつ、子どもを持ちたい人が安心して持てる環境を整えることが必要だ。
人口減少がもたらす影響は多岐にわたる。経済面では、労働力人口の減少により、GDP成長率の低下や、産業の競争力低下が懸念される。社会保障面では、現役世代の負担増加が避けられず、制度の持続可能性が問われている。地域社会では、過疎化により公共サービスの維持が困難になり、コミュニティの崩壊が進んでいる。
これらの課題に対して、私は三層の対策が必要だと考える。
第一に、国レベルでの総合的な少子化対策である。児童手当の拡充、保育の無償化、高等教育費の負担軽減など、経済的支援を強化すべきだ。同時に、男性の育児参加を促進するため、育児休業の取得を義務化することも検討すべきである。フランスなど、積極的な家族政策により出生率を回復させた国の事例も参考にできる。
第二に、働き方改革の徹底である。長時間労働を是正し、柔軟な働き方を可能にすることで、仕事と育児の両立を実現する。リモートワークの普及は、この点で大きな可能性を秘めている。企業文化の変革も不可欠であり、育児休業を取得しやすい雰囲気作りが求められる。
第三に、地方創生である。若者の都市部への集中を緩和するため、地方に魅力的な雇用を創出する。デジタル技術を活用した新産業の育成、地域資源を活かした観光業の振興、移住支援制度の充実などが有効だ。
しかし、政策だけでは不十分である。社会全体で、子育てを応援する文化を育てることが重要だ。地域での子育て支援、職場での理解、多様な家族のあり方を認める寛容さなど、一人ひとりの意識と行動が社会を変える。
私は公務員として、これらの政策の立案と実施に関わりたいと考えている。人口減少は避けられない現実だが、それを前提とした上で、すべての人が安心して暮らせる社会を設計することは可能だ。量ではなく質を重視し、持続可能で包摂的な社会を、次世代に残すことが私たちの責務である。
視点別の書き方:5つのアプローチ
1. 経済的視点
焦点:労働力不足、経済成長、社会保障
主張の例
人口減少による労働力不足は、経済成長を阻害する。AI・ロボット技術の活用や、外国人労働者の受け入れなど、多様な対策が必要だ。
2. 子育て支援の視点
焦点:保育、教育費、ワークライフバランス
主張の例
子育てにかかる経済的・時間的負担を軽減する社会的支援が不可欠だ。社会全体で子どもを育てる意識が重要である。
3. 地方創生の視点
焦点:過疎化、地方の雇用、移住促進
主張の例
地方に魅力的な雇用と生活環境を整備し、若者の流出を防ぐことが、地域の持続可能性の鍵となる。
4. 高齢社会への対応の視点
焦点:高齢者の活躍、介護、世代間交流
主張の例
高齢者を「支えられる側」だけでなく、「社会を支える側」としても位置づけ、活躍の場を広げることが重要だ。
5. ライフスタイルの多様化の視点
焦点:価値観の変化、多様な生き方の尊重
主張の例
結婚・出産を強制せず、多様な生き方を認めつつ、子どもを持ちたい人が安心して持てる環境を整えることが大切だ。
よくある失敗パターンと改善策
失敗パターン1:現状説明だけで終わる
❌ NG例
日本では人口が減っています。少子化と高齢化が進んでいます。これは大きな問題です。
なぜダメか?
- 自分の考えがない
- 対策が示されていない
- 誰でも書ける内容
✅ 改善例
日本では人口が減少し、2050年には1億人を割ると予測される。この問題に対して、私は子育て支援の強化が最も重要だと考える。経済的支援と働き方改革により、若い世代が安心して子どもを持てる社会を作るべきだ。
失敗パターン2:抽象的な対策だけ
❌ NG例
人口減少を解決するには、みんなが協力することが大切です。政府も頑張るべきです。
なぜダメか?
- 具体性がない
- 「みんな」「頑張る」は空虚
- 実現可能性が不明
✅ 改善例
人口減少対策として、第一に児童手当を月3万円に増額し、第二に保育所を5年で10万人分増設し、第三に男性の育児休業取得を義務化すべきだ。これらの具体的施策により、子育て環境を改善できる。
失敗パターン3:悲観的に終わる
❌ NG例
人口減少は止められないので、日本の未来は暗いです。私たちにできることはありません。
なぜダメか?
- ネガティブで読後感が悪い
- 諦めの姿勢
- 前向きさがない
✅ 改善例
人口減少は深刻だが、悲観するだけでは何も変わらない。一人ひとりが家族や地域を大切にし、支え合うことで、人口が減っても豊かな社会を作れる。私はその実現に貢献したい。
失敗パターン4:自分と無関係に書く
❌ NG例
政府は対策をすべきです。企業も努力すべきです。社会が変わるべきです。
なぜダメか?
- 他人事
- 自分の関わりが見えない
- 評論家的
✅ 改善例
政府や企業の対策は重要だが、私たち一人ひとりにもできることがある。私は、地域の子育て支援ボランティアに参加し、将来は子育てしやすい社会を作る仕事に就きたい。
採点基準:5つの評価ポイント
1. 問題理解度(20点)
✅ 人口減少の現状を正しく理解している ✅ 少子化・高齢化の両面を認識している ✅ 多面的な影響を理解している
2. 原因分析力(20点)
✅ 複数の原因を挙げている ✅ 表面的でなく構造的に分析している ✅ 因果関係が論理的に説明されている
3. 解決提案力(20点)
✅ 具体的で実現可能な対策を示している ✅ 複数のレベル(国・地域・個人)で考えている ✅ 独自の視点や工夫がある
4. 自分との関連づけ(20点)
✅ 自分の経験や観察を含めている ✅ 自分にできることを具体的に示している ✅ 将来の行動につなげている
5. 文章力(20点)
✅ 構成が明確(序論・本論・結論) ✅ 論理的で読みやすい ✅ 適切な語彙と表現
書く前の準備:3ステップ
ステップ1:情報収集
知っておくべき数字
- 現在の人口
- 出生率
- 高齢化率
- 将来予測
知っておくべきキーワード
- 少子高齢化
- 合計特殊出生率
- 労働力人口
- 社会保障
- 過疎化
- 限界集落
ステップ2:自分の視点を決める
どの視点から論じるか選ぶ:
- [ ] 子育て支援
- [ ] 経済・労働力
- [ ] 地方創生
- [ ] 高齢社会
- [ ] 多様な生き方
ステップ3:構成メモを作る
【序論】
現状:
問題意識:
【本論】
原因:
影響:
対策:
自分の考え:
【結論】
自分の行動:
社会への願い:
提出前チェックリスト
内容のチェック
- [ ] 人口減少の現状が示されているか
- [ ] 原因が複数挙げられているか
- [ ] 影響が具体的に説明されているか
- [ ] 対策が具体的に提案されているか
- [ ] 自分の考えが明確に示されているか
- [ ] 自分にできることが書かれているか
- [ ] 前向きな締めくくりになっているか
構成のチェック
- [ ] 序論・本論・結論の構成になっているか
- [ ] 論理的な流れがあるか
- [ ] 段落が適切に分かれているか
表現のチェック
- [ ] 「です・ます調」または「だ・である調」で統一されているか
- [ ] 誤字脱字がないか
- [ ] 数字やデータは正確か
- [ ] 適切な専門用語を使っているか
よくある質問(FAQ)
Q1. 数字やデータを覚えていない場合は?
A. 正確な数字を覚えていなくても問題ありません。「約〇〇万人」「〇割程度」など、おおよその数字で構いません。重要なのは、問題の深刻さを示すことです。
Q2. 原因と対策、どちらを重視すべき?
A. 試験によりますが、一般的には対策と自分の考えを重視しましょう。原因分析は簡潔にし、「どうすべきか」「自分はどう関わるか」に重点を置きます。
Q3. 移民・外国人労働者について書いてもいい?
A. はい。ただし、賛否が分かれるテーマなので、一方的な主張ではなく、バランスの取れた記述を心がけましょう。
Q4. 地方と都市、どちらの視点で書くべき?
A. 自分の経験に基づいて選びましょう。地方出身なら地方の視点、都市部なら都市の視点で書くと、リアリティが出ます。
Q5. 文字数が足りない場合は?
A. 以下を追加しましょう:
- 影響の具体例(経済・社会・地域)
- 対策の詳細(誰が・何を・どのように)
- 成功事例の紹介
- 自分の経験や観察
まとめ:社会問題を「自分事」として考える
人口減少は、日本社会が直面する最も重要な課題の一つです。作文では、この問題を「遠い社会の話」ではなく、**「自分の未来に関わる問題」**として捉えることが重要です。
高評価を得る作文の3要素
1. 深い理解 現状・原因・影響を多面的に理解している
2. 具体的な提案 実現可能で説得力のある対策を示す
3. 主体的な姿勢 自分がどう関わるかを明確に示す
最後に
「正解」を書こうとする必要はありません。大切なのは、あなた自身がこの問題をどう捉え、どう向き合おうとしているかです。
ニュースの受け売りではなく、日常の観察や経験から考えたこと、自分なりの提案を、誠実に書いてください。それが、最も説得力のある作文になります。
関連記事
- 【2025年最新】大学1年生必見!教授が高評価する実践的レポート作成完全マニュアル
- 大学生・社会人の必須文章! レポートの書き方と基本テクニック(ひな型・テンプレート付き)
- 【初心者向け】レポート・論文に使える情報源&資料の探し方まとめ
- レポート・論文の作成に役立つ「テキスト批評」とは
この記事が役に立ったら、ブックマークして受験対策にお役立てください!
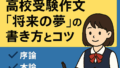

コメント