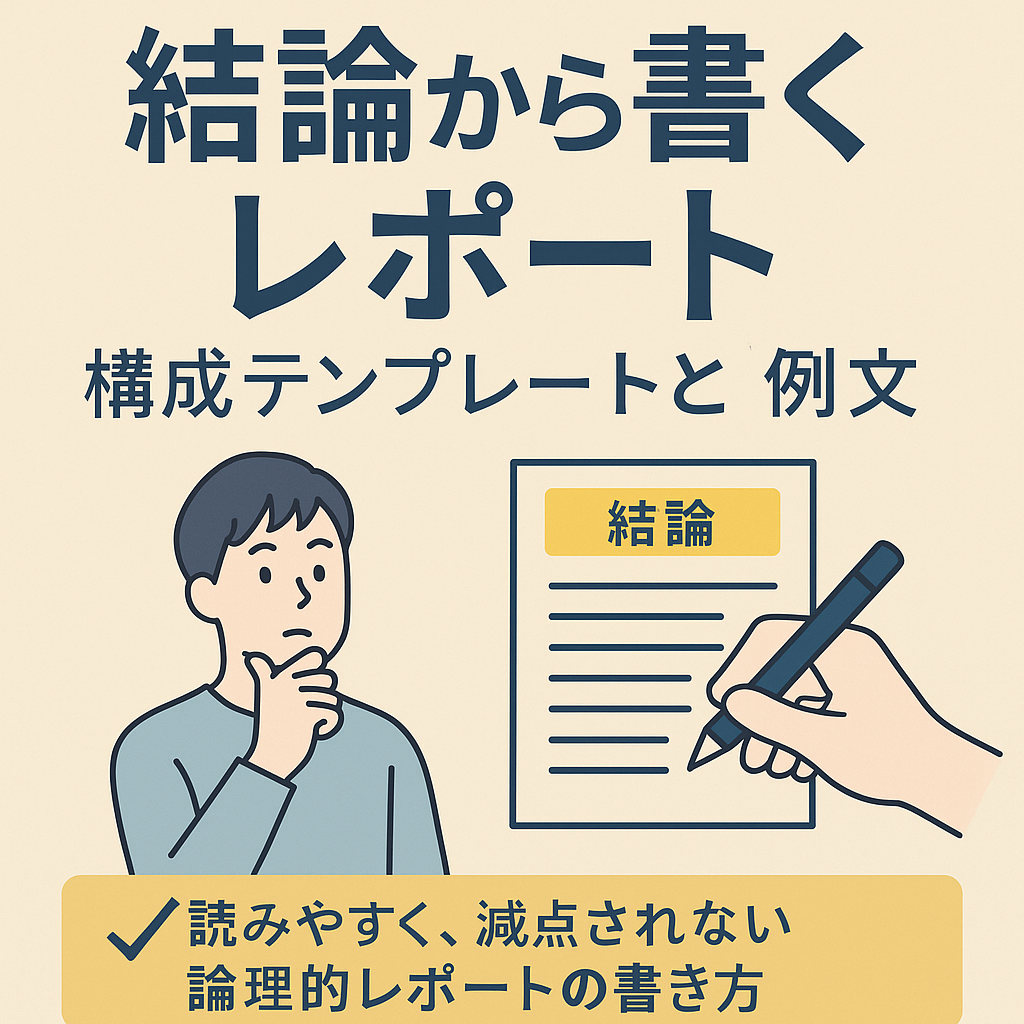
「何を言いたいのかわからない」「結論が見えない」——大学のレポートでこんなコメントをもらったことはありませんか?
その原因は、結論を最後まで書かない構成にあります。 大学レポートで高評価を得るには、「結論から書く」=結論ファーストの構成が必須です。
この記事では、誰でもすぐに使えるテンプレートと具体的な例文を使って、論理的で読みやすいレポートの書き方を徹底解説します。コピペOKのテンプレート付きなので、今日からすぐに実践できます!
なぜ大学レポートは「結論から書く」べきなのか?
教授が求めているのは「主張の明確さ」
大学教授は1回の採点で数十〜数百枚のレポートを読みます。最初の3行で「この学生は何を主張しているのか」が分からないと、それだけで評価が下がります。
結論を最初に示すことで、教授は「この学生の論点」を即座に理解でき、その後の論証を追いやすくなります。
結論ファースト(結論先行型)の3つのメリット
- 主張が明確で論点がブレない——何について論じているかが一目瞭然
- 論理的な構成を作りやすい——結論を証明する形で本論を組み立てられる
- 説得力が増す——「主張→根拠→事例→再主張」の流れで読者を納得させられる
つまり、「結論→理由→事例→まとめ」という構成にするだけで、論理的で読まれやすいレポートになります。
結論から書くレポートの基本構成【4段階テンプレート】
以下が、結論ファーストレポートの黄金構成です。この型に沿って書けば、どんなテーマでも論理的なレポートが完成します。
【コピペOK】結論ファースト構成テンプレート
| 段階 | 内容 | 文字数の目安(2000字の場合) | 書くべきこと |
|---|---|---|---|
| 序論 | 主張(結論)を最初に明示 | 約200〜300字(15%) | 「私は〜と考える」で結論を述べる |
| 本論① | 理由1:理論的・社会的根拠 | 約400〜500字(30%) | 「なぜなら〜」で一般的な根拠を示す |
| 本論② | 理由2:具体例・データ | 約400〜500字(30%) | 「例えば〜」で具体的事例を提示 |
| 結論 | 再主張+今後の展望・課題 | 約200〜300字(15%) | 「以上から〜」で主張を再確認 |
合計:1,200〜1,600字(2000字レポートの場合)
各段階で書くべき内容の詳細
序論のポイント
- 1文目で結論(主張)を明確に述べる
- 背景説明は2〜3行程度に抑える
- 「私は〜と考える」「〜であると主張する」など断定的な表現を使う
本論①のポイント
- 理論や先行研究、社会的背景などの一般的根拠を示す
- 「〜という研究がある」「〜と指摘されている」など客観的事実を引用
本論②のポイント
- 具体的なデータ、事例、ニュース、統計などを提示
- 「例えば〜」「実際に〜」で始めると書きやすい
結論のポイント
- 序論で述べた主張を別の言葉で再度述べる
- 今後の課題や展望を1〜2文加える
- 新しい情報は入れない
【例文付き】結論ファーストレポートの実例
実際に結論ファースト構成を使ったレポート例を紹介します。そのままコピペして、自分のテーマに置き換えて使ってください。
テーマ:「SNSは人間関係を希薄にするか」
【序論】(約250字)
私は、SNSは人間関係を希薄にするのではなく、むしろ多様化させると考える。確かに、SNS上でのトラブルや誹謗中傷が社会問題として取り上げられることは事実である。しかし、それはSNSの一側面に過ぎず、本質的な機能ではない。現代社会において、SNSは地理的・時間的制約を超えた新たなコミュニケーション手段として、人間関係の選択肢を広げている。本レポートでは、SNSが人間関係に与える肯定的影響について、理論的根拠と具体例をもとに論じる。
【本論①:理論的根拠】(約400字)
まず、SNSは情報発信と交流の機会を個人に開いた点で、コミュニケーション史上画期的な発明である。社会学者マニュエル・カステルズ(2009)は、インターネットが「ネットワーク社会」を形成し、従来の地理的制約を超えた新しい社会的つながりを生み出したと指摘している。従来の人間関係は、学校や職場、地域コミュニティなど物理的な場所に依存していた。しかし、SNSの登場により、同じ趣味や価値観を持つ人々が国境や時間を超えて容易につながれるようになった。この点で、人間関係の「選択肢」が大幅に拡張されたといえる。つまり、SNSは既存の関係を代替するのではなく、新しい関係性の形を追加したのである。
【本論②:具体例・データ】(約450字)
さらに、コロナ禍以降の社会状況を見ると、SNSが孤立を防ぐ重要な手段として機能した事実が確認できる。総務省の調査(2021)によれば、2020年以降、オンラインコミュニティへの参加率が前年比で約35%増加した。特に若年層においては、オンライン学習コミュニティやボランティア活動への参加が顕著に増加している。例えば、Twitterでは医療従事者への感謝を示す「#ありがとう医療従事者」といったハッシュタグ運動が広がり、見知らぬ人々が社会課題に対して連帯する姿が見られた。また、InstagramやDiscordを通じて、趣味のコミュニティに参加し、リアルでは出会えなかった他者と深い交流を持つケースも増えている。このことから、SNSは人間関係の質を多様化させ、新しい形の社会的つながりを創出していると考えられる。
【結論】(約250字)
以上の理由から、SNSは人間関係を希薄化させるというよりも、「多様化と選択の自由」をもたらすコミュニケーションツールであると結論づけられる。従来の対面中心の関係性に加えて、オンラインでの新しい交流形態が生まれたことで、個人は自分に合った関係性を選択できるようになった。ただし、今後はSNSを適切に使いこなすための情報リテラシーや、オンライン上での倫理観の教育がより重要になるだろう。SNSの可能性を最大限に活かしつつ、負の側面を最小化する社会的取り組みが求められる。
結論ファーストで失敗する3つのパターンと改善策
多くの学生が陥りがちな失敗パターンと、その具体的な改善方法を紹介します。
失敗パターン1:序論で背景説明ばかりして結論が出てこない
問題点 「近年、SNSが普及している。総務省によれば…」と延々と背景を書いて、結論が本論まで出てこない。
改善策 序論の1文目で必ず「私は〜と考える」と結論を述べる。背景説明は2〜3行に抑える。
改善例 ❌ 「近年、SNSの普及により…統計によれば…問題も指摘されている。」 ✅ 「私はSNSが人間関係を多様化させると考える。近年のSNS普及により…」
失敗パターン2:結論と本論で同じ内容を繰り返している
問題点 序論で述べた主張を、本論でも結論でもそのまま繰り返すだけで、内容が深まらない。
改善策
- 本論では「なぜそう言えるのか」の根拠と事例を詳しく説明
- 結論では主張に加えて「今後の課題」や「展望」を追加
改善例 ❌ 結論:「SNSは人間関係を多様化させる。」(繰り返すだけ) ✅ 結論:「SNSは人間関係を多様化させる。今後は情報リテラシー教育が課題である。」
失敗パターン3:本論が感想中心で根拠が弱い
問題点 「私も〜と思う」「〜な気がする」など、主観的な感想ばかりで客観的根拠がない。
改善策
- 先行研究、統計データ、ニュース記事などの客観的情報を引用
- 「〜と指摘されている」「〜というデータがある」など断定的表現を使う
改善例 ❌ 「SNSで友達が増えた気がする。」 ✅ 「総務省の調査(2021)によれば、SNS利用者の67%が新しい交流が生まれたと回答している。」
結論ファーストで書く実践3ステップ【30分で完成】
時間がない時でも、この3ステップに従えば30分でレポートの骨格が完成します。
ステップ1:課題を読んだら即座に「結論メモ」を書く(5分)
レポート課題を読んだら、いきなり本文を書き始めるのではなく、まず結論だけをメモします。
やり方
- 「私は〜と考える」を1文だけ書く
- この段階では完璧でなくてOK
例 課題:「SNSは人間関係にどのような影響を与えるか論じなさい」 → メモ:「私はSNSが人間関係を多様化させると考える」
ステップ2:理由を2つだけ箇条書きする(10分)
結論に対して「なぜそう思うのか」を2つだけ挙げます。
やり方
- 理由1:理論的・一般的な根拠
- 理由2:具体的な事例・データ
例
- 理由1:地理的制約を超えた交流が可能になったから
- 理由2:コロナ禍でオンラインコミュニティが増加したから
ステップ3:その順番のままレポート本文にする(15分)
メモした順番を以下のように配置するだけで完成です。
- 結論メモ → 序論
- 理由1 → 本論①
- 理由2 → 本論②
- 結論メモを言い換え → 結論
この方法なら、迷わずに論理的な構成が完成します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 結論を最初に書くと、読む意味がなくなりませんか?
いいえ。結論を先に示すことで、読み手は「どう証明するのか」に注目して読めます。むしろ論点が明確になり、説得力が増します。
Q2. 序論と結論で同じことを書いてもいいですか?
基本的には同じ主張を述べますが、結論では「今後の課題」や「展望」を加えることで差別化します。完全に同じ文章の繰り返しは避けましょう。
Q3. 本論は2つではなく3つでもいいですか?
はい。文字数に余裕があれば、本論を3つに増やしても構いません。ただし、2つの方が論点が明確になりやすいです。
合わせて読みたい関連記事
大学生・社会人の必須文章! レポートの書き方と基本テクニック(ひな型・テンプレート付き)
【2025年最新】大学1年生必見!教授が高評価する実践的レポート作成完全マニュアル
【初心者向け】レポート・論文に使える情報源&資料の探し方まとめ
まとめ:結論ファーストが高評価レポートへの最短ルート
結論から書くレポート構成をマスターすれば、論理的で読みやすいレポートが誰でも書けるようになります。
この記事の重要ポイント
- 大学レポートは「結論→理由→事例→再主張」の順で書く
- 序論の1文目で「私は〜と考える」と結論を明示する
- 30分で骨格を作る3ステップ法を活用する
結論ファーストは、「読まれるレポート」を作る第一歩です。 今日からこのテンプレートを使って、教授に評価されるレポートを書いてみましょう!
この記事が役に立ったら、ブックマークして次回のレポート作成に活用してください!

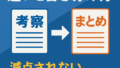
コメント