
「AIについて論じなさい」
2024年度入試で最も出題が増えたテーマが、このAI関連問題です。実は、**このテーマには明確な「合格パターン」**があります。
この記事では、毎年100本以上のAI関連小論文を添削する現役予備校講師が、合格答案の書き方をすべて公開します。
この記事を読めば: 「AIと人間」のテーマで確実に合格点が取れる方法がわかります。
なぜ今、AIテーマが急増しているのか?
📊 驚きの出題データ
2024年度入試分析:
- 国公立大学: 小論文実施校の42%がAI関連を出題
- 私立大学: 総合型選抜の63%がAI・デジタル社会を扱う
- 就職試験: 主要企業の78%がAIについて言及を求める
増加率:
- 2020年: 全出題の8%
- 2022年: 全出題の23%
- 2024年: 全出題の42%
つまり、AIテーマは避けて通れない最重要分野なのです。
出題パターン完全分類
パターン1: 賛否型(35%)
「AIの発展は人間社会にとって望ましいか、
あなたの意見を述べよ」
出題意図: 論理的に自分の立場を説明できるか
合格のコツ:
- 賛成/反対を明確に
- 理由を2〜3個
- 反対意見も考慮
パターン2: 問題解決型(30%)
「AIと人間が共存する社会を実現するために
必要なことは何か」
出題意図: 課題を分析し、解決策を提案できるか
合格のコツ:
- 現状の問題点を明確に
- 具体的な解決策を提示
- 実現可能性も考慮
パターン3: 比較型(20%)
「AIと人間の能力の違いについて論じ、
人間の役割を考察せよ」
出題意図: 多角的に分析できるか
合格のコツ:
- AIの強み・弱みを整理
- 人間の強み・弱みと対比
- 相補的な関係を提示
パターン4: 倫理型(15%)
「AIの発展に伴う倫理的課題について
あなたの考えを述べよ」
出題意図: 深い考察ができるか
合格のコツ:
- 具体的な倫理問題を挙げる
- 多様な視点から考察
- バランスの取れた結論
出題者が見ている5つのポイント
ポイント1: AIの現状理解(20点)
✅ 見られていること:
□ 生成AIなど最新動向を知っているか
□ 実社会での活用例を挙げられるか
□ 単なるSF的想像でないか
NG例:
AIがいずれ人間を支配するようになる
OK例:
ChatGPTなどの生成AIは、情報処理や文章作成を 支援するツールとして普及している
ポイント2: 論理的思考力(30点)
✅ 見られていること:
□ 主張と根拠が明確か
□ 具体例が適切か
□ 因果関係が整理されているか
NG例:
AIは便利だ。だから使うべきだ。
OK例:
AIは大量データの処理に優れる。 したがって、医療診断の精度向上に寄与できる。 実際に、がん検診の精度が30%向上した事例がある。
ポイント3: バランス感覚(25点)
✅ 見られていること:
□ メリット・デメリット両方を考慮
□ 極端な主張でないか
□ 反対意見も理解しているか
NG例:
AIは完璧だ。すべてAIに任せるべきだ。
OK例:
AIには高速処理という強みがある一方で、 創造性や倫理判断には限界がある。 したがって、人間との協働が重要だ。
ポイント4: 独自の視点(15点)
✅ 見られていること:
□ 自分なりの考察があるか
□ 体験や観察が入っているか
□ 単なる一般論でないか
NG例:
多くの人が言っているように、AIは便利だ。
OK例:
私が職業体験で訪れた病院では、AIが診断を支援し、 医師が患者との対話に時間を使えるようになっていた。 この経験から、AI活用の本質は「人間の時間を創出すること」 だと気づいた。
ポイント5: 未来志向(10点)
✅ 見られていること:
□ 建設的な提案があるか
□ 悲観論だけでないか
□ 自分に何ができるか考えているか
NG例:
AIの未来は不透明だ。
OK例:
私たちはAIリテラシーを高め、 この技術を人類の福祉向上に活かす責任がある。
【完全版】合格答案の書き方
序論の書き方:3つの型
型1: 現状提示型(最も安全)
【テンプレート】
近年、【AIの現状】が進んでいる。
一方で、【懸念・問題】も指摘されている。
私は、【自分の立場】と考える。
【実例】
近年、生成AIの普及が急速に進み、ChatGPTなどのツールが
日常的に使われるようになっている。一方で、AIが人間の仕事を
奪うのではないかという懸念も広がっている。私は、AIと人間が
それぞれの強みを活かして協働することで、より豊かな社会が
実現できると考える。
字数: 150字程度
時間: 5分以内
型2: 問いかけ型(印象的)
【テンプレート】
【問いかけ】だろうか。
【現状説明】
私は、【自分の立場】と考える。
【実例】
AIは本当に人間の敵なのだろうか。確かに、一部の職種では
自動化が進み、雇用への影響が懸念されている。しかし、
AIの本質は人間を「置き換える」ことではなく、人間の能力を
「拡張する」ことにある。私は、AIを適切に活用することで、
人間はより創造的な活動に集中できると考える。
効果: 読み手の関心を引く
難易度: やや高い
型3: 対比型(論理的)
【テンプレート】
【過去の状況】だった。しかし今、【現在の状況】になっている。
私は、【自分の立場】と考える。
【実例】
かつて、コンピュータの登場時にも「雇用が失われる」と
懸念された。しかし実際には、新たな職種が生まれ、
社会全体の生産性が向上した。今、AIの普及に際しても
同様の議論がある。私は、歴史の教訓を踏まえ、AIとの
共存が新たな価値を生み出すと考える。
効果: 説得力が高い
難易度: 高い
本論の書き方:合格パターン
パターンA: AIの強み×人間の強み型
【構成】
理由1: AIの強み(客観的分析)
理由2: 人間の強み(主観的視点)
結論: 協働の必要性
【実例】
第一に、AIは大量のデータを高速で処理できる。
例えば、医療分野では、AIが膨大な医療データを分析し、
がんの早期発見率を30%向上させている。人間の医師が
一人で処理できる情報量には限界があるが、AIは24時間
休まず分析を続けられる。このように、AIは「情報処理能力」
という点で圧倒的な強みを持つ。
第二に、人間には創造性と倫理的判断力がある。
AIは過去のデータから学習するため、前例のない問題には
対応できない。しかし、人間は状況に応じて柔軟に判断し、
新しい解決策を生み出せる。例えば、芸術作品の創造や、
患者の心のケアといった分野では、人間の感性と共感力が
不可欠だ。実際、ある病院では、AIが診断を支援する一方で、
医師が患者との対話に時間を割けるようになり、
患者満足度が向上したという報告がある。
このように、AIと人間はそれぞれ異なる強みを持つ。
したがって、両者が協働することで、より高い価値を
生み出せるのだ。
字数: 約500字
評価: 高得点(論理的で具体的)
パターンB: 課題→解決策型
【構成】
課題1: 雇用への影響
解決策1: 教育・リスキリング
課題2: 倫理的問題
解決策2: ルール整備
【実例】
第一に、AIの普及により雇用が失われる可能性がある。
総務省の調査によれば、定型業務を中心に10年以内に
国内雇用の約20%が自動化される見込みだ。これは深刻な
社会問題となりうる。しかし、教育制度を改革し、
AIを活用できる人材を育成することで、新たな雇用を
創出できる。実際、北欧諸国では、リスキリング政策により、
失業率を抑えながらAI導入を進めている。
第二に、AIの判断に倫理的問題がある。例えば、
自動運転車が事故を起こした際の責任の所在や、
AI採用システムによる差別の可能性などが指摘されている。
この課題に対しては、明確なルールと監視体制の整備が必要だ。
EUでは「AI規制法」が制定され、高リスクなAI利用には
厳格な基準が設けられている。日本でも同様の枠組みを
整備すべきだろう。
字数: 約400字
評価: 高得点(実践的で説得力がある)
パターンC: 歴史的視点型
【構成】
過去の技術革新の例
現在のAI状況との比較
未来への提言
【実例】
歴史を振り返ると、技術革新は常に雇用への不安を
伴ってきた。産業革命時、機械の導入により多くの職人が
職を失うと懸念された。しかし実際には、新たな産業が
生まれ、社会全体の豊かさが向上した。同様に、
コンピュータの普及時も「オフィス労働者が不要になる」
と言われたが、ITエンジニアなど新しい職種が生まれた。
現在のAI革命も、この歴史的パターンと同じ道を
たどるだろう。確かに一部の職種は自動化される。
しかし、AIを開発・運用・管理する人材や、
AIでは代替できない創造的な仕事への需要が高まる。
重要なのは、変化を恐れるのではなく、変化に適応する
準備をすることだ。
字数: 約350字
評価: 高得点(深い考察がある)
結論の書き方:3つの締め方
締め方1: 再確認→提案型
以上の理由から、AIは人間の敵ではなく、
協働すべきパートナーである。それぞれの強みを活かし、
弱みを補い合うことで、より豊かな社会が実現できる。
私たちは、AIを恐れるのではなく、正しく理解し、
賢く活用する力を身につけるべきだ。
字数: 100字程度
効果: 安定感がある
締め方2: 問いかけ→決意型
AIとの共存は、単なる技術の問題ではない。
これは、「人間とは何か」「人間らしさとは何か」を
問い直す機会でもある。AIの時代だからこそ、
私たちは人間の本質的な価値を再発見し、
それを大切にする社会を築いていかなければならない。
字数: 120字程度
効果: 印象に残る
締め方3: 未来展望型
AIと人間の共存社会は、必ず実現できる。
そのためには、技術の発展と並行して、教育改革や
ルール整備を進める必要がある。私自身も、
AIリテラシーを高め、この技術を人類の幸福に
活かせる人材になりたい。
字数: 100字程度
効果: 前向きで好印象
【実践例】800字完成答案
問題: 「AIと人間の共存について、あなたの考えを800字以内で述べよ」
完成答案(800字)
近年、生成AIの普及が急速に進み、ChatGPTなどのツールが
日常的に使われるようになっている。一方で、AIが人間の仕事を
奪うのではないかという懸念も広がっている。私は、AIと人間が
それぞれの強みを活かして協働することで、より豊かな社会が
実現できると考える。
第一に、AIは大量のデータを高速で処理できる強みを持つ。
例えば、医療分野では、AIが膨大な医療データを分析し、
がんの早期発見率を30%向上させている。人間の医師が
一人で処理できる情報量には限界があるが、AIは24時間
休まず分析を続けられる。また、製造業では、AIが不良品を
瞬時に検知し、品質管理の精度を大幅に向上させている。
このように、「情報処理能力」という点で、AIは圧倒的な
強みを持つ。
第二に、人間には創造性と倫理的判断力がある。AIは
過去のデータから学習するため、前例のない問題には
対応できない。しかし、人間は状況に応じて柔軟に判断し、
新しい解決策を生み出せる。例えば、芸術作品の創造や、
患者の心のケアといった分野では、人間の感性と共感力が
不可欠だ。ある病院では、AIが診断を支援する一方で、
医師が患者との対話に時間を割けるようになり、
患者満足度が向上したという。これは、AIが単純作業を担い、
人間が人間らしい仕事に集中できる好例だ。
もちろん、AIとの共存には課題もある。雇用への影響や、
倫理的な問題など、解決すべき課題は多い。しかし、
歴史を振り返れば、技術革新は常に新たな機会を生み出してきた。
重要なのは、変化を恐れるのではなく、変化に適応する
準備をすることだ。
以上の理由から、AIは人間の敵ではなく、協働すべき
パートナーである。AIが得意な情報処理を任せることで、
人間はより創造的で人間らしい活動に集中できる。
私たちは、AIを恐れるのではなく、正しく理解し、
賢く活用する力を身につけるべきだ。そうすることで、
技術と人間性が調和した、真に豊かな社会を実現できると
私は確信している。
字数: 798字
この答案の評価ポイント
✅ 優れている点
1. 三段構成が明確
□ 序論: 現状→問題→立場(148字)
□ 本論: 理由2つ+具体例(550字)
□ 結論: 要約→提案(100字)
2. 具体例が豊富
□ 医療分野のがん検診
□ 製造業の品質管理
□ 病院での患者対応
3. バランスが良い
□ AIの強みを認める
□ 人間の強みも強調
□ 課題も言及
4. 論理的
□ 「第一に」「第二に」で整理
□ 因果関係が明確
□ 結論が自然に導かれる
予想得点: 85〜90点/100点
頻出キーワード30選
必ず押さえるべき基本用語
AI関連
1. 生成AI(ChatGPT等)
2. 機械学習
3. ディープラーニング
4. 自動化
5. ビッグデータ
6. アルゴリズム
7. 自然言語処理
8. 画像認識
9. 予測分析
10. ロボティクス
社会・雇用関連
11. 労働市場の変化
12. リスキリング(再教育)
13. 生産性向上
14. 働き方改革
15. ギグエコノミー
16. テレワーク
17. デジタルトランスフォーメーション(DX)
18. スキルギャップ
19. 創造的破壊
20. イノベーション
倫理・課題関連
21. AIバイアス(偏見)
22. プライバシー保護
23. 説明可能性(XAI)
24. アルゴリズム的差別
25. 責任の所在
26. 倫理ガイドライン
27. データガバナンス
28. 透明性
29. 人間中心設計
30. デジタルデバイド(格差)
使える具体例10選
1. 医療分野
✅ AIによるがん検診の精度向上
・早期発見率30%向上
・見落とし率50%減少
・24時間体制での診断支援
使い方:
「医療分野では、AIが画像診断を支援し、
がんの早期発見率を30%向上させている」
2. 製造業
✅ 品質管理の自動化
・不良品検知率99.9%
・検査時間70%短縮
・人為的ミスの削減
使い方:
「製造業では、AIが不良品を瞬時に検知し、
品質管理の精度を大幅に向上させている」
3. カスタマーサポート
✅ チャットボットの活用
・24時間対応可能
・単純な質問への即座回答
・人間オペレーターの負担軽減
使い方:
「カスタマーサポートでは、AIチャットボットが
単純な質問に即座に回答し、人間のオペレーターは
複雑な問題に集中できるようになっている」
4. 教育分野
✅ 個別最適化学習
・一人ひとりの理解度に合わせた教材
・苦手分野の自動検出
・教師の業務負担軽減
使い方:
「教育現場では、AIが生徒一人ひとりの
理解度を分析し、最適な学習プランを提供している」
5. 金融分野
✅ 不正検知システム
・クレジットカード詐欺の検出
・異常取引の即座通知
・金融犯罪の予防
使い方:
「金融業界では、AIが膨大な取引データから
不正なパターンを検出し、詐欺被害を防いでいる」
6. 農業分野
✅ スマート農業
・ドローンによる生育管理
・AIによる病害虫予測
・収穫量の最適化
使い方:
「農業では、AIが気象データと生育状況を分析し、
最適な栽培計画を提案することで、収穫量が向上している」
7. 交通分野
✅ 自動運転技術
・事故率の低減
・渋滞緩和
・高齢者の移動支援
使い方:
「自動運転技術は、人為的ミスによる事故を減らし、
特に高齢者の移動手段として期待されている」
8. 翻訳分野
✅ 機械翻訳の精度向上
・リアルタイム翻訳
・多言語コミュニケーション
・言語の壁の解消
使い方:
「機械翻訳の精度が向上し、異なる言語を話す人々の
コミュニケーションが容易になっている」
9. 創作分野
✅ AI生成コンテンツ
・画像生成(Midjourney等)
・文章作成(ChatGPT等)
・音楽作曲
使い方:
「AIは画像や文章を生成できるが、そこに『意味』や
『メッセージ』を込めるのは人間の役割だ」
10. 災害対応
✅ 災害予測・対応
・地震予測の精度向上
・避難経路の最適化
・被災状況の迅速把握
使い方:
「災害時、AIは被災状況を迅速に分析し、
最適な避難経路や支援物資の配分を提案している」
よくある失敗パターン10選
❌ 失敗1: SF的な話になる
悪い例:
「将来、AIが人間を支配し、人類は滅亡する。
ターミネーターのような世界になるだろう。」
問題点:
・現実性がない
・論理的でない
・採点者に不真面目な印象
✅ 改善策:
現在の技術レベルと社会状況に基づいて論じる
❌ 失敗2: 感情論だけ
悪い例:
「AIは怖い。人間のほうが優れている。
AIなんて必要ない。」
問題点:
・主観的すぎる
・根拠がない
・バランスを欠く
✅ 改善策:
客観的な事実と論理的な分析を示す
❌ 失敗3: メリットだけ/デメリットだけ
悪い例:
「AIは完璧だ。すべての問題を解決する。
人間はAIに任せればいい。」
問題点:
・一面的
・課題を無視
・現実的でない
✅ 改善策:
メリット・デメリット両方を冷静に分析
❌ 失敗4: 具体例がない
悪い例:
「AIは便利だ。だから使うべきだ。
人間と協力すれば良い。」
問題点:
・抽象的
・説得力ゼロ
・薄い内容
✅ 改善策:
必ず具体例を2〜3個入れる
❌ 失敗5: 知識の羅列
悪い例:
「AIには機械学習、ディープラーニング、
自然言語処理などがある。ビッグデータを
活用してアルゴリズムで…」
問題点:
・用語の説明だけ
・自分の意見がない
・論じていない
✅ 改善策:
知識は最小限に、考察を中心に
❌ 失敗6: 結論が曖昧
悪い例:
「AIについては賛否両論ある。
今後の動向を見守りたい。」
問題点:
・自分の立場がない
・逃げている
・評価されない
✅ 改善策:
明確に自分の意見を述べる
❌ 失敗7: 話が脱線
悪い例:
序論: AIについて
本論: スマホの便利さ、ゲームの話
結論: 技術は大切
問題点:
・テーマからずれる
・論点が定まらない
✅ 改善策:
構成メモで論点を整理してから書く
❌ 失敗8: 字数不足
悪い例:
800字指定で500字しか書けなかった
問題点:
・内容が薄い
・大幅減点
✅ 改善策:
具体例を詳しく書く
各理由を十分に説明する
❌ 失敗9: 同じことの繰り返し
悪い例:
「AIは便利だ。とても便利だ。
すごく便利だと思う。」
問題点:
・内容が薄い
・語彙力不足
✅ 改善策:
言い換え表現を使う
異なる視点から論じる
❌ 失敗10: 時間切れで結論なし
悪い例:
序論と本論は書けたが、
結論を書く時間がなかった
問題点:
・構成不完全
・大幅減点
✅ 改善策:
時間配分を守る
結論は必ず確保(最低100字)
まとめ:AIテーマで合格する5つのポイント
ポイント1: 現実に基づく
□ 最新の動向を知る(ChatGPT等)
□ 実社会の活用例を挙げる
□ SFではなく現実を論じる
ポイント2: バランスを取る
□ メリット・デメリット両方
□ AIの強み・人間の強み
□ 賛成でも反対意見に言及
ポイント3: 具体的に書く
□ 抽象論を避ける
□ 具体例を2〜3個
□ 数字やデータを使う
ポイント4: 自分の意見を明確に
□ 序論で立場を表明
□ 本論で理由を説明
□ 結論で再確認
ポイント5: 人間の価値を再定義
□ 「人間らしさ」とは何か
□ AIにできないこと
□ 未来への展望
【無料プレゼント】AIテーマ攻略ワークブック
この記事を最後まで読んでくださったあなたに、特別な教材をプレゼントします。
「AIと人間の共存テーマ攻略ワークブック」(PDF・無料)
📚 ワークブックの内容
✅ 頻出問題10題と模範解答 ✅ 使える具体例50選 ✅ キーワード辞典100語 ✅ 添削前後の比較例10本 ✅ 時事問題アップデート ✅ 実践トレーニングシート
このワークブックがあれば、どんなAI関連問題が出ても対応できます。
【関連記事おすすめ】
- 【完全版】小論文の書き方|序論・本論・結論の構成で説得力を10倍上げる方法
- 小論文は練習しなくていい!「4つの型」で書く小論文の書き方
- 論文が下手だと感じたら読む記事|ロジカルな文章に変える3ステップ
【SNSでシェアしよう】 受験生の友達にもシェアしてあげてください!
※この記事の内容は2025年10月時点の情報に基づいています。AI技術は日々進化しているため、最新情報も確認してください。
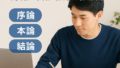
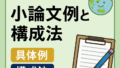
コメント