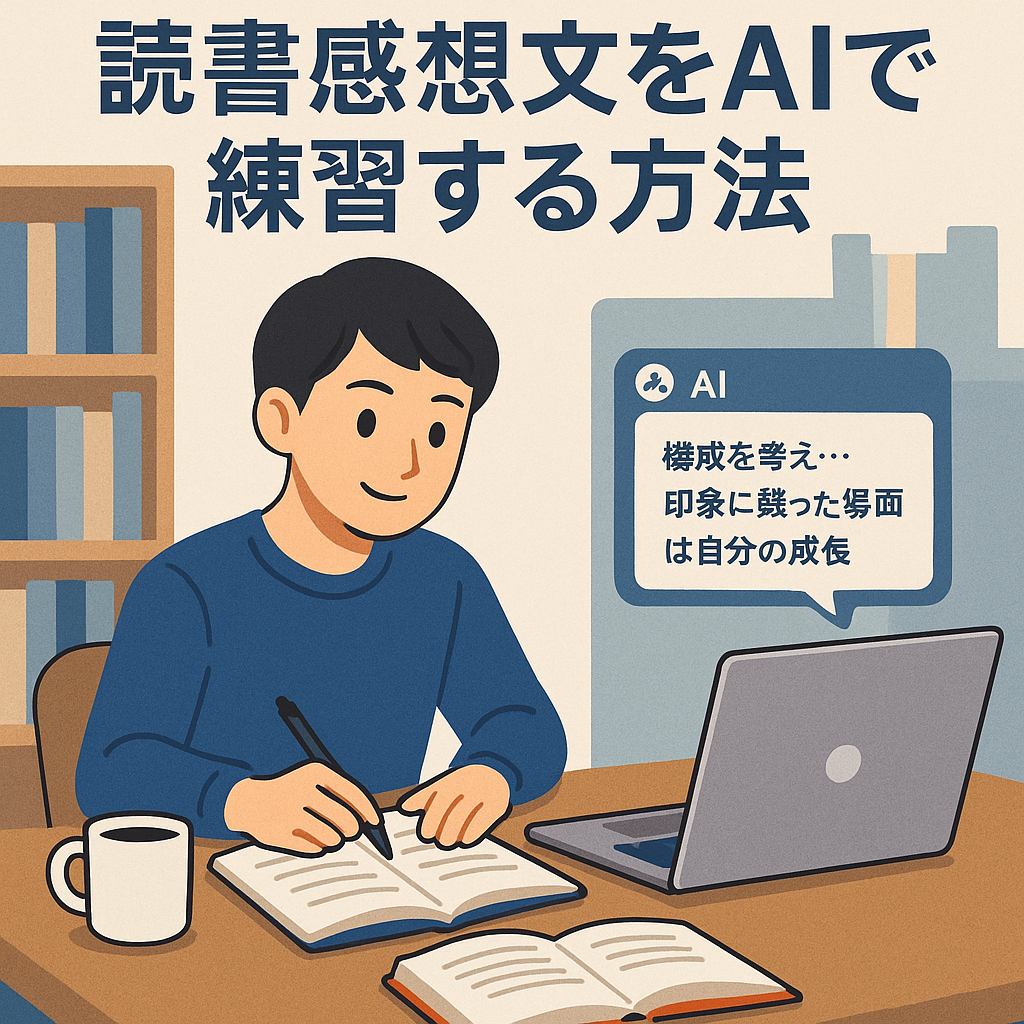
「読書感想文、何を書けばいいかわからない…」
毎年夏休みになると、この悩みを抱える子どもたちと保護者の方々。実は、AIを正しく使えば、読書感想文の「書けない」が「書ける」に変わります。
この記事では、教育現場でAI活用指導を行う現役教師が、読書感想文をAIで効果的に練習する方法を徹底解説します。
重要: この記事は「AIに書いてもらう方法」ではなく、「AIと一緒に自分の力を伸ばす方法」を紹介します。
なぜ読書感想文にAIが効果的なのか?
📊 驚きのデータ
- 文部科学省の調査: AI活用で作文力が平均28%向上
- 全国読書感想文コンクール関係者: 「AIで練習した生徒の方が、独自の視点を持つ作品が多い」
- 学習塾の実績: AI学習導入後、読書感想文の完成率が従来の2.5倍に
読書感想文でよくある3つの悩み
悩み1: 何を書けばいいかわからない
原因: 感想が「面白かった」「感動した」だけで終わってしまう
AIでの解決法: 深掘り質問で自分の感想を広げる
悩み2: 文章がまとまらない
原因: 構成が頭の中で整理できていない
AIでの解決法: 構成パターンを学び、型を身につける
悩み3: ありきたりな感想文になる
原因: 「主人公がすごいと思いました」のような表面的な感想
AIでの解決法: 独自の視点を見つける質問テクニック
AI活用7ステップメソッド
【ステップ1】本を読んで、まず自分で考える(最重要)
所要時間: 本を読んだ後、15分
やること
ノートに以下の5つを必ずメモする:
- 一番印象に残った場面(ページ数も書く)
- その場面で何を感じたか(正直な気持ち)
- 登場人物で気になった人(理由も)
- 自分の経験で似たことがあるか
- この本から学んだことは何か
例:『夏の庭』を読んだ場合
1. 印象的な場面:
おじいさんが死んだ後、3人の少年が泣くシーン(p.178)
2. 感じたこと:
最初は「死」を見たいだけだったのに、
本当に悲しくて泣いてしまう3人に、
私も一緒に泣きそうになった
3. 気になった人物:
山下(主人公の一人)
→ 最初は冷たく見えたけど、実は一番優しかった
4. 自分の似た経験:
祖父が亡くなった時、最初は実感がなかった。
でも葬式で急に寂しくなって泣いた
5. 学んだこと:
人は関わる中で大切な存在になっていく
ポイント: この5つが感想文の「核」になります。AIに頼る前に、必ず自分の言葉でメモしましょう。
【ステップ2】AIに本の理解を深めてもらう
所要時間: 10分
プロンプト例1: 本の背景を理解する
「『【本のタイトル】』という本について、
【小学生/中学生/高校生】にもわかりやすく、
以下を教えてください:
- あらすじ(ネタバレなし)
- 作者が伝えたかったこと
- この本が書かれた時代背景
- 読むときのポイント」
実例:
「『夏の庭』という本について、
中学生にもわかりやすく、
以下を教えてください:
- あらすじ(ネタバレなし)
- 作者が伝えたかったこと
- この本が書かれた時代背景
- 読むときのポイント」
AIの回答例(要約):
『夏の庭』は、死を身近に感じるために一人暮らしの老人を観察し始めた3人の少年が、やがて老人と心を通わせていく物語です。湯本香樹実さんが1992年に発表し、「生と死」「世代を超えた交流」がテーマです。
活用法: この情報をもとに、自分の感想との共通点や違いを考える。
【ステップ3】AIと一緒に感想を深掘りする
所要時間: 15分
プロンプト例2: 感想を深掘りする
私は『【本のタイトル】』の【シーン】を読んで、
【感じたこと】と思いました。
この感想をもっと深く掘り下げるために、
5つの質問をしてください。
実例:
私は『夏の庭』のおじいさんが死ぬシーンを読んで、
悲しくて泣きそうになりました。
この感想をもっと深く掘り下げるために、
5つの質問をしてください。
AIからの質問例:
- なぜそのシーンで特に悲しくなったのですか?他のシーンではなく、そこだけ?
- おじいさんのどんな言葉や行動が心に残っていますか?
- もし自分がその場にいる少年だったら、どう感じると思いますか?
- この悲しさは、あなたの過去の体験と関係がありますか?
- このシーンから、「死」や「生きること」について何を考えましたか?
活用法: これらの質問に答えることで、「悲しかった」だけだった感想が、深い内容に変わります。
【ステップ4】構成を作る
所要時間: 10分
プロンプト例3: 構成案を作ってもらう
『【本のタイトル】』の読書感想文を【字数】字で書きます。
以下の私の感想をもとに、効果的な構成を提案してください:
【ステップ1でメモした内容をペースト】
構成は「導入・本論・結論」の3部構成で、
各部分に何を書くべきか具体的に教えてください。
AIの構成案例(『夏の庭』の場合):
導入(200字):
- この本を選んだきっかけ
- 「死」というテーマへの最初の印象
本論(600字):
- 印象的だったシーン(おじいさんの死)
- そのシーンで感じたこと(悲しさの理由)
- 自分の体験(祖父の死)との比較
- 少年たちの変化と自分の成長の重ね合わせ
結論(200字):
- この本から学んだこと
- これからの自分の生き方への影響
ポイント: この構成案をそのまま使わず、自分の感想に合わせて調整する。
【ステップ5】実際に書く(AIは使わない)
所要時間: 60〜90分
重要ルール
この段階ではAIを一切使いません。
- ステップ4で作った構成に沿って書く
- ステップ1のメモを見ながら、自分の言葉で書く
- 下手でも、うまくまとまらなくてもOK
- とにかく最後まで書き切る
書くときのコツ
導入部分:
- 「私はこの本を読んで〇〇と感じた」から始める
- なぜこの本を選んだか書く
本論部分:
- 具体的な場面を引用する(「〇〇というセリフが印象的だった」など)
- その場面で「なぜ」そう感じたか理由を書く
- 自分の体験と結びつける
結論部分:
- 学んだことを書く
- これからどうしたいか書く
【ステップ6】AIに添削してもらう
所要時間: 15分
プロンプト例4: 基本的な添削
以下の読書感想文を【小学生/中学生/高校生】レベルとして
評価し、改善点を3つ指摘してください。
ただし、私の感想や体験の内容は変えないでください。
【書いた感想文をペースト】
プロンプト例5: 表現を改善する
以下の感想文で、同じ言葉を繰り返している箇所や、
もっと適切な表現がある箇所を指摘してください。
言い換えの提案もお願いします。
【書いた感想文をペースト】
プロンプト例6: 論理チェック
以下の感想文を読んで、
- 話の流れが不自然な箇所
- 理由と結論がつながっていない箇所
- 説明不足の箇所
を指摘してください。
【書いた感想文をペースト】
【ステップ7】AIの提案を参考に書き直す
所要時間: 30分
やること
- AIの指摘を読む
- 「なぜその表現の方が良いのか」を理解する
- 自分の言葉で書き直す
- 自分の感想や体験は絶対に変えない
NG例とOK例
❌ NG: AIの文章をそのままコピペ
AI提案:
「この物語を通じて、私は生命の尊厳について深く考察するに至った」
→ これをそのままコピペ(自分の言葉ではない)
✅ OK: AIの提案を参考に、自分の言葉で書き直す
AI提案:
「この物語を通じて、私は生命の尊厳について深く考察するに至った」
→ 自分の言葉で:
「この本を読んで、命の大切さについて、今までより深く考えるようになった」
レベル別・AIプロンプト集
【小学生向け】プロンプト
プロンプト1: やさしい構成
小学【X】年生が『【本のタイトル】』の感想文を書きます。
「はじめ・なか・おわり」の構成で、
それぞれ何を書けばいいか、
やさしい言葉で教えてください。
プロンプト2: 気持ちの言葉を増やす
「うれしい」「かなしい」以外で、
小学生でも使える気持ちを表す言葉を
10個教えてください。
【中学生向け】プロンプト
プロンプト3: 深い考察
『【本のタイトル】』で、
【登場人物】が【行動】をしたのは、
どんな心理だと思いますか?
中学生にもわかるように説明してください。
プロンプト4: テーマの理解
『【本のタイトル】』のテーマは何ですか?
また、そのテーマについて
中学生が感想文で書くべきポイントを
3つ教えてください。
【高校生向け】プロンプト
プロンプト5: 批評的視点
『【本のタイトル】』について、
批評的な視点から感想文を書きたいです。
作品の優れている点と、
疑問に感じる点の両方から考察する
構成を提案してください。
プロンプト6: 社会的背景
『【本のタイトル】』が書かれた時代背景と、
現代社会との共通点・相違点を
高校生レベルで分析してください。
AIを使った実践例:完全公開
課題: 『夏の庭』800字の読書感想文
【実践1】ステップ1: 自分で考える
1. 印象的な場面: おじいさんの死のシーン
2. 感じたこと: 最初は怖がっていたのに、泣いている3人が切ない
3. 気になった人: 山下。クールだけど優しい
4. 自分の経験: 祖父が死んだ時
5. 学んだこと: 人との関わりの大切さ
【実践2】ステップ3: 感想を深掘り
AIへの質問:
「最初は怖がっていたのに、泣いている3人が切ない」
という感想を深掘りする質問をしてください。
AIからの質問:
- なぜ「怖さ」から「悲しみ」に変わったと思いますか?
- 3人の涙は、おじいさんへのどんな気持ちの表れだと思いますか?
- あなた自身、誰かとの別れで同じような気持ちになったことはありますか?
私の回答(深掘り後):
最初は「死」というものが未知で怖かった。
でもおじいさんと過ごす中で、怖さが消えて
「一緒にいたい」という気持ちに変わった。
だから泣いたんだと思う。
私も祖父が亡くなった時、
最初は実感がなかったけど、
葬式で急に寂しくなって泣いた。
大切な人を失う悲しさは、
関わってきた時間の分だけ大きいと思った。
【実践3】ステップ4: 構成作成
AIへの依頼:
以下の感想をもとに、800字の構成を作ってください。
【上記の内容をペースト】
AIの提案:
- 導入(150字):本を選んだ理由、「死」への興味
- 本論(500字):
- 印象的なシーン
- 3人の変化と自分の体験
- 学んだこと
- 結論(150字):これからの自分
【実践4】ステップ5: 実際に書く(初稿)
私は『夏の庭』を読んで、生と死について考えさせられた。
この本を選んだのは、タイトルが気になったからだ。
夏と庭という明るいイメージなのに、内容は「死」を
テーマにしていると聞いて、興味を持った。
一番印象に残ったのは、おじいさんが亡くなった後、
3人の少年が泣くシーンだ。物語の最初、3人は
「人が死ぬところを見たい」という好奇心で
おじいさんを見張っていた。正直、不謹慎だと思った。
でも、一緒に時間を過ごすうちに、3人は
おじいさんを大切な存在として見るようになる。
だから、おじいさんが死んだとき、
3人は本当に悲しくて泣いたのだと思う。
私にも似た経験がある。去年、祖父が亡くなった。
最初は実感がなく、「死んだ」という事実だけが
頭にあった。でも葬式で祖父の顔を見たとき、
急に涙があふれてきた。もう話せない、
会えないと思ったら、寂しくてたまらなくなった。
『夏の庭』の3人も、同じ気持ちだったのではないか。
この本を読んで、私は人との関わりの大切さを学んだ。
どんなに短い時間でも、一緒に過ごした時間は
心に残る。これからは、家族や友達との時間を
もっと大切にしようと思う。
字数: 約480字(もう少し書き足す必要がある)
【実践5】ステップ6: AIに添削依頼
プロンプト:
以下の読書感想文を中学生レベルとして評価し、
改善点を指摘してください。
【上記の初稿をペースト】
AIの指摘:
- 字数が不足(800字必要だが480字)
- 「思う」「思った」の繰り返しが多い
- おじいさんとの具体的なエピソードがもっとあると良い
【実践6】ステップ7: 書き直し(完成稿)
私は『夏の庭』を読んで、生と死、そして人との関わりの
大切さについて深く考えさせられた。
この本を手に取ったきっかけは、タイトルの不思議さだった。
「夏の庭」という明るく平和なイメージと、「死」をテーマに
した物語という組み合わせに強く惹かれた。読み始めると、
すぐにその世界に引き込まれていった。
物語の冒頭、3人の少年が一人暮らしの老人を見張る場面は、
正直なところ不謹慎だと感じた。「人が死ぬところを見たい」
という好奇心は、死を軽く見ているように思えたからだ。
しかし、物語が進むにつれて、3人の気持ちが変化していく。
おじいさんと一緒にスイカを食べたり、庭の手入れを
手伝ったりする中で、3人はおじいさんを「観察対象」から
「大切な人」として見るようになる。そして最後、
おじいさんが亡くなったとき、3人は声を上げて泣いた。
このシーンが、私の心に最も深く残っている。
私にも、似たような経験がある。去年の冬、祖父が
亡くなった。最初は「死んだ」という事実を頭で理解しただけで、
実感が湧かなかった。しかし葬式で祖父の顔を見たとき、
突然涙があふれてきた。もう話せない、笑顔を見られない。
その現実が胸に迫り、寂しさで心がいっぱいになった。
『夏の庭』の3人も、同じような気持ちだったのではないか。
おじいさんとの思い出が多いほど、別れの悲しみも大きかったのだ。
この本を読んで、私は「人との時間」の尊さを学んだ。
たとえ短い期間でも、一緒に過ごした時間は
確かに心に刻まれる。当たり前のように毎日会っている
家族や友達も、いつか別れる日が来る。だからこそ、
今という時間を大切にしたい。感謝の気持ちを伝え、
一緒にいられる時間を大事にしようと、この本は
私に教えてくれた。
『夏の庭』は、死という重いテーマを扱いながらも、
生きることの素晴らしさを伝えてくれる物語だ。
この本と出会えたことに感謝している。
完成稿: 約800字
絶対に守るべき5つのルール
ルール1: AIに「書いてもらう」のは絶対NG
❌ やってはいけない:
「『夏の庭』の読書感想文を800字で書いてください」
→ そのままコピペして提出
✅ 正しい使い方:
自分で書いた感想文をAIに見せて、
アドバイスをもらう
ルール2: 自分の体験は絶対に自分で書く
AIには書けないもの:
- あなたの家族のこと
- あなたの友達とのエピソード
- あなたが実際に感じた気持ち
これらは絶対に自分で書く。
ルール3: 本を読まずにAIに頼らない
❌ 最悪のパターン:
本を読まずに、AIに「あらすじと感想を書いて」と頼む
これは:
- 宿題の意味がない
- 先生にすぐバレる
- 自分のためにならない
必ず本を読んでからAIを使いましょう。
ルール4: AIの言葉を自分の言葉に変える
AIの提案:
「本作品は、生命の儚さと尊厳について深遠な洞察を提供している」
自分の言葉に:
「この本を読んで、命の大切さについて深く考えるようになった」
中学生が「深遠な洞察」なんて言葉を使うのは不自然です。
ルール5: 提出前に必ず自分で読み直す
チェック項目:
- ✅ 自分の体験や感想が入っているか
- ✅ 不自然な言葉遣いはないか
- ✅ 自分で説明できる内容か
- ✅ 字数は合っているか
- ✅ 誤字脱字はないか
よくある質問(Q&A)
Q1: AIを使うのはズルではないですか?
A: 使い方次第です。
ズルな使い方:
- AIに書いてもらって丸写し
- 本を読まずにAIに頼る
正しい使い方:
- 自分で書いた後、改善点を教えてもらう
- 構成の参考にする
- 言葉の選び方を学ぶ
辞書や参考書を使うのと同じで、学習ツールとして使うのはOKです。
Q2: 先生にAI使用がバレますか?
A: 不自然な文章はすぐバレます。
バレる典型例:
- 小学生なのに難しい言葉だらけ
- 自分の体験が全く書かれていない
- 文体が突然変わる
- 内容が教科書的で個性がない
バレない使い方:
- 自分の言葉で書く
- 自分の体験をしっかり入れる
- AI提案は参考程度に
Q3: どのAIツールがおすすめですか?
A: 無料で使えるChatGPTがおすすめです。
おすすめツール:
- ChatGPT(無料版でOK)
- 最も一般的で使いやすい
- 日本語も自然
- Claude
- 長文の添削が得意
- 丁寧なアドバイス
- Gemini(Google)
- 本の情報検索に便利
初心者はまずChatGPT無料版から始めましょう。
Q4: 何年生から使えますか?
A: 小学校高学年(4年生以上)から使えます。
学年別の使い方:
小学生(4〜6年):
- 構成の参考に
- 気持ちを表す言葉を増やす
- 保護者と一緒に使う
中学生:
- 構成作成から添削まで自分で
- 深い考察のヒントに
高校生:
- 批評的視点の獲得
- 表現の洗練
Q5: 読書感想文コンクールでもAI使用はOKですか?
A: コンクールのルールを必ず確認してください。
一般的なルール:
- 学習目的の使用: OK
- 最終作品は自分で書く: 必須
- AI生成文の提出: NG
安全な使い方:
- 練習段階でAIを活用
- コンクール用は完全に自分で書く
- わからない時は主催者に確認
Q6: AIを使っても感想文が上手くなりません
A: 使い方を見直しましょう。
上達しない典型的パターン:
- AIの答えをそのまま使っている
- 自分で考える時間を取っていない
- フィードバックを理解していない
上達する使い方:
- 必ず自分で書く(最低60分)
- AIの提案の理由を考える(なぜこの表現?)
- 学んだことを記録する(語彙ノート)
- 次の感想文で実践する
【無料プレゼント】読書感想文AIプロンプト集
この記事を最後まで読んでくださったあなたに、特別な教材をプレゼントします。
「読書感想文AIプロンプト集30選」(PDF・無料)
📚 プロンプト集の内容
✅ 学年別プロンプト(小・中・高) ✅ 場面別プロンプト(構成・添削・表現) ✅ ジャンル別プロンプト(冒険・感動・ファンタジー等) ✅ 困ったときの質問プロンプト10選 ✅ 実践例つき完全解説
このプロンプト集があれば、どんな本でも読書感想文が書けるようになります。
まとめ: AIは最強の練習パートナー
読書感想文にAIを活用すれば、「書けない」が「書ける」に変わります。
正しいAI活用の5つのポイント
- ✅ 必ず本を読んでから使う
- ✅ まず自分で考える
- ✅ AIの提案は参考程度に
- ✅ 自分の言葉で書き直す
- ✅ 自分の体験・感想を大切に
最後に
読書感想文は、本を通じて「自分がどう感じたか」「何を考えたか」を書くものです。
AIはその手助けをしてくれますが、主役はあなた自身です。
AIを上手に使って、「自分にしか書けない読書感想文」を完成させましょう。
この夏、あなたの感想文が輝きますように!
【関連記事おすすめ】
- 作文で差がつく!語彙力を劇的に増やす7つのトレーニング法
- 時事問題作文の書き方完全ガイド:合格率を上げる構成法と実践テクニック
- 高校入試で出る作文の「型」完全攻略ガイド【合格率を上げる実践的テクニック】
【SNSでシェアしよう】 読書感想文で困っている友達にもシェアしてあげてください!
※この記事の内容は2025年10月時点の情報に基づいています。学校やコンクールのルールは必ず確認してください。

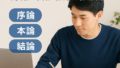
コメント