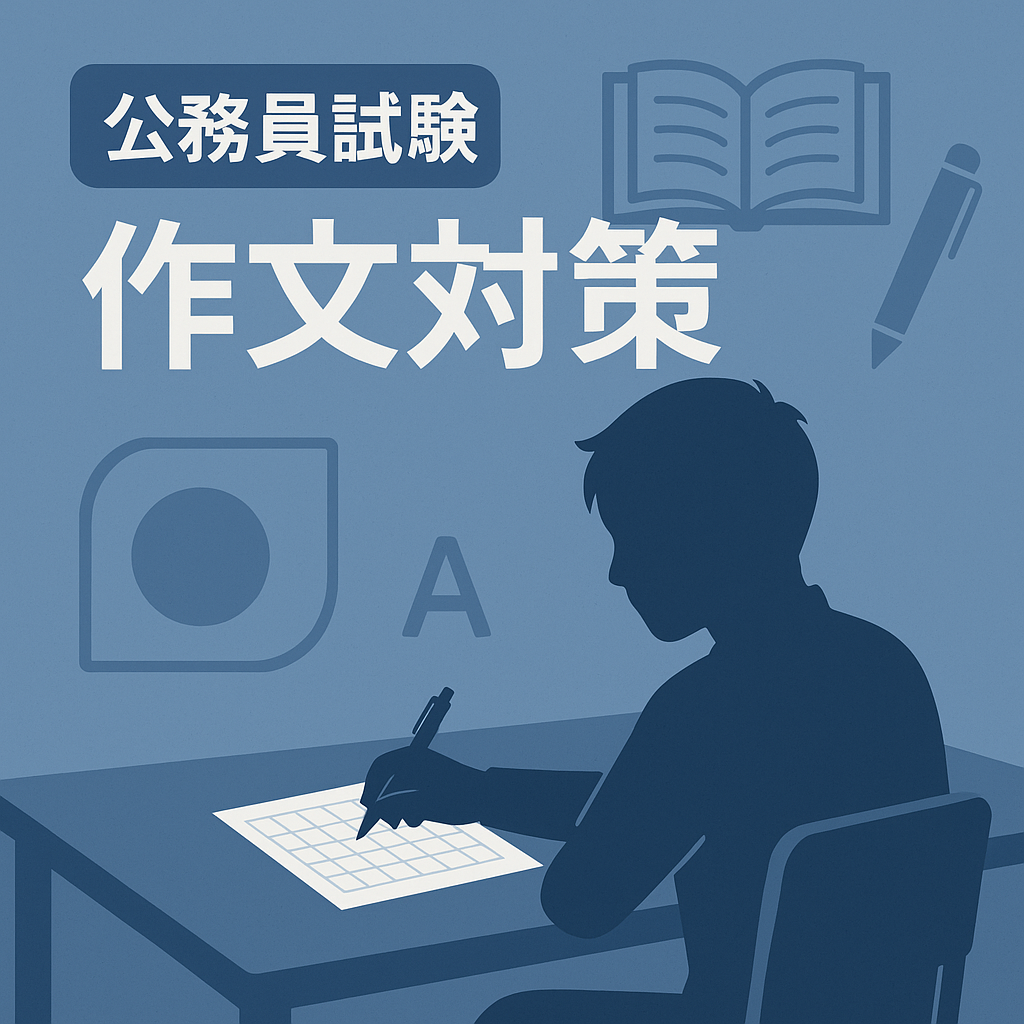
「作文試験って何を書けばいいの?」 「筆記試験は通ったのに作文で落ちた…」 「公務員らしい文章ってどう書くの?」
公務員試験において、作文・小論文試験は多くの受験生が苦戦する科目です。実際、筆記試験で高得点を取っても、**作文試験で不合格になるケースは全体の約30%**にも上ります。
この記事では、元公務員試験採点官として1000本以上の作文を評価してきた経験から、確実に合格点を取るための実践的な書き方を具体的にお伝えします。
なぜ公務員試験で作文が重視されるのか?
採点官が作文で本当に見ているポイント
多くの受験生が誤解していますが、採点官は作文で「文章の上手さ」だけを見ているわけではありません。
実際に評価されているのは:
- 公務員としての適性:住民目線で考えられるか
- 論理的思考力:筋道立てて説明できるか
- 社会問題への関心:時事・行政課題を理解しているか
- 実行力・具体性:現実的な解決策を提案できるか
- 人格・価値観:公共の利益を優先できるか
作文試験の配点と影響力
| 試験区分 | 作文配点 | 筆記との比率 | 不合格率 |
|---|---|---|---|
| 国家一般職 | 2/10点 | 20% | 約25% |
| 地方上級 | 3/10点 | 30% | 約30% |
| 市役所 | 4/10点 | 40% | 約35% |
特に地方公務員試験では、作文の配点が全体の30-40%を占めるため、軽視すると致命的です。
【完全版】公務員試験作文の基本構成
黄金の4段構成
1. 序論(全体の15%)
役割: 問題提起・立場表明
テンプレート:
近年、【社会状況・背景】が課題となっている。
この【問題】について、私は【基本的な立場・考え】と考える。
以下、その理由を述べる。
良い例:
近年、少子高齢化の進行により、地域コミュニティの維持が困難になっている。
この課題について、行政と住民の協働による新たな支え合いの仕組みが必要であると考える。
以下、その理由を述べる。
悪い例:
少子高齢化は大変な問題です。何とかしなければいけないと思います。
2. 現状分析(全体の25%)
役割: 問題の具体化・データ提示
テンプレート:
まず、【問題】の現状を整理すると、【具体的なデータ・事例】となっている。
この背景には【原因1】【原因2】があると考えられる。
特に【最も重要な原因】は、【詳細な説明】という深刻な影響を与えている。
3. 解決策提示(全体の45%)
役割: 具体的な対策・公務員としての役割
テンプレート:
この課題に対し、行政として以下の取り組みが重要である。
第一に、【対策1】が必要である。
具体的には【詳細な方法・手段】により、【期待される効果】を実現できる。
第二に、【対策2】も不可欠である。
【先進事例・参考例】のような取り組みを参考に、【実施内容】を進めるべきである。
公務員として、私は【自分の役割・貢献】に取り組み、【実現したい状態】に貢献したい。
4. 結論(全体の15%)
役割: まとめ・決意表明
テンプレート:
以上のことから、【問題解決】には【包括的な取り組み】が必要である。
私は公務員として、【具体的な決意・行動】により、【理想的な社会・地域】の実現に尽力したい。
【テーマ別完全攻略】頻出10テーマと模範答案
1. 少子高齢化と地域社会
出題傾向: 国家・地方ともに最頻出 評価のポイント: 具体的な地域課題と行政の役割
模範答案(800字)
我が国は世界に類を見ない速度で少子高齢化が進行し、地域社会の維持が危機的状況にある。この課題について、行政と住民の協働による新たな支え合いの仕組み構築が急務であると考える。以下、その理由を述べる。
総務省の統計によると、2025年には65歳以上の高齢者が人口の30%を超え、同時に出生率は1.3を下回る状況が続いている。この背景には、若年層の経済的不安定、核家族化の進行、地域コミュニティの衰退がある。特に地方部では、高齢者の孤立と子育て世帯の支援不足が同時進行し、地域全体の活力低下を招いている。
この課題に対し、行政として以下の取り組みが重要である。
第一に、多世代交流の場づくりが必要である。具体的には、高齢者の知識・経験を子育て支援に活かす「世代間支援プログラム」の創設により、高齢者の社会参加促進と子育て世帯の負担軽減を同時に実現できる。先進自治体の事例では、このような取り組みにより高齢者の生きがい創出と子育て満足度向上を達成している。
第二に、地域包括ケアシステムの充実も不可欠である。医療・介護・福祉サービスを地域で一体的に提供することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を整備すべきである。
公務員として、私は住民一人ひとりの声に耳を傾け、地域の実情に応じた柔軟な施策立案に取り組みたい。特に、住民と行政の橋渡し役として、地域の課題を的確に把握し、実効性のある支援策の実現に尽力したい。
少子高齢化は一朝一夕には解決できない課題だが、行政・住民・地域団体が連携することで、誰もが安心して暮らせる持続可能な地域社会を実現できると確信している。私は公務員として、この実現に向けて全力で取り組む所存である。
2. 環境問題・脱炭素社会
出題傾向: SDGs関連で増加中 評価のポイント: 具体的な環境政策と住民協力
重要な論点:
- カーボンニュートラル目標(2050年)
- プラスチックごみ削減
- 再生可能エネルギー導入
- 住民の環境意識向上
構成のポイント:
- 地球温暖化の現状と影響
- 自治体レベルでの具体的取り組み
- 住民参加型の環境保全活動
- 公務員としての啓発・推進役割
3. 災害対策・防災
出題傾向: 地方公務員で特に重視 評価のポイント: 住民の生命・財産を守る具体策
必須要素:
- 自然災害の増加傾向(データ)
- 自助・共助・公助の役割分担
- 避難所運営・情報伝達体制
- 平時からの地域コミュニティ強化
4. デジタル化・情報社会
出題傾向: 国家公務員で頻出 評価のポイント: デジタル格差への配慮
論じるべき内容:
- 行政のDX推進と住民サービス向上
- 高齢者等のデジタル弱者への配慮
- 個人情報保護とセキュリティ
- 対面サービスとの適切なバランス
5. 地域活性化・地方創生
出題傾向: 市役所・町村役場で頻出 評価のポイント: 地域の独自性を活かした提案
成功する論述のコツ:
- 地域資源の発見と活用
- 移住・定住促進策
- 地域産業の振興
- 関係人口の創出
採点基準と評価レベル
評価項目と配点(100点満点)
内容・論理性(50点)
- 課題理解(10点): 出題意図を正確に把握
- 現状分析(15点): データに基づく客観的分析
- 解決策(15点): 具体的で実現可能な提案
- 公務員視点(10点): 公共の利益を優先
構成・表現(30点)
- 論理構成(10点): 一貫した流れ
- 文章表現(10点): 適切で明確な表現
- 具体性(10点): 抽象論に終わらない
形式・正確性(20点)
- 文字数(7点): 制限内での適切な分量
- 文法・表記(7点): 誤字脱字・文法ミス
- 原稿用紙使用(6点): 正しい書式
レベル別評価
A評価(85点以上)- 確実合格
- 公務員としての高い適性が認められる
- 具体的で実現可能な提案
- 論理的で説得力のある構成
- データ・事例の効果的活用
B評価(70-84点)- 合格圏
- 基本的な要件を満たす
- 一定の具体性と論理性
- 公務員視点が示されている
C評価(60-69点)- 合格ギリギリ
- 最低限の要件は満たす
- やや抽象的・一般的
- 独自性に欠ける
D評価(59点以下)- 不合格
- テーマから逸脱
- 論理性に欠ける
- 公務員視点が欠如
よくある失敗パターンと対策
失敗パターン1:「一般論・抽象論で終わる」
ダメな例:
少子高齢化は深刻な問題です。みんなで協力して頑張る必要があると思います。
改善例:
少子高齢化に対し、行政は子育て世帯への経済支援と高齢者の社会参加促進を
両輪で進める必要がある。具体的には...
失敗パターン2:「公務員視点の欠如」
ダメな例:
企業が働きやすい環境を作るべきだと思います。
改善例:
行政として、企業の働き方改革を支援する相談窓口の設置と、
好事例の情報共有により、地域全体の労働環境改善に取り組むべきである。
失敗パターン3:「データ・根拠不足」
ダメな例:
最近、環境問題が深刻になっています。
改善例:
環境省の調査によると、CO2排出量は1990年比で○%増加しており、
地球温暖化の進行が懸念されている。
試験当日の時間配分戦略
制限時間60分の場合
1. 構想・メモ(10分)
- テーマ分析と論点整理
- 全体構成の決定
- 使用するデータ・事例の選定
2. 執筆(45分)
- 序論:5分
- 現状分析:10分
- 解決策:25分
- 結論:5分
3. 見直し(5分)
- 誤字脱字チェック
- 論理の一貫性確認
- 文字数確認
時間不足時の対処法
優先順位:
- 序論と結論は必ず完成させる
- 解決策は1つでも具体的に
- 現状分析は簡潔にまとめる
頻出時事・社会問題の基礎知識
必須統計データ(2025年版)
【人口動態】
・合計特殊出生率:1.26(2024年)
・高齢化率:29.1%(2024年)
・生産年齢人口:約7400万人
【労働】
・平均賃金:月額約32万円
・非正規雇用率:約38%
・テレワーク実施率:約30%
【環境】
・CO2排出量:年間約10億トン
・再エネ比率:約22%
・プラごみリサイクル率:約25%
【デジタル】
・マイナンバーカード普及率:約80%
・行政手続オンライン化率:約60%
重要な政府方針・計画
- 2050年カーボンニュートラル
- デジタル田園都市国家構想
- こども未来戦略
- 全世代型社会保障
- 地方創生総合戦略
実践的トレーニング法
段階別学習プログラム
初級(試験3ヶ月前)
- 基本構成の習得
- 頻出テーマの基礎知識収集
- 新聞社説の構成分析(週3回)
中級(試験2ヶ月前)
- 各テーマで1本ずつ執筆(計10本)
- 時間制限での執筆練習
- 添削・フィードバック活用
上級(試験1ヶ月前)
- 本番形式での模擬試験(週2回)
- 苦手テーマの集中対策
- 最新時事の情報更新
自己添削チェックリスト
【内容】
□ テーマに適切に対応しているか
□ 公務員視点が明確に示されているか
□ 具体的なデータ・事例があるか
□ 実現可能な解決策を提示しているか
【構成】
□ 序論・本論・結論が明確か
□ 論理の流れが一貫しているか
□ 適切な段落分けがされているか
【表現】
□ 公務員として適切な文体か
□ 誤字・脱字はないか
□ 文字数制限を守っているか
合格者の共通点
高評価を得た受験生の特徴
- 具体性:抽象論ではなく具体的な提案
- データ活用:統計や事例を効果的に使用
- バランス感覚:様々な立場への配慮
- 実現可能性:現実的で説得力のある内容
- 公共性:常に住民目線・公益優先
まとめ:公務員試験作文で合格するために
公務員試験の作文は、正しい対策をすれば確実に得点源にできる科目です。
成功の5原則:
- 基本構成を守る:序論・現状分析・解決策・結論の4段階
- 公務員視点を忘れない:常に住民目線・公共の利益を優先
- 具体性を重視する:データ・事例で説得力を高める
- 時事問題に敏感になる:日々のニュースを意識的にチェック
- 継続的に練習する:週2-3回の執筆で確実にスキルアップ
今すぐ始められるアクション:
- [ ] 新聞の社説を毎日読む習慣をつける
- [ ] 頻出10テーマで各1本ずつ執筆
- [ ] 基礎統計データを暗記
- [ ] 過去問を分析して出題傾向を把握
多くの受験生が作文対策を後回しにして失敗します。早めに対策を始めた人ほど、確実に合格に近づきます。この記事の方法を実践して、ぜひ公務員試験の合格を勝ち取ってください!
参考資料
- 人事院「国家公務員試験情報」
- 各自治体の過去問題集
- 総務省統計局「日本の統計」
- 内閣府「経済財政白書」
関連記事

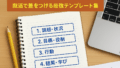
コメント