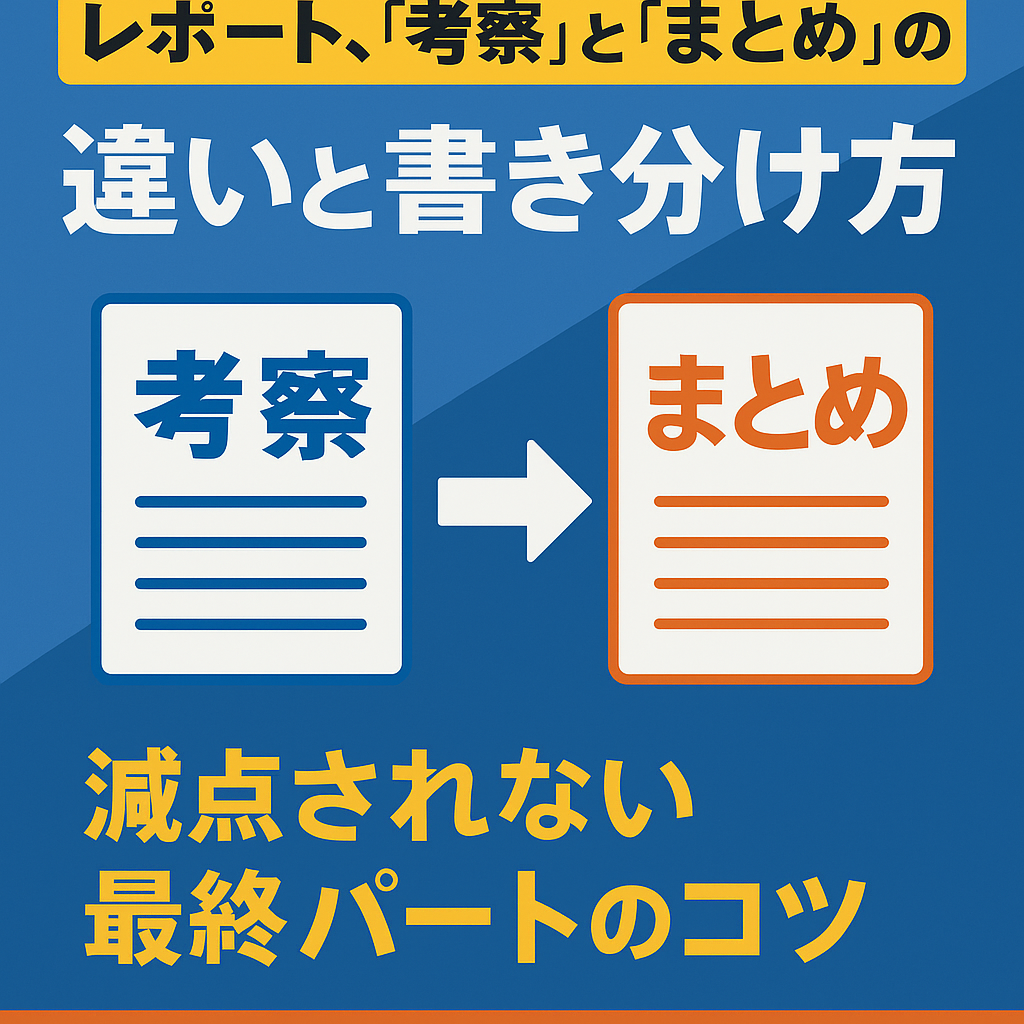
「考察って何を書けばいいの?」「まとめと考察の違いがわからない…」——レポートの最後で手が止まってしまう大学生は少なくありません。
実は、考察とまとめを正しく書き分けられるかどうかで、レポートの評価が大きく変わります。 教授が最後に読むのがこの2つのパートだからです。
この記事では、考察とまとめの明確な違いと、誰でもすぐに使える書き分けテンプレート&例文を詳しく解説します。コピペOKのテンプレートで、今日から高評価レポートを完成させましょう!
考察とまとめの違いを一言で理解する
まず、考察とまとめの根本的な違いを明確にしましょう。
考察とは「結果を解釈し、自分の頭で考える部分」
考察(Consideration/Discussion)は、調査や実験の結果に対して、「なぜそうなったのか」「この結果から何が言えるのか」を自分の言葉で分析する部分です。
- データや結果の原因・理由を推察する
- 結果の意味や影響を評価する
- 今後の課題や改善案を提案する
重要なキーワード: 「なぜなら」「〜と考えられる」「〜という要因が影響している」「したがって」
まとめとは「レポート全体を整理して締める部分」
まとめ(Conclusion)は、レポート全体の内容を簡潔に振り返り、結論を再確認する部分です。 新しい情報は加えず、読者に納得感を与えることが目的です。
- レポートで明らかになったことを再提示
- 結論を簡潔に述べる
- 今後の展望や課題に軽く触れる
重要なキーワード: 「以上のことから」「本レポートでは〜を明らかにした」「今後の課題として」
【図解】考察とまとめの位置づけ
| パート | 役割 | 書くべき内容 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 本論 | 事実・データを提示 | 調査結果、実験データ、事例 | 「調査によれば」「データによると」 |
| 考察 | 結果を解釈・分析 | 原因の推察、意味の評価、提案 | 「なぜなら」「〜と考えられる」 |
| まとめ | 全体を整理して締める | 結論の再確認、今後の課題 | 「以上のことから」「明らかになった」 |
簡単に言うと: 考察は「考える」パート、まとめは「整理する」パート。この意識を持つだけで、書く内容が明確になります。
なぜ考察とまとめの区別が重要なのか?
教授は「考察」で学生の理解度を判断する
教授がレポートで最も重視するのが「考察」です。 なぜなら、考察には「学生がデータをどう理解し、どう考えたか」が表れるからです。
考察が弱いと、以下のように判断されます:
- 「結果をただ羅列しているだけ」
- 「自分の頭で考えていない」
- 「内容を理解していない」
逆に、考察がしっかりしていれば、多少本論が弱くても評価が上がります。
まとめがないと「締まりのないレポート」になる
まとめがないレポートは、「途中で終わっている」印象を与えます。読者(教授)に「結局何が言いたかったのか」が伝わりません。
まとめを書くことで:
- レポート全体に一貫性が生まれる
- 読者に納得感を与える
- プロフェッショナルな印象になる
【例文で比較】考察とまとめの違い
実際の例文を見ながら、考察とまとめの違いを理解しましょう。
テーマ例:「大学図書館の利用実態調査」
❌ 悪い例:考察とまとめが混同している
【考察とまとめ】
調査の結果、学生の多くが自習目的で図書館を利用していることがわかった。
貸出冊数は減少傾向にある。以上のことから、図書館の役割が変化している。
何が問題か?
- 結果をただ要約しているだけで、「なぜ」がない
- 考察(分析)とまとめ(整理)が区別されていない
- 自分の視点や提案がない
✅ 良い例:考察とまとめを明確に分けている
【考察】
調査結果から、学生の多くは「自習スペース」として図書館を利用していることが明らかになった。
この傾向は、コロナ禍以降にオンライン授業が増加し、自宅での学習環境が不十分な学生が
図書館を「第三の学習空間」として活用していることが一因と考えられる。
また、貸出冊数の減少傾向については、電子書籍やオンラインデータベースの普及が
大きく影響していると推察される。総務省の調査(2023)によれば、
大学生の電子書籍利用率は過去5年で約40%増加しており、
この数値と図書館の貸出減少率が相関している。
したがって、今後の大学図書館は「本を借りる場所」から、
学習支援と電子資料アクセスを提供する「複合的学習拠点」へと
役割を転換する必要があるだろう。
【まとめ】
以上の調査を通じて、大学図書館の利用形態が従来の「書籍の貸出」中心から、
「学習空間としての活用」へと変化していることが明らかになった。
結果として、図書館は電子資料の充実と学習環境の整備という
2つの方向性で機能を強化すべきであるという結論に至った。
今後の課題として、学生のニーズに合わせた空間設計と
デジタルリソースの拡充が挙げられる。
何が良いのか?
- 考察で「なぜそうなったのか」の原因を分析
- データ(総務省調査)を用いて客観性を担保
- 具体的な提案(複合的学習拠点への転換)を提示
- まとめで全体を整理し、結論を簡潔に再確認
- 今後の課題で締めくくり、前向きな印象を与える
よくある失敗パターンと改善方法
大学生が陥りがちな失敗パターンを紹介します。
失敗パターン1:考察で結果を要約するだけ
問題点
【考察】
調査の結果、図書館利用者の80%が自習目的であった。
貸出冊数は前年比20%減少した。
これは考察ではなく、単なる結果の再掲です。「なぜ」がありません。
改善方法
- 「なぜその結果になったのか」を推察する
- 「その結果が意味することは何か」を分析する
- 具体的な改善案や提案を加える
改善例
【考察】
調査の結果、図書館利用者の80%が自習目的であった。この背景には、
オンライン授業の増加により、対面での学習機会が減少し、
学生が静かな学習環境を求めて図書館に集まっていると考えられる。
また、貸出冊数の20%減少は、電子書籍の普及が主な要因であろう。
したがって、図書館は物理的な学習空間の価値を再認識し、
席数の拡充や予約システムの導入を検討すべきである。
失敗パターン2:まとめで新しい情報を書く
問題点
【まとめ】
以上のことから、図書館の役割が変化していることがわかった。
今後、海外の事例として、スタンフォード大学では...
まとめで新しい情報(海外事例)を出すと、論理がぶれます。
改善方法
- 新しい情報は本論または考察に入れる
- まとめは既に述べた内容の整理にとどめる
改善例
【まとめ】
以上のことから、図書館の役割が従来の貸出機能から
学習空間としての機能へと変化していることが明らかになった。
今後は電子資料と物理空間の両立が課題となる。
失敗パターン3:考察とまとめを区別せず1段落で終わる
問題点
【考察・まとめ】
調査の結果、図書館の利用形態が変化している。
今後は学習空間として機能を強化すべきである。
考察と考察とまとめが混ざっており、構成が不明確です。
改善方法
- 必ず「考察」と「まとめ」を分けて見出しをつける
- 考察で分析・提案、まとめで整理・締めと役割を明確化
【コピペOK】考察とまとめの書き方テンプレート
そのまま使えるテンプレートを用意しました。自分のレポートに合わせてカスタマイズしてください。
考察テンプレート(基本型)
【考察】
1. 本調査/実験の結果、[結果の要約]が明らかになった。
2. この結果の背景には、[原因・要因の推察]があると考えられる。
[根拠・データ・先行研究]によれば、[補足説明]。
3. また、[別の視点・要因]も影響している可能性がある。
例えば、[具体例]が挙げられる。
4. したがって、今後は[提案・改善案]が重要となるだろう。
具体的には、[具体的な提案]を検討すべきである。
考察テンプレート(理系・実験レポート用)
【考察】
1. 実験の結果、[測定値・観察結果]という結果が得られた。
2. この値は理論値[理論値]と比較すると、[差異の説明]である。
この誤差の原因として、[誤差要因1]と[誤差要因2]が考えられる。
3. 特に[要因]については、[詳細な分析]が影響したと推測される。
4. 今後の改善点として、[実験方法の改善案]や
[測定精度向上の方法]を導入することで、
より正確なデータが得られると考えられる。
まとめテンプレート(基本型)
【まとめ】
1. 本レポートでは、[テーマ]について調査/分析を行った。
2. 結果として、[主要な発見1]と[主要な発見2]が明らかになった。
3. 以上のことから、[結論]という結論が導かれる。
4. 今後の課題として、[課題1]や[課題2]が挙げられる。
これらの点について、さらなる研究/検討が必要である。
まとめテンプレート(短縮型)
【まとめ】
本レポートでは[テーマ]について論じ、[結論]という結論に至った。
今後は[今後の展望]が課題となるだろう。
実践例:テンプレートを使った完成形
テンプレートを実際に使った例を紹介します。
テーマ:「SNSが若者のコミュニケーションに与える影響」
【考察】
本調査の結果、SNS利用者の約70%が「対面よりも気軽に意見を言える」と
回答していることが明らかになった。
この結果の背景には、SNSが非同期コミュニケーションを可能にし、
発言前に内容を吟味できる時間的余裕があることが影響していると考えられる。
山田(2022)の研究によれば、若者は対面での即興的な会話に
プレッシャーを感じる傾向があり、SNSがその緊張を緩和する
「バッファー」として機能しているという。
また、SNS上での「いいね」やコメント機能が、
自己肯定感の向上に寄与している可能性も考えられる。
実際、調査対象者の65%が「SNSで肯定的反応を得ることで自信がつく」と回答している。
したがって、SNSは若者のコミュニケーション手段として、
対面コミュニケーションを代替するのではなく、
補完する役割を果たしていると結論づけられる。
今後は、SNSと対面コミュニケーションのバランスを
どのように取るかが課題となるだろう。
【まとめ】
以上の調査を通じて、SNSは若者にとって対面コミュニケーションを
補完する重要なツールであることが明らかになった。
結果として、SNSは「気軽さ」と「時間的余裕」を提供することで、
若者のコミュニケーション障壁を低減させているという結論に至った。
今後の課題として、SNS依存による対面コミュニケーション能力の
低下を防ぐための教育的取り組みが挙げられる。
考察とまとめで評価を上げる5つのコツ
コツ1:考察では必ず「なぜ」を入れる
結果を述べるだけでなく、「なぜその結果になったのか」を必ず分析しましょう。
コツ2:客観的根拠(データ・先行研究)を1つは引用する
「〜と考えられる」だけでなく、「○○の研究によれば」とデータで補強すると説得力が増します。
コツ3:まとめは200〜300字程度に抑える
まとめは簡潔に。長すぎると冗長になります。
コツ4:今後の課題・展望を必ず入れる
「今後は〜が課題である」と締めることで、前向きで完成度の高い印象を与えます。
コツ5:小見出しで「考察」「まとめ」を明示する
見出しをつけることで、構成が明確になり、教授が読みやすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 考察とまとめは必ず両方書かないといけませんか?
基本的には両方書くべきです。ただし、短いレポート(1000字以下)の場合は「結論」として1つにまとめることもあります。課題の指示を確認しましょう。
Q2. 考察で「〜と思う」「〜な気がする」は使っていいですか?
避けるべきです。「〜と考えられる」「〜と推察される」など、客観的な表現を使いましょう。
Q3. まとめで序論の内容を繰り返してもいいですか?
はい。序論で述べた主張を、まとめで再確認するのは有効です。ただし、全く同じ文章ではなく、言い換えましょう。
Q4. 理系の実験レポートでも考察とまとめは分けるべきですか?
はい。実験レポートでは「考察(誤差の原因分析や改善案)」と「結論(実験結果のまとめ)」を分けて書くのが一般的です。
合わせて読みたい関連記事
大学生・社会人の必須文章! レポートの書き方と基本テクニック(ひな型・テンプレート付き)
【2025年最新】大学1年生必見!教授が高評価する実践的レポート作成完全マニュアル
【初心者向け】レポート・論文に使える情報源&資料の探し方まとめ
まとめ:考察とまとめの書き分けが評価を決める
考察とまとめを正しく書き分けられるようになれば、どんなテーマのレポートでも高評価を得られます。
この記事の重要ポイント
- 考察は「なぜ」を分析するパート、まとめは「整理」するパート
- 考察では原因・理由・提案を必ず含める
- まとめでは結論の再確認と今後の課題を簡潔に述べる
- 必ず小見出しで「考察」「まとめ」を分けて書く
教授が最後に読むのが考察とまとめです。 ここを丁寧に書けば、レポート全体の印象が格段に良くなります。今日からこのテンプレートを使って、評価されるレポートを完成させましょう!
この記事が役に立ったら、ブックマークして次回のレポート作成に活用してください!

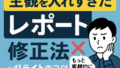
コメント