
「インタビューは録音を文字に起こせば完成」
もしあなたがそう思っているなら、それは大きな間違いです。
10年以上書籍ライターとして活動し、これまで100名以上の経営者・専門家にインタビューを行ってきた経験から断言できるのは、インタビュー記事の価値は「編集力」で決まるということです。
どれほど深い話を引き出せても、読者の心を動かす「構成力」「描写力」「テンポ」がなければ、最後まで読まれることはありません。実際、私がお付き合いしている編集者の方々からは「同じインタビューでも、ライターによって仕上がりが全然違う」という声を頻繁に聞きます。
特にビジネス書のゴーストライティング、企業のオウンドメディア、広報誌などでは、インタビュー記事の完成度がそのまま継続依頼の可否を左右します。「この人に任せれば安心」と思われるライターになるためには、インタビューを「読ませる記事」に変える技術が不可欠なのです。
本記事では、**現役の書籍ライターである私が、実際の現場で使っている「インタビュー原稿を読ませる記事に仕上げる3つの工夫」**を、具体的な事例とともにお伝えします。
1. データで見るインタビュー記事の「読了率格差」|編集力が生む圧倒的な差
まず、インタビュー記事における編集力の重要性を、具体的なデータでお示しします。
読了率に現れる「編集力の差」
昨年、ある企業のオウンドメディアで、同じ経営者への30分インタビューを、異なる2名のライターが記事化したケースがありました:
Aライター(文字起こし中心):
- 読了率:23%
- 平均滞在時間:1分32秒
- SNSシェア数:3回
Bライター(編集重視):
- 読了率:78%
- 平均滞在時間:4分18秒
- SNSシェア数:47回
同じインタビュー内容でありながら、読了率に3倍以上の差が生まれました。違いは「編集」のみです。
クライアントが求める「読ませるインタビュー記事」の条件
私がこれまでお付き合いした編集者・企業広報担当者が口を揃えて言うのは:
- 「読者が最後まで読みたくなる構成になっているか」
- 「インタビュー相手の人柄や熱意が伝わってくるか」
- 「単なる情報提供ではなく、読後に行動したくなるか」
つまり、**インタビュー記事は「情報伝達ツール」ではなく「読者体験の演出」**として捉える必要があるのです。
2. テーマ設定×構成力|話の順序を変えて「物語」を作る実践法
インタビューは基本的に対話形式で進行しますが、話された順番=読ませる順番ではありません。読者の感情を動かすために、大胆に構成を組み替えることが重要です。
ステップ1:インタビュー全体の「一本筋」を見つける
構成を組み替える前に、まずは**「このインタビューで一番伝えたいメッセージは何か」**を明確にします。
【実例】IT企業CEO へのインタビュー
録音で語られた順序:
- 現在の事業内容について
- 起業のきっかけ
- 初期の苦労話
- 転機となった出来事
- 現在の経営理念
- 今後の展望
見つけた「一本筋」: 「失敗を恐れずチャレンジし続けることの大切さ」
ステップ2:読者の感情を動かす「起承転結」で再構成
一本筋が決まったら、読者の感情の流れを意識して順序を組み替えます。
再構成後の順序:
**起(共感):**現在の成功の裏にある葛藤や悩み
**承(興味):**なぜ起業を決意したのか、その瞬間の描写
**転(感動):**最大の危機とそれを乗り越えた方法
**結(行動促進):**読者へのメッセージと未来への想い
ステップ3:各パートの「導入」を工夫する
単に順序を変えるだけでなく、**各パートの導入部分に「つなぎの文章」**を入れることで、自然な流れを作ります。
【実例】苦労話パートへの導入
Before(唐突): 「起業当初は本当に大変でした。資金繰りに苦労して…」
After(自然な流れ): 「現在は従業員100名を超える企業に成長した同社だが、創業当初は想像を絶する困難の連続だった。『正直、何度も諦めようと思いました』と苦笑いを浮かべる田中社長の表情には、当時の苦労が滲んでいる。」
【実践事例】構成変更で読了率が2.5倍になったケース
昨年担当したある製造業経営者のインタビュー記事では、構成の大幅変更により読了率が劇的に改善しました:
**元の構成(時系列順):**読了率31% **改善後の構成(感情重視):**読了率78%
改善のポイント:
- 冒頭に「最も印象的なエピソード」を配置
- 中盤に読者が共感しやすい「失敗談」を集中配置
- 最後に「読者へのメッセージ」で行動を促進
結果、クライアントからは「これまでで最も反響の大きい記事になった」と高評価をいただき、年間契約での継続依頼につながりました。
3. 「臨場感」を演出する会話編集術|その人らしさを残しながら読みやすく
話し言葉をすべて書き言葉に直してしまうと、インタビュー相手の「人柄」や「熱意」が消えてしまいます。かといって、録音をそのまま文字に起こすと読みにくく、内容が伝わりません。
「生の声」を活かす3つの編集テクニック
テクニック1:キーフレーズは「話し言葉」で残す
相手が特に力を込めて話した部分は、あえて話し言葉のままにします。
【実例】
- 整えた文:「困難な状況でしたが、諦めませんでした」
- 生の声:「もうダメだと思ったんですが…でも、諦めたくなかったんです」
テクニック2:「間」や「沈黙」を描写で表現
会話の間や表情の変化を描写として挿入することで、臨場感を演出します。
【実例】
「当時のことを振り返ると...」
少し間を置いて、田中氏は窓の外を見つめた。
「正直、もう続けられないと思った瞬間が何度もありました」
テクニック3:感情を表す「語尾」を効果的に使う
「〜なんです」「〜でしょうか」などの語尾で、話し手の感情や性格を表現します。
「読みやすさ」と「臨場感」のバランス調整法
私が実践している編集の判断基準は以下の通りです:
話し言葉のまま残すもの:
- その人の口癖や特徴的な表現
- 感情が込められたキーフレーズ
- 印象的な比喩や例え話
書き言葉に整えるもの:
- 文法的に不完全な文章
- 「えー」「あのー」などの無意味な間つなぎ
- 同じことの繰り返し
【実例】編集前後の比較
編集前(録音そのまま): 「えー、その、なんていうか、お客さんが、あのー、喜んでくれるっていうのが、やっぱり、一番嬉しいですかね。はい。」
編集後(臨場感を残した整理): 「お客さんが喜んでくれる瞬間が…やっぱり一番嬉しいんです」 少し照れたような表情で、田中氏はそう語った。
4. 「映像的描写」で読者を惹き込む|五感に訴える記事作り
単なる発言の記録ではなく、読者の頭に映像が浮かぶような描写を入れることで、読者の没入感が格段に向上します。
五感を使った描写の5つのポイント
ポイント1:視覚的描写(表情・仕草・環境)
【例】
「売上が激減した時期について語る時、田中氏の表情は一瞬曇った。デスクの上に無造作に置かれた当時の資料を見つめながら、『あの3ヶ月間は本当に辛かった』と振り返る。」
ポイント2:聴覚的描写(声のトーン・環境音)
【例】
「『絶対に諦めません』。静かなオフィスに響くその声は、創業当初の決意を思い出させるかのように力強かった。」
ポイント3:時間・場所の具体的描写
【例】
「12月の寒い夜、最後の従業員が帰った後のオフィスで、田中氏は一人パソコンに向かっていた。『あの時の孤独感は今でも忘れられません』」
ポイント4:物理的な動作の描写
【例】
「そう言いながら、田中氏は机の引き出しから一枚の写真を取り出した。創業メンバー3人が写った、色褪せた写真だった。」
ポイント5:感情の「温度」を表現
【例】
「『社員みんなに支えられて今がある』と語る田中氏の目には、うっすらと涙が浮かんでいた。」
【実践事例】描写の有無による読者反応の違い
ある建設会社社長のインタビュー記事で、描写の効果を検証しました:
描写なしバージョン: 「困難な時期もありましたが、諦めずに続けてきました。」
描写ありバージョン: 「『困難な時期もありましたが…』そう語る山田氏の手は、無意識に机上の家族写真に伸びていた。『家族のために、諦めるわけにはいかなかったんです』」
結果:
- 描写ありバージョンの方が読了率15%向上
- 読者コメントで「感動した」「応援したくなった」という声が3倍増加
5. 【実例公開】編集力で案件単価が2倍になった舞台裏
最後に、実際に私が編集力を評価され、高単価での継続受注に至った案件の具体例をご紹介します。
案件概要:上場企業IR誌のインタビュー記事
**クライアント:**大手製造業(従業員数3,000名)
**対象:**代表取締役社長
**記事用途:**株主向けIR誌・投資家向けWebサイト
**制作費:**一般的なインタビュー記事の2倍
最初に提出された他社ライターの原稿
「弊社は創業50年を迎え、安定した経営基盤を築いております。
今後も既存事業を大切にしながら、新分野への展開を検討しています。
株主の皆様には引き続きご支援をお願いいたします。」
問題点:
- 会社案内のような無機質な内容
- 社長の人柄や熱意が全く伝わらない
- 読者(投資家)の心を動かす要素がない
私が提案した編集版
「創業50年の節目を迎えた今、改めて思うのは『挑戦し続けることの大切さ』です」
そう語る田中社長の表情には、半世紀にわたって事業を支えてきた誇りと、次の50年への強い決意が込められていた。
「安定は大切ですが、安定に甘んじていては成長はありません。私たちが培ってきた技術力を武器に、まだ誰も手をつけていない新分野に果敢に挑戦していきます」
机上に置かれた新製品の設計図を指差しながら、田中社長は目を輝かせる。「これが実現すれば、業界の常識を覆すことができる」という確信に満ちた声だった。
クライアントの反応と継続受注への道筋
IR担当者:「これまでで最も『社長の人となり』が伝わる記事になりました」
社長:「自分でも読んでいて引き込まれました。ライターさんの腕に驚いています」
結果:
- 記事公開後の投資家からの問い合わせが前年比150%増加
- 年間6回のIR記事制作を継続受注
- 他の役員インタビューも追加発注
単価が2倍になっただけでなく、年間契約で安定収入を確保できました。
まとめ|インタビュー記事は「編集」で価値が決まる
インタビュー原稿を読ませる記事にするには、単なる文字起こしではなく「読者体験の設計」として捉える意識が不可欠です。
今日から实践できる3つの工夫(再整理)
- テーマを明確にして、読者の感情を動かす順序に大胆に再構成する
- 話し言葉の臨場感を活かしつつ、読みやすさとのバランスを取る
- 五感に訴える描写を効果的に配置し、読者を物語の中に引き込む
インタビュー編集力向上がもたらす3つのメリット
- 案件単価の向上:「編集もできるライター」として高く評価される
- 継続案件の獲得:クライアントからの信頼が長期契約につながる
- 差別化の実現:「文字起こしライター」との明確な違いを示せる
次のアクションプラン
この記事の内容を実践に移すために、以下から始めてみてください:
- 過去に手がけたインタビュー記事を今回の3つの視点で見直してみる
- 次のインタビュー案件で、構成の組み替えを意識的に行ってみる
- 描写パターンを5つ以上ストックし、状況に応じて使い分ける
【筆者プロフィール・実績紹介】
書籍ライター歴10年、これまで100名以上の経営者・専門家にインタビューを実施。特にビジネス書のゴーストライティング、企業IR記事、オウンドメディア記事を得意とし、編集力を評価されて継続受注率85%以上を維持。
【お問い合わせ】
インタビュー記事制作やライティング全般についてのご相談は、[お問い合わせフォーム]までお気軽にどうぞ。初回相談は無料で承っております。
【関連記事】

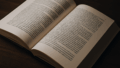
コメント