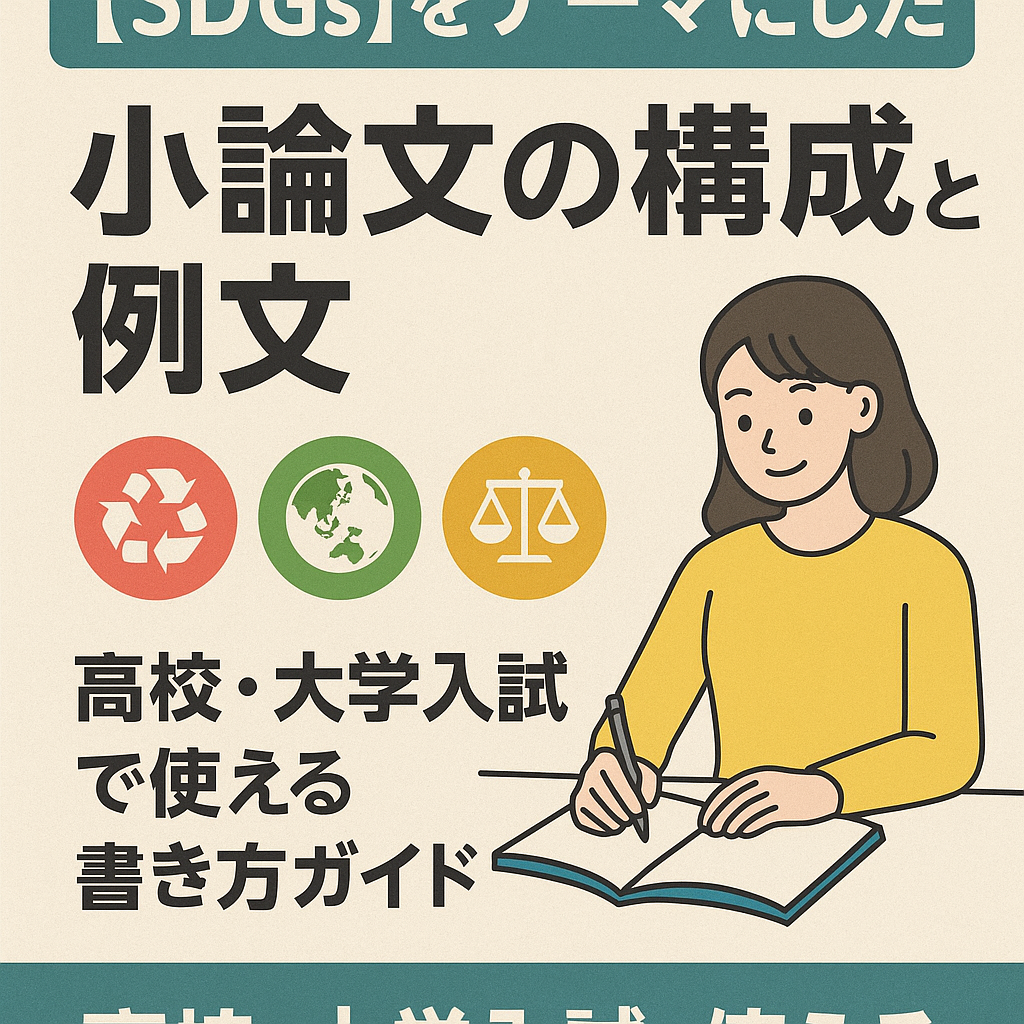
推薦入試や総合型選抜(旧AO入試)で、SDGs(持続可能な開発目標)をテーマにした小論文の出題が急増しています。環境問題、ジェンダー平等、教育格差、貧困対策など、SDGsの17の目標に関連するテーマは、現代社会を生きる私たちにとって避けては通れない課題です。
入試で問われているのは、単なる知識ではありません。「あなた自身がこの問題をどう捉え、どう行動しようとしているか」という思考力と主体性です。
この記事では、SDGsをテーマにした小論文の構成法と、実際に使える例文を紹介します。
SDGsとは?基本をおさえよう
小論文では、テーマの定義を明確にすることが第一歩です。SDGsについて簡潔に説明できるようにしておきましょう。
SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標) とは、2015年の国連サミットで採択された、2030年までに達成すべき17の国際目標です。貧困、教育、気候変動、ジェンダー平等など、地球規模の課題解決を目指す世界共通の指針となっています。
導入部では専門用語を並べすぎず、「定義→なぜ重要か→自分が注目する理由」 の流れで書くとスムーズです。
小論文の基本構成:三段階で組み立てる
SDGsをテーマにした小論文でも、基本の「序論・本論・結論」の三段構成が有効です。
| 段落 | 内容 | 文字数の目安 |
|---|---|---|
| 序論 | SDGsの概要、テーマ選定の理由と問題意識 | 約200字 |
| 本論 | 現状分析、問題点の掘り下げ、自分の考察と具体的提案 | 約400字 |
| 結論 | まとめと将来への展望、自分の行動宣言 | 約200字 |
構成のポイント
- 序論:何が問題なのかを明確に示す(問題提起)
- 本論:なぜそう考えるのか、根拠と具体例を示す(論証)
- 結論:自分はどうしたいのか、将来の姿勢を示す(主体性)
この型を守るだけで、論理的で読みやすい小論文になります。
よく出題されるSDGsテーマ一覧
入試では、17の目標の中から特定のテーマが繰り返し出題される傾向があります。
| カテゴリ | 出題例 | 関連する目標 |
|---|---|---|
| 環境 | プラスチックごみ削減と私たちの行動 | 目標12、13、14 |
| 教育 | 教育格差をなくすために必要なこと | 目標4 |
| 貧困・格差 | 貧困の連鎖を断ち切るには | 目標1、10 |
| ジェンダー | 性別に関係なく活躍できる社会とは | 目標5 |
| テクノロジー | AI時代における人間の役割 | 目標9 |
| 地域社会 | 持続可能なまちづくりと地域の課題 | 目標11 |
特に「目標12:つくる責任 つかう責任」や「目標5:ジェンダー平等」は頻出テーマです。
実践例文:SDGs小論文(800字)
テーマ:「つくる責任 つかう責任」と環境問題
私が最も関心を持っているSDGsの目標は「つくる責任 つかう責任」である。私たちが日常的に大量の資源を消費し、廃棄している現実は、環境破壊だけでなく、将来世代の生活基盤をも脅かしている。特にプラスチックごみの問題は深刻で、日本では年間約900万トンが排出され、その一部が海洋汚染の原因となっている。
この問題の根底には、「便利さ」を優先しすぎる私たちの生活習慣がある。コンビニのレジ袋やペットボトルを何気なく使い捨てることが、積み重なって地球規模の環境負荷につながっている。私自身、高校一年生まで環境問題を「遠い国の話」として捉えていたが、授業で海洋プラスチックの実態を知り、日常の小さな選択が未来を左右することに気づいた。
では、私たちに何ができるのか。まず個人レベルでは、マイボトルやエコバッグの使用、詰め替え商品の選択など、身近な行動から変えていくことが重要だ。私の通う高校では、文化祭でリユース食器を導入し、ごみの量を前年比で40%削減できた。この経験から、一人ひとりの意識が変われば、確実に結果が出ることを実感した。
さらに、学校や地域でも、環境教育やリサイクル活動を通じて意識を高める機会を増やすべきだ。行政や企業の取り組みも不可欠だが、最終的に社会を変えるのは、私たち消費者一人ひとりの選択である。
持続可能な社会とは、他人任せではなく、私たちが「未来の地球に責任を持つ」社会だと考える。私は将来、環境に配慮した企業活動に関わり、持続可能な消費を促進できる人材になりたい。SDGsの目標を「自分ごと」として捉え、日々の行動で示すことが、より良い未来への第一歩だと信じている。
高評価につながる書き方のコツ
1. 自分の体験と社会課題をつなげる
抽象的な話だけでなく、具体的な経験を入れることで説得力が増します。
- 「学校の文化祭でリサイクル企画を実施した」
- 「ボランティア活動で貧困問題に触れた」
- 「海外研修で教育格差を目の当たりにした」
2. データや事例を1つ入れる
客観的な情報を加えることで、論文の信頼性が高まります。
- 「環境省によると…」
- 「国連の報告書では…」
- 「○○市の調査結果によれば…」
3. 理想論で終わらせない
「みんなで頑張ろう」では弱い。具体的で実現可能な提案を示しましょう。
- ❌「世界中が協力すれば解決できる」
- ⭕「まず自分の学校でプラスチック削減キャンペーンを始めたい」
4. 批判的思考を示す
一方的な主張ではなく、異なる視点や課題にも触れると深みが出ます。
- 「環境対策にはコストがかかるという指摘もあるが…」
- 「個人の努力だけでは限界があるため、制度改革も必要だ」
レベル別・文字数別の例文集
【例文1】高校入試向け(600字)|テーマ:教育の重要性
私が注目するSDGsの目標は「質の高い教育をみんなに」である。世界では約2億5000万人の子どもが学校に通えていないと言われている。日本では当たり前のように学校に通えるが、それは決して当然ではない。
私は中学二年生のとき、募金活動を通じて発展途上国の教育問題を知った。教科書やノートがなく、学校の建物さえない地域があることに衝撃を受けた。教育を受けられないことで、将来の仕事の選択肢が狭まり、貧困から抜け出せない悪循環が生まれている。
この問題を解決するために、私たちにできることは何か。まず、使わなくなった文房具や本を寄付する活動に参加することが挙げられる。また、募金や啓発活動を通じて、多くの人に問題を知ってもらうことも大切だ。
高校に進学したら、国際協力に関するボランティア活動に参加したいと考えている。教育は人生を変える力を持っている。すべての子どもが平等に学べる世界を実現するために、私も行動していきたい。
【例文2】高校入試向け(800字)|テーマ:地域の環境問題
私の住む地域では、近年、海岸にプラスチックごみが増加している。SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」に関連して、この問題について考えたい。
昨年、学校のクラスで地元の海岸清掃活動に参加した。一時間で集めたごみの量は、45リットルのごみ袋で20袋以上にもなった。ペットボトル、レジ袋、発泡スチロールなど、ほとんどがプラスチック製品だった。このまま放置すれば、海洋生物が誤飲したり、マイクロプラスチックとして生態系全体に影響を与えたりする恐れがある。
なぜこれほど多くのごみが海に流れ込むのか。原因の一つは、私たちの日常生活にある。使い捨て製品を気軽に使い、適切に処理しないことで、ごみが川や海に流出してしまうのだ。また、ごみのポイ捨てや不法投棄も問題である。
この問題に対して、私たちができることは三つある。第一に、マイバッグやマイボトルを使い、プラスチックごみを減らすこと。第二に、正しくごみを分別し、リサイクルを徹底すること。第三に、地域の清掃活動に積極的に参加することだ。
高校では環境委員会に入り、校内でのプラスチック削減キャンペーンを提案したい。美しい海を次世代に残すために、今できることから始めていきたい。
【例文3】大学入試向け(800字)|テーマ:ジェンダー平等
日本のジェンダーギャップ指数は146カ国中125位と、先進国の中で著しく低い。SDGsの目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、日本社会にとって喫緊の課題である。
私がこの問題に関心を持ったきっかけは、高校で女子の理系進学率の低さを知ったことだ。文部科学省の調査によると、理工系学部の女子学生の割合は約16%にとどまる。この背景には、「理系は男子向き」という無意識の偏見や、ロールモデルの不足がある。私自身、理系を志望する際に「女子なのに珍しいね」と言われた経験があり、社会に根強く残るジェンダーバイアスを実感した。
ジェンダー不平等は教育分野だけでなく、雇用や政治の場でも顕著だ。管理職に占める女性の割合は13.2%、国会議員の女性比率は9.9%と、国際的に見ても極めて低い水準にある。この状況は、多様な視点を欠いた意思決定につながり、社会全体の発展を阻害している。
解決には制度改革と意識改革の両面が必要だ。クォータ制の導入や育児支援の充実など、政策的な支援は不可欠である。同時に、性別によるラベリングを避け、個人の能力や適性を重視する文化を育てることが重要だ。教育現場では、幼少期からジェンダーバイアスを取り除く取り組みが求められる。
私は大学で社会学を学び、ジェンダー問題の構造的要因を研究したい。将来は、すべての人が性別にかかわらず自分らしく生きられる社会の実現に貢献したい。平等な社会は、一人ひとりの意識改革から始まると考える。
【例文4】大学入試向け(1000字)|テーマ:食料問題と持続可能性
世界では約8億人が飢餓に苦しむ一方で、年間約13億トンの食料が廃棄されている。この矛盾した現実は、SDGsの目標2「飢餓をゼロに」と目標12「つくる責任 つかう責任」が密接に関連していることを示している。
私がこの問題に関心を持ったのは、高校の海外研修でフィリピンを訪れた際、スラム街で栄養失調の子どもたちを目の当たりにしたことがきっかけだ。一方で日本では、コンビニやスーパーで大量の食品が廃棄されている。農林水産省によると、日本の食品ロスは年間約522万トンにのぼり、これは国民一人当たり毎日茶碗一杯分の食料を捨てている計算になる。
食料問題の根本には、グローバルな供給システムの歪みがある。先進国は安価な食料を大量に輸入し、消費期限前の商品を次々と廃棄する。一方、発展途上国では気候変動による干ばつや洪水が農業生産を脅かし、十分な食料を確保できない状況が続いている。さらに、食料生産そのものが環境負荷を生み出し、温室効果ガスの排出や森林破壊の原因となっている。
この複雑な問題に対して、多角的なアプローチが必要だ。第一に、個人レベルでは、食品ロス削減のために必要な量だけ購入し、賞味期限を正しく理解することが重要である。私自身、フードシェアリングアプリを活用し、廃棄予定の食品を購入する取り組みを始めた。第二に、企業には、過剰生産を避け、売れ残り商品を食品バンクに寄付するなどの対策が求められる。第三に、行政は、学校給食での地産地消の推進や、食育プログラムの充実を図るべきだ。
加えて、持続可能な農業への転換も不可欠である。化学肥料や農薬に依存した大規模農業から、環境負荷の少ない有機農業や循環型農業へのシフトが求められる。都市部では、垂直農法やスマート農業といった技術革新も注目されている。
しかし、個人や企業の努力だけでは限界がある。国際社会全体で、食料の公平な分配システムを構築し、途上国の農業支援を強化する必要がある。同時に、気候変動対策を進め、持続可能な食料生産の基盤を守ることが重要だ。
私は大学で農業経済学を学び、将来は食料問題の解決に貢献したい。すべての人が十分な食料を得られ、かつ地球環境を守れる持続可能な食料システムの構築を目指したい。食の問題は、人間の尊厳と地球の未来に直結する課題である。私たち一人ひとりが「食べる」という行為の意味を見つめ直し、責任ある選択をすることが、より良い未来への第一歩となる。
各レベルの書き方のポイント
高校入試(600-800字)
- 個人的な体験を中心に書く
- 具体的でわかりやすい例を使う
- 自分にできることを明確に示す
- 難しい専門用語は避ける
- 素直な言葉で等身大の思いを表現
大学入試(800-1000字)
- データや統計を効果的に使う
- 構造的な問題分析を示す
- 多角的な視点から考察する
- 批判的思考を取り入れる
- 将来の専門分野との関連を示す
まとめ:SDGsは「自分ごと」として書こう
SDGsをテーマにした小論文で大切なのは、知識の量ではなく、あなた自身の思考の深さと行動意欲です。
採点者が見ているのは、「あなたがこの問題をどう捉え、どう向き合おうとしているか」。きれいごとよりも、等身大の視点で問題意識を持ち、自分なりの答えを示すことが何より重要です。
この記事で紹介した構成法と例文を参考に、ぜひ自分らしい小論文を書いてみてください。
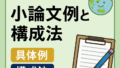
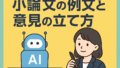
コメント