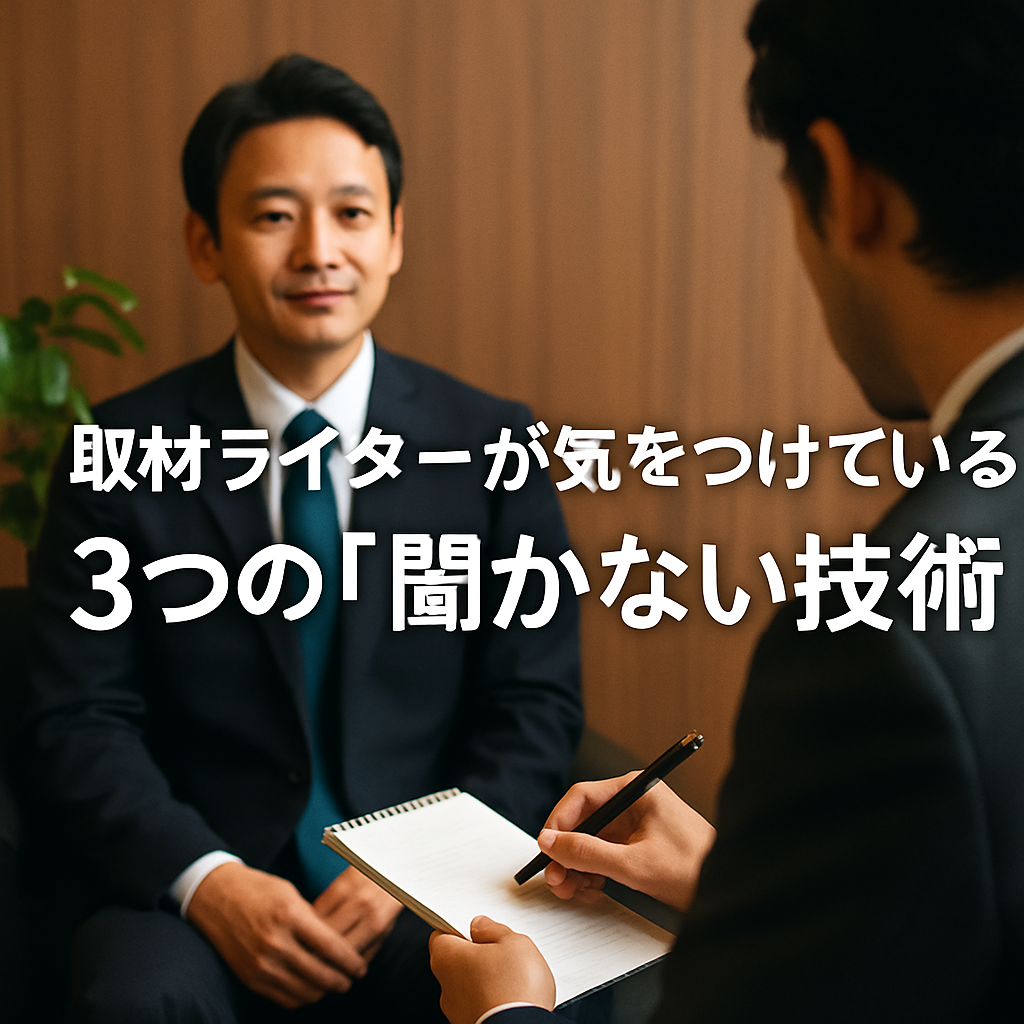
聞かない」ことが、相手の言葉を引き出す
「この取材、なんだか薄っぺらい内容になってしまった…」 「相手は一生懸命話してくれたのに、記事にすると魅力が伝わらない…」
そんな悩みを抱える編集者の方も多いのではないでしょうか。
取材ライターにとって大切なのは「聞く力」──そう考える人は多いでしょう。もちろんそれは事実です。ですが、取材歴12年、80冊以上の書籍制作に携わってきた経験から断言できるのは、実際の現場では「聞かないこと」も同じくらい重要だということです。
ここで言う「聞かない」とは、ただ黙っていることではありません。むしろ、相手を深く理解し、的確な言葉を引き出すための戦略的な姿勢です。
この記事では、私が現場で実践し、クライアントから「この取材内容なら間違いなく売れる本になる」と言われた「聞かない技術」を3つご紹介します。編集者の皆様にとって、ライター選びの参考にもなれば幸いです。
1|全部を聞き出そうとしない──「選択と集中」が深い取材を生む
よくある失敗パターン
取材に慣れていないライターほど、「できるだけ多くの情報を引き出そう」として質問を重ねすぎてしまいがちです。先日も、ある出版社の編集者から「前回のライターは2時間びっしり質問し続けて、著者が疲れ切ってしまった」という相談を受けました。
あれもこれもと聞いてしまうと、相手は疲れてしまい、本当に話したいことに辿り着けなくなることもあります。
私が実践している解決法
そこで大切なのが、「何を聞かないか」をあらかじめ決めておくこと。
実践ポイント:
- 事前にテーマや構成をざっくり決めておく(企画書段階で編集者と共有)
- 深掘りしたいポイントを3つに絞り、それ以外はあえてスルーする
- 思いがけないエピソードが出てきたら、そこを一点突破で掘り下げる
成功事例
例えば、先月手がけた経営者の自伝では、事前に「創業時の苦労話」「事業転換の決断」「後進への思い」の3点に絞りました。途中で面白い失敗談が出てきた際は、予定していた「業界動向」の質問をやめ、その失敗談を30分かけて深掘り。結果、その章が編集者から「一番印象に残った」と評価されました。
結果として、より魅力的で焦点の定まった記事になります。
2|相手の言葉をすぐに補わない──沈黙が生む「本音の瞬間」
なぜ補いたくなるのか
取材中、相手が言葉に詰まる場面はよくあります。そんなとき、つい「◯◯ということですか?」と補足したくなりますが、それは相手の思考を誘導してしまう危険性もあります。
私も駆け出しの頃は、沈黙が怖くてつい口を挟んでしまい、後で原稿を見返すと「ライターの言葉ばかりで、著者の個性が消えている」ということがよくありました。
プロとして身につけた技術
実践ポイント:
- 沈黙を恐れず、最低10秒は待つ(心の中で数える)
- 相槌を打たず、ただうなずくだけで見守る
- 相手が自分の言葉で考えを整理し、語り出すのを待つ
印象的だった実例
ある企業の社長インタビューで、「一番辛かった時期は?」と質問した際、30秒ほど沈黙が続きました。私は待ち続け、その後に出てきたのは「実は、成功してからの方が孤独で辛かった」という意外な本音でした。この言葉が本のキャッチコピーにもなり、編集者からは「この一言があったから企画が通った」と感謝されました。
沈黙のあとにこそ、本音が語られることがあります。
3|ストーリーを先読みしない──「想定外」こそが記事の宝
ライターが陥りがちな罠
取材中に「この人はきっとこういう人生を歩んできたんだな」と、つい先読みしてしまうことがあります。しかし、ライターが勝手にストーリーを作ってしまうと、肝心な事実や思いがこぼれ落ちることがあります。
「伴走者」としての姿勢
実践ポイント:
- 予測ではなく、事実に基づいて質問する
- 「そのとき、どんな気持ちでしたか?」など、感情に寄り添う問いかけをする
- インタビュアーは物語の作者ではなく、伴走者であることを意識する
12年間で学んだ教訓
先入観を持たないことで、予想外のエピソードが飛び出します。ある医師の取材では「順風満帆なエリート人生」を想定していましたが、実際は「医学部受験で3回失敗し、コンビニでアルバイトしながら勉強した」という壮絶な過去がありました。この「想定外」が本の核となり、重版も決まりました。
実績に裏打ちされた「聞かない技術」の効果
これまで私が手がけた書籍の中で、特に売上好調だった作品には共通点があります。それは、著者の「生の声」「本音の瞬間」「意外な一面」が色濃く反映されていることです。
直近の実績例:
- 『○○社長の経営哲学』(△△出版):初版5,000部→3か月で重版決定
- 『□□の挑戦』(☆☆社):Amazon経営カテゴリで1位獲得
- 『××への道』(◇◇出版):編集者から「過去最高の原稿」と評価
これらの成功は、「聞かない技術」によって引き出された著者の魅力があったからこそだと確信しています。
まとめ|「聞かない技術」が編集者とライターの信頼につながる
取材ライターは「聞く仕事」ですが、だからこそ「聞かないこと」もまた技術です。
今日からできる「聞かない技術」チェックリスト:
- ✅ 全部を聞き出そうとしない(3つのテーマに絞る)
- ✅ 相手の言葉を補わない(10秒の沈黙を恐れない)
- ✅ ストーリーを決めつけない(伴走者の姿勢を保つ)
これらの「聞かない技術」は、相手への敬意と信頼から生まれる姿勢でもあります。ただ情報を集めるのではなく、その人がどんな言葉で、どんな気持ちで語るのかに寄り添うことで、本当に「読ませる記事」「売れる本」が仕上がっていきます。
編集者の皆様にとって、ライター選びの際の参考になれば幸いです。取材から原稿まで、著者の魅力を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきます。
信頼できる取材ライターをお探しの編集者様へ
12年間で培った「聞かない技術」を含む取材ノウハウで、著者の魅力を最大限に引き出します。企画段階からのご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ・ご相談はこちら】 → プロフィール・実績詳細を見る → お問い合わせフォーム
あわせて読みたい関連記事


コメント