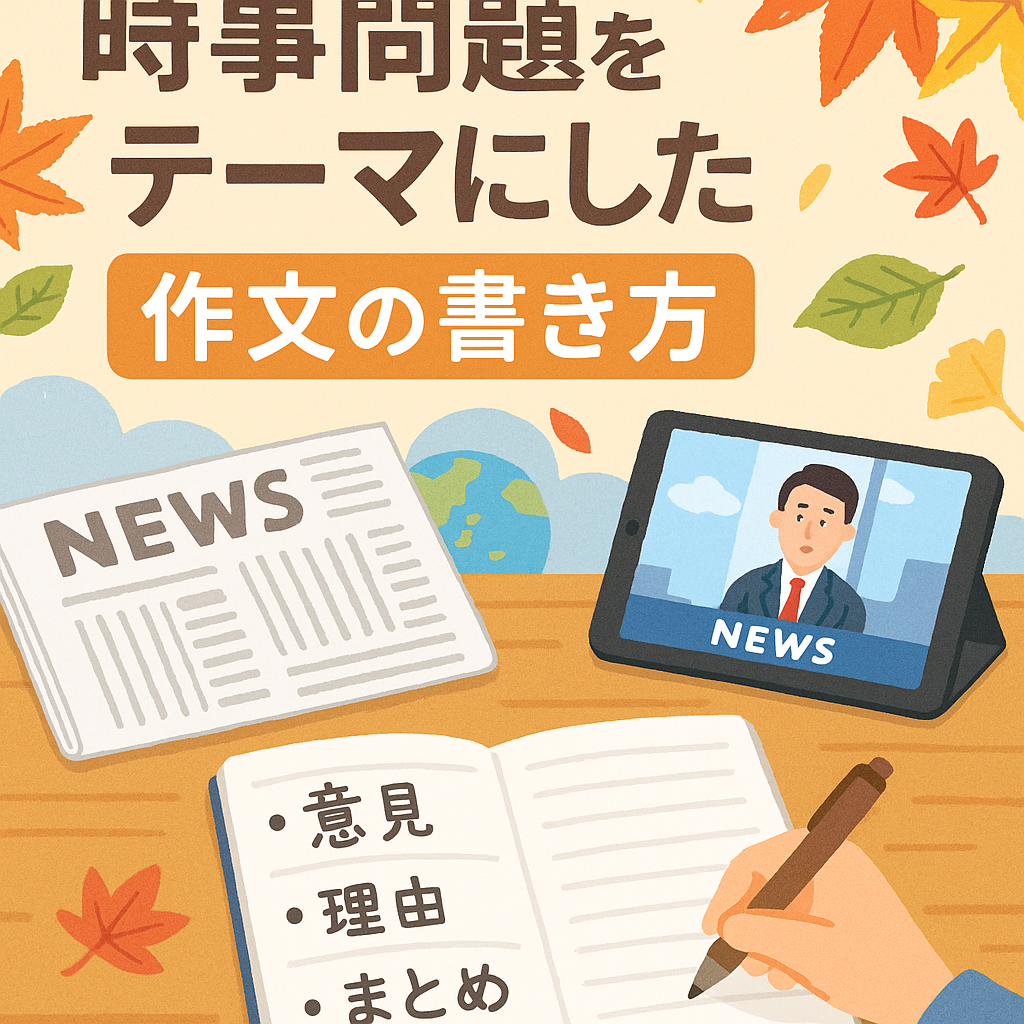
「時事問題の作文、何を書けばいいか分からない…」そんな悩みを抱えていませんか?
高校入試、公務員試験、大学の小論文など、多くの試験で出題される時事問題作文。実は正しい型を知っているだけで、誰でも合格レベルの作文が書けるようになります。
この記事では、15年以上の指導経験を持つ元予備校講師が、時事問題作文の攻略法を徹底解説します。
なぜ今、時事問題作文が重視されるのか?
近年、入試や就職試験で時事問題作文の出題が増えています。その理由は3つあります。
1. 社会への関心度を測るため
採点者が見ているのは「普段からニュースに触れているか」という姿勢です。スマホでゲームばかりしている受験生と、毎日ニュースをチェックしている受験生では、社会人としての準備度が違います。
2. 論理的思考力の確認
知識を暗記するだけでなく、「なぜそう思うのか」を筋道立てて説明できる力が求められています。これは大学でのレポート作成や、社会人になってからのプレゼンテーションでも必須のスキルです。
3. 問題解決能力の評価
「この社会問題に対して、あなたならどう考えるか?」という問いは、将来のリーダーシップを見る質問でもあります。単なる批判ではなく、建設的な提案ができるかが評価されます。
【重要】時事問題作文の絶対ルール
時事作文で失敗する人の多くは、この3つのルールを知りません。
✓ ルール1:感情論だけで終わらせない
「〇〇は問題だと思います」だけでは不十分。なぜそう思うのか、具体例を交えて説明しましょう。
✓ ルール2:極端な主張を避ける
「絶対に禁止すべき」「完全に賛成」のような極論は避け、バランスの取れた意見を示すことが大切です。
✓ ルール3:自分の言葉で書く
ニュースの受け売りではなく、「自分はどう考えるか」を中心に書きましょう。
合格する作文の「黄金パターン」
時事問題作文には、確実に点数が取れる構成の型があります。
【基本の三段構成】
第1段落:導入(問題提起) – 150〜200字
- 最近のニュースや社会的課題を簡潔に紹介
- 「私はこの問題について〇〇と考える」と自分の立場を明確に
例文テンプレート:
近年、〇〇が社会問題となっている。〇〇新聞の報道によれば、〇〇という状況だ。私はこの問題について、〇〇という立場から考えたい。
第2段落:本論(理由・具体例) – 300〜400字
- 自分の意見を支える理由を2〜3点挙げる
- 必ず具体例(体験談、データ、身近な事例)を入れる
- 「第一に」「第二に」などの接続詞で論理を明確に
ポイント:
- 一般論だけでなく、自分の体験を入れると説得力が増します
- 「例えば、私の通う学校では…」という書き出しが効果的
第3段落:結論(まとめ・提案) – 100〜150字
- 意見を簡潔に再度まとめる
- 「今後どうすべきか」の提案や決意を示す
- 前向きな表現で締めくくる
NGな締め方: ❌ 「以上が私の意見です」← 事務的すぎ
❌ 「これは難しい問題だ」← 逃げている印象
良い締め方: ✅ 「私はこの問題に今後も関心を持ち続け、〇〇したい」
✅ 「社会全体で〇〇に取り組むことが求められている」
2025年に出題される可能性が高いテーマTOP7
最新の社会動向から、今年特に出題が予想されるテーマをピックアップしました。
1. 生成AI・人工知能の活用
出題例: 「生成AIが普及する社会について、あなたの考えを述べよ」
押さえるポイント: 便利さと著作権問題、依存のリスクなど両面から考察
2. 少子高齢化と労働力不足
出題例: 「人口減少社会で私たちができることは何か」
押さえるポイント: 移民政策、働き方改革、地域活性化
3. 気候変動と環境問題
出題例: 「脱炭素社会の実現に向けて高校生ができること」
押さえるポイント: 再生可能エネルギー、プラスチック削減、個人の取り組み
4. デジタル社会と情報リテラシー
出題例: 「SNSとの正しい付き合い方について」
押さえるポイント: フェイクニュース、プライバシー保護、デジタルデバイド
5. 災害対策と防災意識
出題例: 「自然災害に強い社会を作るために必要なこと」
押さえるポイント: 自助・共助・公助、日頃の備え、地域コミュニティ
6. グローバル化と国際協力
出題例: 「国際社会における日本の役割について」
押さえるポイント: 平和貢献、経済協力、文化交流
7. 教育の多様化
出題例: 「これからの学校教育に求められるものは何か」
押さえるポイント: オンライン教育、個別最適化学習、いじめ問題
【実践例】採点者が高評価する作文サンプル
テーマ:「生成AIの普及について、あなたの考えを600字以内で述べなさい」
近年、ChatGPTなどの生成AIが急速に普及し、文章作成や画像生成が誰でも簡単にできるようになった。私はこの技術を「正しく理解し、適切に活用すべきもの」だと考える。
理由は二つある。第一に、生成AIは学習効率を大幅に向上させる可能性があるからだ。例えば私は英語の長文読解で分からない部分をAIに質問し、文法構造を理解することで成績が向上した。教師に質問する時間が限られている中、24時間利用できるAIは心強い学習パートナーとなる。第二に、単純作業から解放されることで、人間はより創造的な活動に時間を使えるようになる。データ入力や簡単な文書作成をAIに任せ、人間は企画立案やコミュニケーションなど、人にしかできない仕事に集中できる社会は、生産性向上につながるだろう。
もちろん、著作権の問題や情報の真偽を確認する必要性など、注意すべき点も多い。しかし私は、新しい技術を恐れて拒絶するのではなく、その特性を理解し、人間の能力を補完するツールとして活用していくことが重要だと考える。今後も生成AIの発展に関心を持ち、社会に貢献できる使い方を模索していきたい。
この作文の評価ポイント:
- ✅ 具体的な体験(英語学習での活用)が入っている
- ✅ メリットを2点、明確に説明している
- ✅ 問題点にも触れ、バランスが取れている
- ✅ 前向きな姿勢で締めくくっている
今日から実践できる5つの習慣
習慣1:毎日10分のニュースチェック
朝の通学時間にNHKニュースやYahoo!ニュースをチェック。特に「社会」「経済」カテゴリーに注目しましょう。
習慣2:気になったニュースをメモする
スマホのメモアプリに「日付・見出し・自分の感想」を3行でまとめる習慣をつけましょう。試験直前に見返すと効果的です。
習慣3:週1回、200字の意見文を書く
ニュースを1つ選んで、自分の意見を200字でまとめる練習をしましょう。文章力は書くことでしか上達しません。
習慣4:家族と時事問題について話す
夕食時に「今日のニュースで気になったこと」を話題にしてみましょう。他者の視点を知ることで、考えが深まります。
習慣5:過去問を3題以上解く
志望校や類似試験の過去問を最低3題は解いておきましょう。出題傾向が分かると対策が立てやすくなります。
よくある失敗例と対策
❌ 失敗例1:ニュースの説明だけで終わる
「〇〇という問題があります。以上です。」
対策: 必ず「私は〇〇と考える。なぜなら…」と自分の意見を入れる
❌ 失敗例2:抽象的な内容に終始する
「環境問題は大切だと思います。みんなで協力すべきです。」
対策: 具体例を必ず1つ以上入れる(「例えば、私の学校では…」)
❌ 失敗例3:否定的な結論で終わる
「でも、実現は難しいと思います。」
対策: 必ず前向きな提案や決意で締めくくる
まとめ:合格する作文は「型」で決まる
時事問題作文で高得点を取るための3つのポイントをおさらいしましょう。
- 三段構成(導入→本論→結論)を守る
- 具体例(体験談)を必ず入れる
- 前向きな提案で締めくくる
この型を使えば、どんなテーマでも安定して合格ラインの作文が書けるようになります。
最初は型通りに書くことに抵抗があるかもしれませんが、スポーツの基本フォームと同じです。型をマスターしてから、自分らしさを加えていけば良いのです。
【無料プレゼント】すぐに使える時事問題作文テンプレート集
この記事を最後まで読んでくださったあなたに、特別なプレゼントを用意しました。
「時事問題作文 即効テンプレート集」(PDF・無料)
このPDFには以下の内容が含まれています:
✅ 頻出テーマ別の書き出し文例20パターン
✅ 説得力が増す接続詞一覧表
✅ 印象的な結論の書き方10選
✅ 2025年予想テーマのキーワードリスト
✅ 実際に合格した作文例5本(添削ポイント付き)
【ぜひブックマークしてください!】
このテンプレート集は、時事問題作文の対策に真剣に取り組むあなたのために作成しました。ブックマークして、試験直前まで何度も見返してください。
あなたの合格を応援しています
時事問題作文は、練習すれば必ず上達します。
「何を書けばいいか分からない」という不安は、正しい型を知らないだけ。この記事で紹介した方法を実践すれば、自信を持って試験に臨めるようになります。
試験当日、あなたが自信を持ってペンを走らせている姿を想像してみてください。その未来は、今日からの小さな積み重ねで必ず実現できます。
今すぐできることから始めましょう。まずは今日のニュースを1つチェックして、自分の意見を3行でまとめてみてください。
あなたの合格を心から応援しています。頑張ってください!
【関連記事】
※この記事の内容は2025年10月時点の情報に基づいています。最新の入試情報は各学校の公式サイトでご確認ください。
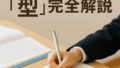

コメント