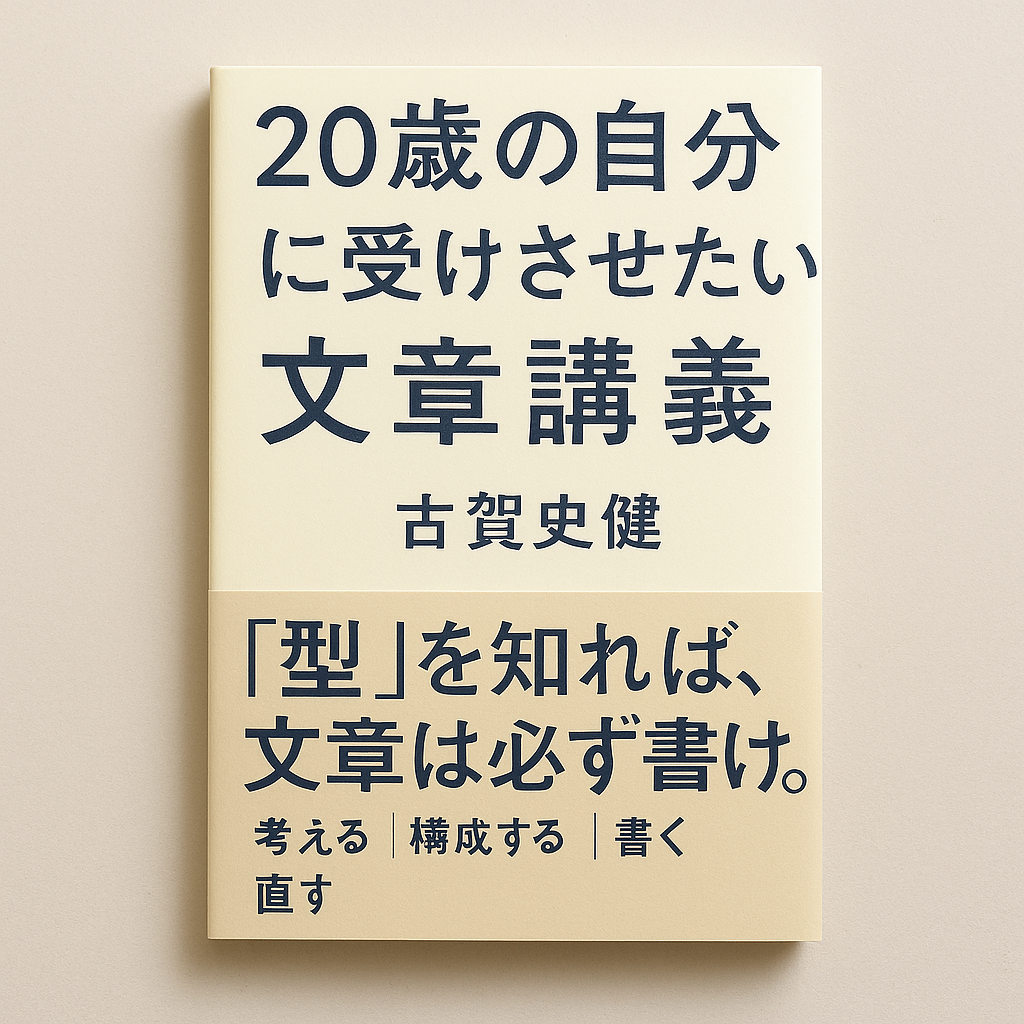
「文章を書くのが苦手で、いつも思うように伝わらない」「頭の中では言いたいことがあるのに、いざ文章にすると支離滅裂になってしまう」「書いた後の見直し方がわからず、いつも自信を持てない」。このような文章の悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
多くの文章術本がテクニックの紹介に終始する中、古賀史健氏の『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は根本的に異なるアプローチを取っています。
この記事では、同書から学べる体系的な文章作成プロセスと、今日から実践できる具体的なメソッドを詳しく解説します。文章力に自信がない方でも、明確な手順に沿って取り組むことで、必ず「伝わる文章」が書けるようになります。
なぜ多くの人が文章で悩むのか
文章の本質を見誤っている現実
多くの人が文章について誤解しているのは、「上手い文章=センスや才能で書くもの」だと思い込んでいることです。しかし実際には、優れた文章は明確なプロセスと技術によって作られています。
古賀史健氏は『嫌われる勇気』をはじめとする数々のベストセラーを手がけたライターです。彼が本書で強調するのは、文章は「技術」であり「訓練可能なスキル」だということです。つまり、正しい方法を学び、適切な手順で練習すれば、誰でも必ず上達できるのです。
「書く前」の準備不足が最大の原因
文章が下手な人の共通点は、いきなり書き始めてしまうことです。料理でレシピを確認せずに材料を鍋に放り込むように、目的や読者を明確にせずに文章を書き始める。これでは、どんなに文才があっても良い文章は生まれません。
優れた文章は「書く前の準備」で80%が決まります。この認識を持つだけで、あなたの文章は劇的に改善されるでしょう。
文章力を確実に向上させる4つのステップ
ステップ1:書く前に「意図」と「読者」を決める
文章作成で最も重要なのは、書き始める前に「誰に、何を、なぜ伝えるのか」を明確にすることです。これを古賀氏は「意図の明確化」と呼んでいます。
具体的な設定方法として、まず読者像を詳しく想像します。年齢、職業、知識レベル、関心事、そして抱えている問題や悩み。読者の顔が具体的に見えるまで想像を深めることで、その人に響く言葉を選べるようになります。
コアメッセージの一文化も重要です。「この文章で伝えたいことは何か」を一文で表現できなければ、読者にも伝わりません。複数のメッセージがある場合は、最も重要な一つに絞り込むか、優先順位をつけて構成に反映させます。
目的の明確化では、読者に求める反応を具体的に設定します。「理解してもらいたい」「共感してもらいたい」「行動を起こしてもらいたい」など、ゴールが明確でなければ、文章の方向性がぶれてしまいます。
ステップ2:構成は「型」から入る習慣化
論理的で説得力のある文章を書くためには、信頼できる構成の「型」を活用することが不可欠です。古賀氏が推奨する代表的な型を紹介しましょう。
PREP法は最も汎用性が高く、ビジネス文書からブログ記事まで幅広く活用できます。Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論の再確認)という流れで、読者の理解を段階的に深めていきます。
SDS法は簡潔性を重視する場面で威力を発揮します。Summary(要点)→Details(詳細)→Summary(要約)の構成で、忙しい読者にも要点が伝わりやすくなります。会議の報告や提案書の冒頭部分に最適です。
問題提起→原因分析→解決提案という型は、読者の悩みを解決する記事や提案書で効果的です。読者が「そうそう、それが知りたかった」と感じる流れを作り出せます。
これらの型を使い分けることで、内容に関係なく一定レベル以上の文章を作れるようになります。慣れてくれば、複数の型を組み合わせたより高度な構成も可能になります。
ステップ3:具体例と抽象化の往復運動をマスターする
読者の理解と納得を得るためには、「具体」と「抽象」を適切に使い分けることが重要です。古賀氏はこれを「往復運動」と表現しています。
具体例の威力は絶大です。抽象的な概念や理論だけでは、読者は「なるほど」と思っても心が動きません。具体的なエピソード、数値データ、身近な比喩を使うことで、読者は「自分のこと」として捉えられるようになります。
抽象化による普遍性も同様に重要です。個別の事例を紹介した後で、「つまり、これは〜ということを意味している」と一般化することで、読者は他の場面でも応用できる学びを得られます。
効果的な往復運動のパターンは以下の通りです。「抽象的な主張→具体的な事例→抽象化された学び」という流れで、読者の理解を段階的に深めていきます。この技術をマスターすることで、説得力のある文章が書けるようになります。
ステップ4:推敲を「チェックリスト」で体系化する
多くの人が苦手とする推敲作業を、古賀氏は「チェックリスト化」することで解決しています。感覚に頼るのではなく、機械的にチェックポイントを確認していく方法です。
文構造のチェック項目として、主語と述語のねじれがないか、一文が長すぎないか(目安は60字以内)、修飾語と被修飾語の関係が明確かを確認します。これらは文章の読みやすさに直結する重要な要素です。
語彙レベルのチェックでは、指示語(これ、それ、あれ)の多用、抽象語の連発、冗長な表現(〜することができる、〜というふうに)を見つけて修正します。これだけで文章の切れ味が格段に向上します。
全体構成のチェックとして、見出しだけを読んで内容の流れが理解できるか、論理の飛躍がないか、結論部分で冒頭の問いに答えているかを確認します。
このチェックリストを習慣化することで、推敲作業が苦痛ではなくなり、確実に文章品質が向上します。
今日から実践できる具体的なワーク集
ワンセンテンス・メッセージの習慣化
文章を書く前に、必ず「この文章で伝えたいことを一文で表現する」練習を行います。複雑な内容でも、核心を一文に凝縮できれば、読者にとって理解しやすい文章になります。
たとえば報告書なら「今四半期の売上は目標を20%上回ったが、来期は競合対策が必要」、ブログ記事なら「時間管理のコツは、重要度と緊急度を分けて考えること」といった具合です。
5分ブリーフィングによる口頭練習
文章を書く前に、内容をPREP法で5分間口頭で説明してみます。話しているうちに論理の破綻や説明不足が見つかり、実際の執筆前に構成を改善できます。
一人で話すのが恥ずかしい場合は、頭の中で「友人に説明するなら」とシミュレーションしてみてください。自然で分かりやすい説明ができるようになります。
音読による文章品質チェック
書き終わった文章を声に出して読むことで、不自然な表現や文章のリズムの悪さを発見できます。つっかえる箇所があれば、そこは読者にとっても読みにくい部分です。
音読時は、句読点の位置、文の長さ、語彙の重複に特に注意を払います。滑らかに読める文章は、読者にとっても理解しやすい文章です。
【関連記事:「構成力が身につく!名著で学ぶ文章読解5選」という記事もおすすめです】
文章スキル向上のための段階的アプローチ
初心者が最初に取り組むべきこと
文章初心者は、まず「型を守る」ことから始めましょう。PREP法を使って短い文章(400~800字程度)を毎日書く練習が効果的です。内容は日記でも読書感想でも構いません。重要なのは、型を意識して書くことです。
毎日の練習メニューとして、朝の10分間でその日のニュースについてPREP法で感想を書く、夜寝る前に今日学んだことを200字で要約する、週末に読んだ本や映画の感想を構成を意識して書く、といった習慣を作ります。
中級者向けの発展技術
基本の型に慣れたら、複数の型を組み合わせたり、読者層に応じて文体を調整したりする練習に移ります。同じ内容でも、専門家向けと一般読者向けでは表現方法を変える必要があります。
文体の使い分け練習では、同じテーマについて敬語文、親しみやすい口調、論文調など、複数のスタイルで書き比べてみます。この練習により、TPOに応じた適切な文章が書けるようになります。
上級者が目指すべき境地
上級者は「型を破る」段階に入ります。基本をマスターした上で、意図的に型を崩したり、独自の構成を作り出したりして、読者に新鮮な驚きを与える文章を目指します。
また、文章を通じて読者の行動変容を促す「影響力」の技術も重要になります。単に情報を伝えるだけでなく、読者の心を動かし、具体的な行動を起こしてもらう文章が書けるようになれば、真の文章力が身についたといえるでしょう。
相乗効果を生む関連書籍の活用法
『20歳の自分に受けさせたい文章講義』の位置づけ
本書は文章術の「基礎体力」を身につけるための本です。基本的なプロセスとマインドセットを学んだ後は、より専門的な技術を扱った関連書籍で知識を深めることをお勧めします。
**『新しい文章力の教室』(唐木元著)**は、より実践的な推敲テクニックと、読みやすさを追求する具体的手法を学べます。古賀氏の本で基礎を学んだ後の次のステップとして最適です。
『新しい文章力の教室』完全活用ガイド – 副業ライターが月10万円稼ぐための文章術習得法
**『文章は接続詞で決まる』(石黒圭著)**では、文章の論理性を高める接続詞の使い方を体系的に学べます。構成力をさらに向上させたい方には特におすすめです。
石黒圭『文章は接続詞で決まる』完全解説 ― 国語研究のプロが明かす「論理の橋渡し」技術で文章力を10倍向上させる方法
**『書くための文章読本』(瀬戸賢一著)**は、文章を書くための読み方、つまり「読者視点」を養成する良書です。他者の優れた文章から学ぶ技術が身につきます。
『書くための文章読本』完全レビュー——物書きが劇的に成長するための日本語表現術バイブル
これらの書籍を段階的に読むことで、文章力を体系的かつ効率的に向上させることができます。
【関連記事:「文章力を伸ばしたい人におすすめの本5選【2025年版】初心者でもすぐ使える!」という記事もおすすめです】
書籍紹介:文章力の基礎を築く必読書
『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(古賀史健著)
本書の最大の特徴は、文章を「技術」として捉え、誰でも習得可能なスキルとして体系化している点です。テクニックの羅列ではなく、「なぜその技術が必要なのか」という理由から丁寧に説明されているため、応用力が身につきます。
特に印象的なのは、実際の悪い文章例と改善例を対比させながら解説している部分です。「こう直せばこんなに良くなる」という変化を具体的に示すことで、読者は改善のポイントを実感として理解できます。
文章に苦手意識を持つ学生から、より効果的な文書作成を目指すビジネスパーソンまで、幅広い読者におすすめできる一冊です。特に「書く前に何をすればいいかわからない」という悩みを持つ方には、目から鱗の内容となるでしょう。
まとめ:文章力は誰でも向上できるスキル
古賀史健氏が『20歳の自分に受けさせたい文章講義』で示した最も重要な洞察は、「文章力はセンスではなく技術である」ということです。適切なプロセスを学び、継続的に練習すれば、誰でも必ず上達できるスキルなのです。
「意図と読者の明確化→型を使った構成→具体と抽象の往復運動→チェックリストによる推敲」という4つのステップを習慣化することで、あなたの文章は劇的に改善されます。重要なのは、完璧を目指すのではなく、毎回少しずつでも意識して取り組むことです。
文章は現代社会における最も重要なコミュニケーションツールの一つです。メール、報告書、プレゼン資料、SNS投稿など、私たちは日々文章を通じて他者とつながっています。文章力の向上は、仕事の効率化、人間関係の改善、そして自分の考えを明確にする思考力の向上にも直結します。
今日から「書く前に5分間考える」「PREP法で構成してみる」「書いた後に音読してみる」といった小さな習慣から始めてみてください。継続することで、必ずあなたの文章は変わっていきます。そして気がついたときには、周囲の人から「文章が上手ですね」と言われる日が来るでしょう。
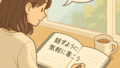

コメント