本稿では、近畿大学図書館司書コースの「情報サービス論[’19-’20]」における、合格レポートを紹介しています。
※内容をそのままコピー&ペーストするのは厳禁です。あくまでも、解答例および書き方の参考にしてください。
設題
設題は次のとおりです。
レファレンスサービスの理論の歩みを簡潔明瞭に記した後、その理論と今日のレファレンスサービスと利用指導(教育機関→図書館利用教育、公共図書館→情報活用能力の育成)の関連を述べ、これからの利用指導はどうあるべきか、貴方自身の考え方を含め論じてください。(2,000字)
レポート作成上の留意事項・ポイント
・箇条書きではなく、文章で書くこと。
・設題の内容をよく理解し、自分の言葉で文章をまとめること。
・テキスト及び参考文献から引用する場合、出典を明確にすること。
・テキスト以外の参考文献を効果的に活用すること。
・感想文やエッセイではなく、指定された教材等の学習効果を明確に反映させること。
・本文文字数は、1,900文字以上であること。
総評基準についてのメッセージ
・テキストなどの丸写しは評価しません。
・記述内容が論理的であるか、結論を述べているかを評価します。
・テキストをよく読んで内容を理解し、レポートの作成に取り組むこと。
・テキストのみならず、参考文献を活用し、その学習効果を明確に反映させること。
合格レポート
1.序論
司書として図書館に従事する人材には、その中核業務である「レファレンスサービス(参考業務)」への理解が不可欠である。とくに、レファレンスサービスの理論を踏まえたこれまでの歩みや利用指導、さらに今後のレファレンスサービスについて考察しておく必要がある。そこで本論では、レファレンスサービスの理論の歩みについてまとめつつ、今日のレファレンスサービスと利用指導との関連、およびこれからの利用指導について論じる。
2.レファレンスサービスの理論の歩み
情報収集過程において、「コンテンツ化されて外部に存在するものにアクセスするための方法(根本2017:66)」であるレファレンス。そんなレファレンスの必要性は、1957年にランガナタンによって著された「図書館学の五法則」に端を発する。とくに、四番目の法則にある「図書館利用者の時間を節約せよ」という言葉は、図書館員が情報調査を担うべき存在であること、および情報調査におけるレファレンスサービスの必要性を如実に表している。
レファレンスサービスの起点には、ウイリアム・ワーナー・ビショップの論文「レファレンスワークの理論」やサミュエル・ロースティンの論文「レファレンスサービスの発達」があるとされている。前者は図書館が発生した時点から何らかの人的援助が行われてきたという見解であり、後者は社会的背景によってレファレンス業務が要請されてきたという見解である。
その後、体系的な参考業務の基礎となったグリーンの「人的援助論」や、利用者教育と媒体的機能に言及したチャイルドの「保守理論」を中心に議論が展開されていく。チャイルドの理論を発展させた「デューイの理論」や、より保守性を高めた「ダナの理論」、さらには保守理論の集大成といわれる「ビショップの理論」など、レファレンス理論は保守色を強めていった。一方でワイヤーは、これまでの保守理論を批判し「自由理論」を提唱。さらにサミュエルは、ワイヤーの理論を発展させ、体系化した。高度な情報化社会となった現代では、保守理論と自由理論の両面から議論が展開されている(毛利,2012)。
3.今日のレファレンスサービスと利用指導について
情報化社会の進展に伴い、今日では、レファレンスサービスの内容にも質的・量的な変化が見られる。質的な変化としては、磁気・電子媒体資料などを含む電子資料の提供や、コンピュータを活用した情報処理知識および主題知識を有する図書館スタッフの活躍などが挙げられる。また量的な変化としては、紙媒体だけでなく、インターネット上の情報をも含む膨大な資料を扱いつつ、学業、就業、さらには生涯学習といった多種多様なニーズに対応することが求められている。その点、情報の直接的な提供を否定する保守理論と、情報の直接提供こそ図書館員の仕事であるとする自由理論という発想があることを踏まえつつ、レファレンスサービス本来の目的を重視した参考業務が行われるべきであろう。
とくにレファレンスサービスと利用指導の関連性から現状を俯瞰すると、学校図書館、大学図書館、公共図書館において、その内容は微妙に異なっているのがわかる。そのことは、学校図書館や大学図書館などの教育機関において、保守理論をベースとした利用者の自立促進と情報の迅速な提供を目指す自由理論が混在していること。さらに公共図書館においては、その規模に応じて自由理論の実践に限界があり、保守理論的な対応にならざるを得ないことと無関係ではない。つまり、今日のレファレンスサービスが保守理論と自由理論の両面から展開されている背景には、現場の実情が加味されているという点を忘れてはならない。
本来、図書館における利用教育とは、「印象づけ」「サービス案内」「情報探索法指導」「情報整理法指導」「情報表現法指導」という五つの領域があるとされている(日本図書館協会2001:13-14)。また、情報探索法指導以下を一つにまとめ、「図書館利用案内」「一般的基礎的な文献探索法指導」「主題文献探索法指導」の3ステップに分けることもあるようだ(毛利2012:73)。とくに学校図書館では、資料を利用するために必要な基礎知識や技術の提供が行われている。一方で大学図書館では、より高度な文献探索法やコンピュータリテラシー教育、さらにはレポート・論文の作成指導なども行われている。さらに公共図書館では、社会教育という観点からより広い意味での利用教育(利用支援)が行われているようだ。今後は、より現場の状況に即した利用指導が求められていくだろう。
4.結論
本論の内容を踏まえて、これからの利用指導はどうあるべきかについても述べておきたい。求められるのは、利用者の求めに応じた受け身の利用指導ではなく、よりレファレンスサービスの利用を促すような積極的な働きかけである。「逐次的」「個別的」「単発的」に実施されてきた利用指導を「計画的」「体系的」「組織的」に実施することはもちろん(日本図書館協会2010:16)、利用者の情報リテラシーを変革するような取り組みが必要だ。
文字数 2089文字
参考文献
根本彰『情報リテラシーのための図書館』2017、みすず書房
毛利和弘『情報サービス論』2012、近畿大学通信教育部
日本図書館協会『図書館利用教育ガイドライン合冊版』2001、日本図書館協会
日本図書館協会『情報リテラシー教育の実践』2010、日本図書館協会
レポート作成のヒント
レポートを作成する際には、以下の点に留意しています。
1.構成を決める
レポートの構成は、「序論」「本論」「結論」が基本となるため、次のように組み立てています。
1.序論: レファレンスサービスを理解することの必要性について
2.本論:「① レファレンスサービスの理論の歩み」と「 ②今日のレファレンスサービスと利用指導について」
3.結論: 本論でまとめた内容に対する、筆者の主張や批判
2.テキストの該当箇所を自分の言葉でまとめる
テキストの内容を参考にしつつ、レファレンスサービスの理論の歩みと、今日のレファレンスサービスおよび利用指導についてまとめました。
このとき、自分の言葉で記述することが重要かと思います。
3.必要に応じて参考書等を使用する
テキストに加えて、参考文献を参照する必要があります。図書館等で、参考文献を入手し、関連する箇所を読み込みます。
また、引用する場合は「」でくくり、出典を記載してください。内容の参考にしただけの場合でも、参考文献に記載します。
キーワード
本設題の場合、次のようなキーワードが挙げられます。これらの言葉に着目しつつ、まとめていく必要があるかと思われます。
・図書館学の五法則
・レファレンスワークの理論、レファレンスサービスの発達
・保守理論と自由理論
・図書館における利用教育
参考文献
図書館利用教育ガイドライン合冊版―図書館における情報リテラシー支援サービスのために
情報リテラシー教育の実践―すべての図書館で利用教育を (JLA図書館実践シリーズ 14)
図書館における利用者教育 理論と実際 (論集・図書館学研究の歩み)
情報リテラシーのための図書館――日本の教育制度と図書館の改革
実地で文章力を高めよう!
コツをマスターしたら、実地で書いてみましょう。
最近では、クラウドソーシングと呼ばれるサイトから、簡単に文章作成やロゴ、デザインを受注できます。もちろん発注も可能です。ちょっとした副収入にもなるので、まずは登録だけでも済ませましょう。登録無料です。
代表的なものとして、最大手のクラウドワークスやランサーズ がオススメです。安心して利用できます。すぐに登録でき、仕事をはじめられるので手っ取り早いですね。価格も数百円~数万円まで幅広いのが特徴です。案件数もかなりあるので、受注・発注ともに活用できます。無料登録だけでもしておきましょう。
ライティングはもちろんのこと、さまざまなスキルを売買できるココナラもオススメです。まずは無料登録だけしておいて、時間が空いたら記事を書いてみましょう。
※プロライターへの「取材・執筆」依頼はコチラ
※稼げるフリーライター養成講座はコチラ
文章の質を高めるために活用できるサイト
文章の基本となる型やテクニックとともに、必要なのが「情報収集力」です。書き方の基礎をマスターしていても、最新の情報や基本となる知識をインプットしていなければ、文章の内容は薄くなります。
そこで、以下に無料で活用できる情報収集サイトを掲載しました。みなが見ている大手サイトではなく、業界ごとのちょっとマニアックなサイトから情報収集することによって、周囲に差をつけることができます。
・Kindle Unlimited (オススメ!)
書籍から漫画、雑誌など、数多くの対象コンテンツを好きなだけ読むことができます。読み放題のサービスの王道です。初めての方は30日間無料で使えるので、ぜひ登録してみましょう。
情報収集の基本と言えば新聞。旧来型のメディアとも言われていますが、有料の情報を得ることで差別化できます。必要なところに必要な投資をすることが、情報収集の秘訣です。就活にも使えます。
・楽天マガジン(オススメ!)
PC、スマホ、タブレットから雑誌を読むならこちら。簡単な申込みをするだけで、全11ジャンル200誌以上のさまざまな雑誌が読み放題です。幅広い知識が簡単に得られます。
・掲載数2800誌以上の取り扱いを誇る『雑誌のオンライン書店Fujisan.co.jp』!多くは送料無料、さらに最大70%割引と大変お得です!
・書店で一番売れているビジネス週刊誌(ABC協会調べ)『週刊ダイヤモンド』がオトク!送料無料・年間3000円以上安くなる・30日間ためし読み可!今すぐ申し込み!
・『ニューズウィーク日本版 Newsweek Japan』日本のメディアにはない深い追求、グローバルな視点。「知とライフスタイル」のナビゲート雑誌。送料無料!さらに最大で1冊400円が280円に!
・現代の悩めるビジネスリーダーの問題解決のバイブル『PRESIDENT(プレジデント)』! 送料無料!更に定期購読なら大幅にディスカウント!
・ジャパンタイムズ発刊の英字新聞『英字新聞 週刊ST』。2004年度で富士山でもっとも売れました!
Web、カメラ、料理など、さまざまなジャンルのワークショップを開催しているのがこちらのサービス。プロから直接まなびたい方にとって最適なサイトです。登録無料。
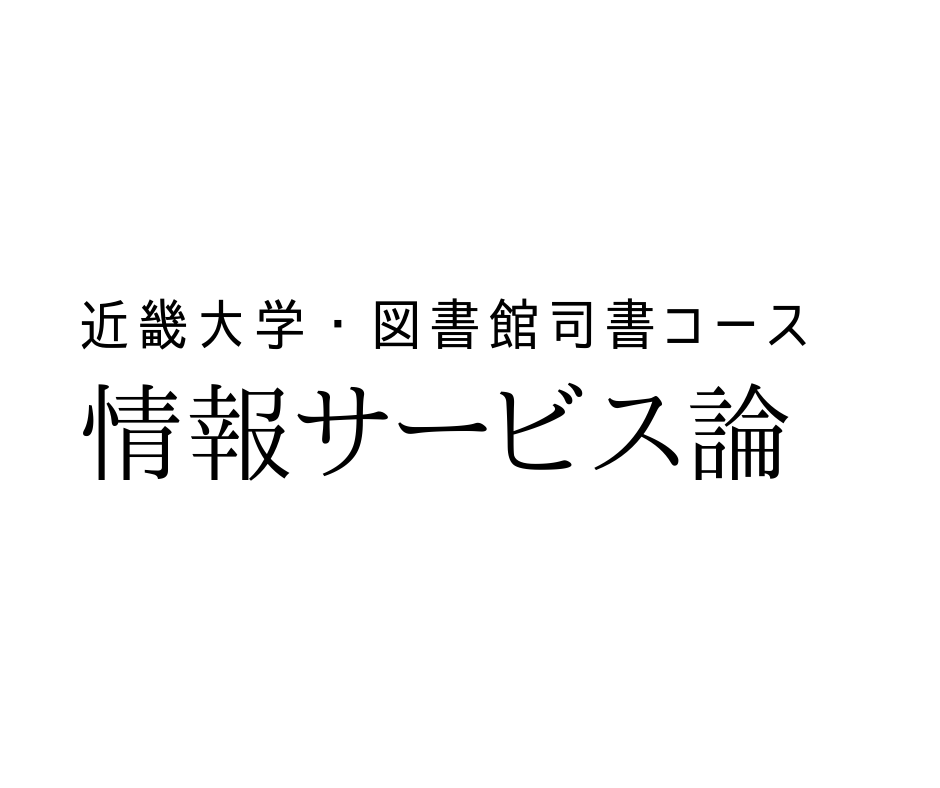
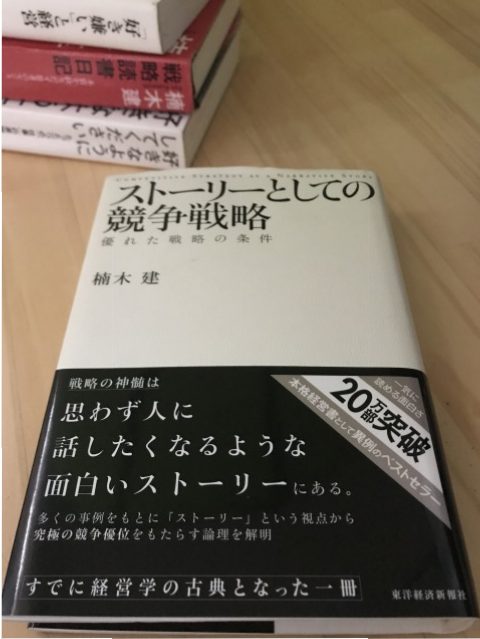
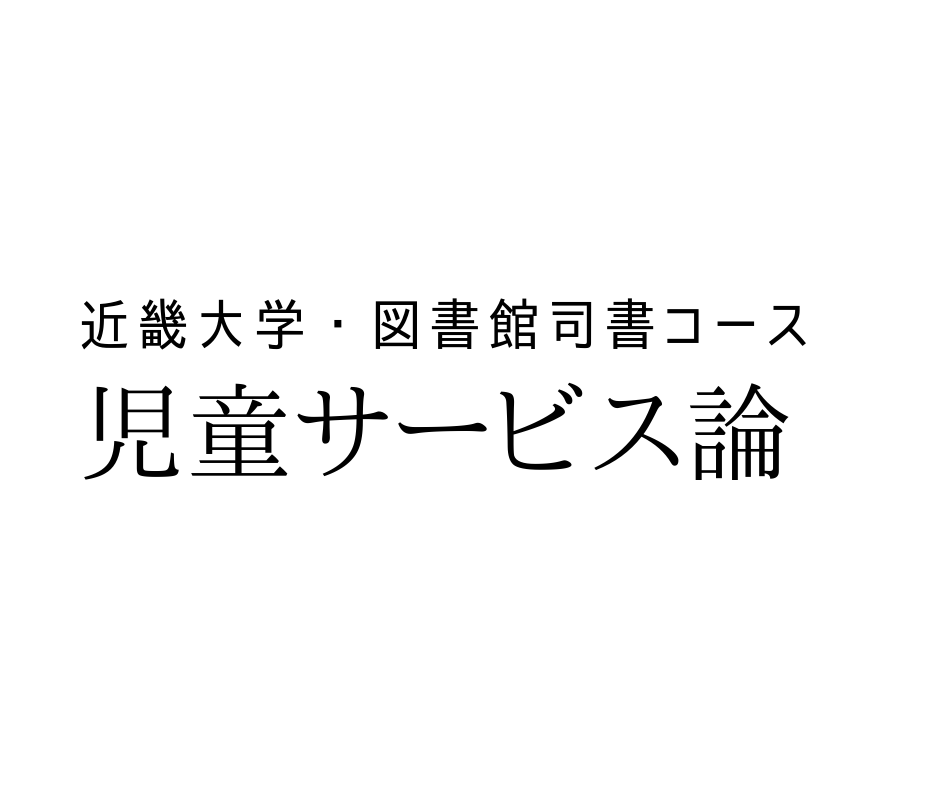
コメント