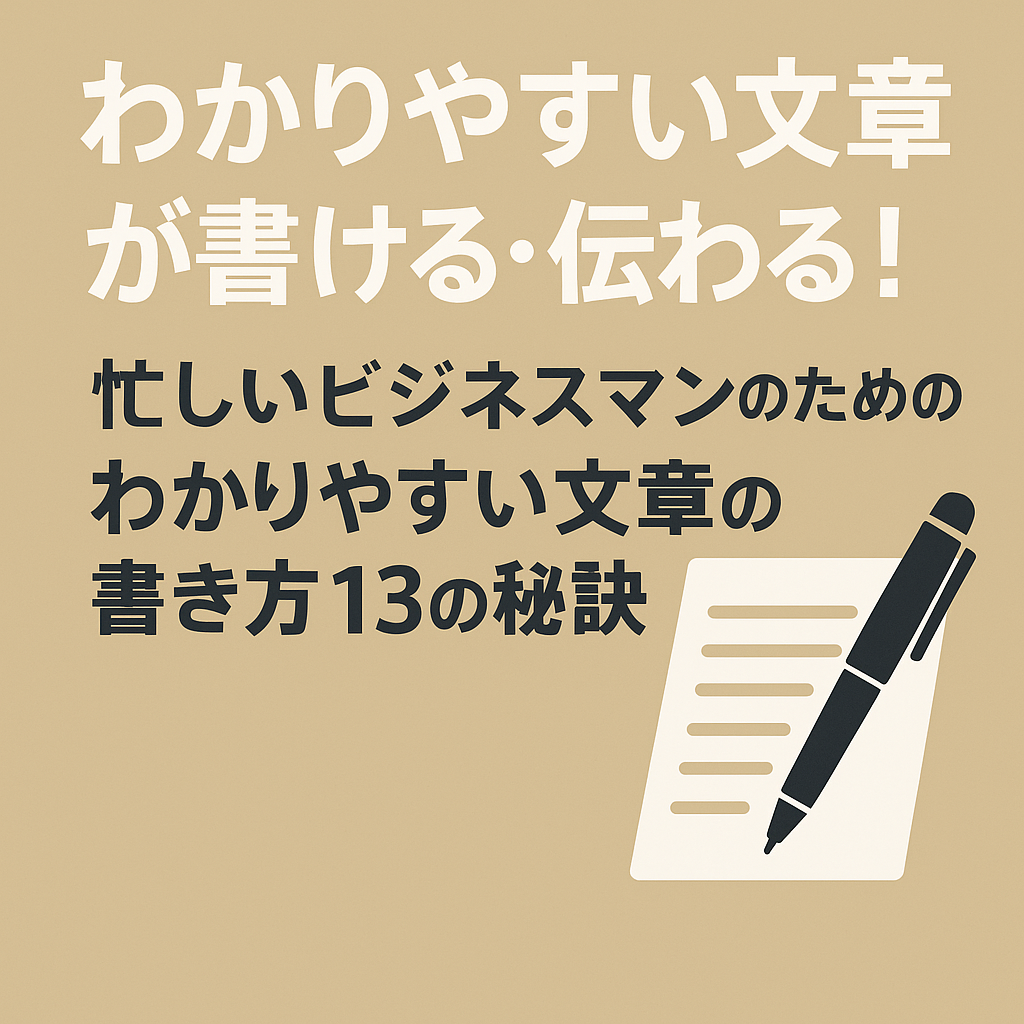
忙しいビジネスパーソンにとって、相手に伝わる「わかりやすい文章」を書く力は、大きな武器になります。
プレゼン資料、メール、報告書、SNS投稿……どんな場面でも「読みやすくて伝わる」文章が書ける人は、信頼され、チャンスを引き寄せます。
本記事では、読みやすさと伝わりやすさを両立するための13の秘訣を、実例とともにわかりやすく解説します。
忙しい方でもすぐに実践できるシンプルなコツばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 結論を先に書く
ビジネス文書では「起承転結」よりも「結論→理由→詳細」の順番が鉄則です。
冒頭で「何を伝えたいのか」を示すだけで、読み手のストレスを減らせます。
✅ 例)
悪い例:「先日の件について、いろいろ考えてみましたが……」
良い例:「先日の提案については、実施を見送る判断をしました。」
2. 一文一義で書く
一文で複数の情報を詰め込むと、読みづらくなります。
一文にはひとつの意味(主張)だけを入れるのが基本です。
✅ ポイント:読点「、」が3つ以上出てきたら、文を分けましょう。
3. 難しい言葉を使わない
専門用語や抽象的な言葉は、読み手にとって「わかりにくい文章」の原因になります。
中学生でも理解できるレベルの言葉に言い換えましょう。
✅ 例)
「可及的速やかに」→「できるだけ早く」
4. 主語と述語を対応させる
主語があいまいだと、読み手は「誰が何をしたのか?」でつまずきます。
主語と述語はセットで、対応させて書くように意識しましょう。
5. 箇条書きを活用する
情報が複数あるときは、文章で並べるよりも箇条書きが効果的です。
視認性が高くなり、読み飛ばされにくくなります。
6. 一文の長さは60文字以内
長すぎる一文は、内容が伝わりにくくなります。
目安として60文字以内で区切るようにしましょう。
7. 主語と目的語の距離を近くする
「~が」「~を」が文の中で離れすぎると、意味を取りづらくなります。
主語・述語・目的語は、なるべく近づけて配置しましょう。
8. 修飾語の位置に注意する
どの言葉を修飾しているのかがあいまいだと、読み手に誤解を与えます。
修飾語は、修飾される語のすぐ前に置くのが基本です。
9. 文末をそろえる
「〜です。〜します。〜になります。」と文末がバラバラだと、文章に統一感がなくなります。
「です・ます」調か「だ・である」調か、最初に決めて、統一しましょう。
10. 具体例を入れる
抽象的な説明だけでは伝わりにくいため、具体例を加えると理解度がグッと上がります。
✅ 例)
抽象的:「文章には構成が重要です」
具体的:「文章を書くときは『結論→理由→事例』の順番で構成すると伝わりやすくなります」
11. 漢字とひらがなのバランスを整える
文章に漢字が多すぎると堅苦しく、ひらがなばかりだと幼稚に見えてしまいます。
「〜的」「〜性」「〜感」などの語は、ひらがなに直せる場合もあります。
✅ 例)
「可能性があります」→「〜かもしれません」
「理解していただく」→「わかってもらう」
12. 接続詞は必要最低限に
「しかし」「つまり」「また」「なので」などの接続詞は、適度に使えばわかりやすくなりますが、多用すると逆効果です。
本当に必要なときだけに絞りましょう。
13. 読み返して声に出す
最後に、必ず「声に出して読む」か「時間をおいて読み返す」ようにしましょう。
客観的な視点で見直すと、不要な語句や違和感に気づきやすくなります。
まとめ|わかりやすい文章は誰でも書ける
読みやすい文章は、特別な才能ではなく、ちょっとした工夫の積み重ねです。
今回紹介した13のポイントを意識するだけで、あなたの文章は格段に伝わりやすくなります。
仕事のメール、報告書、プレゼン資料……どんな場面でも使えるテクニックですので、ぜひ明日から意識してみてください。
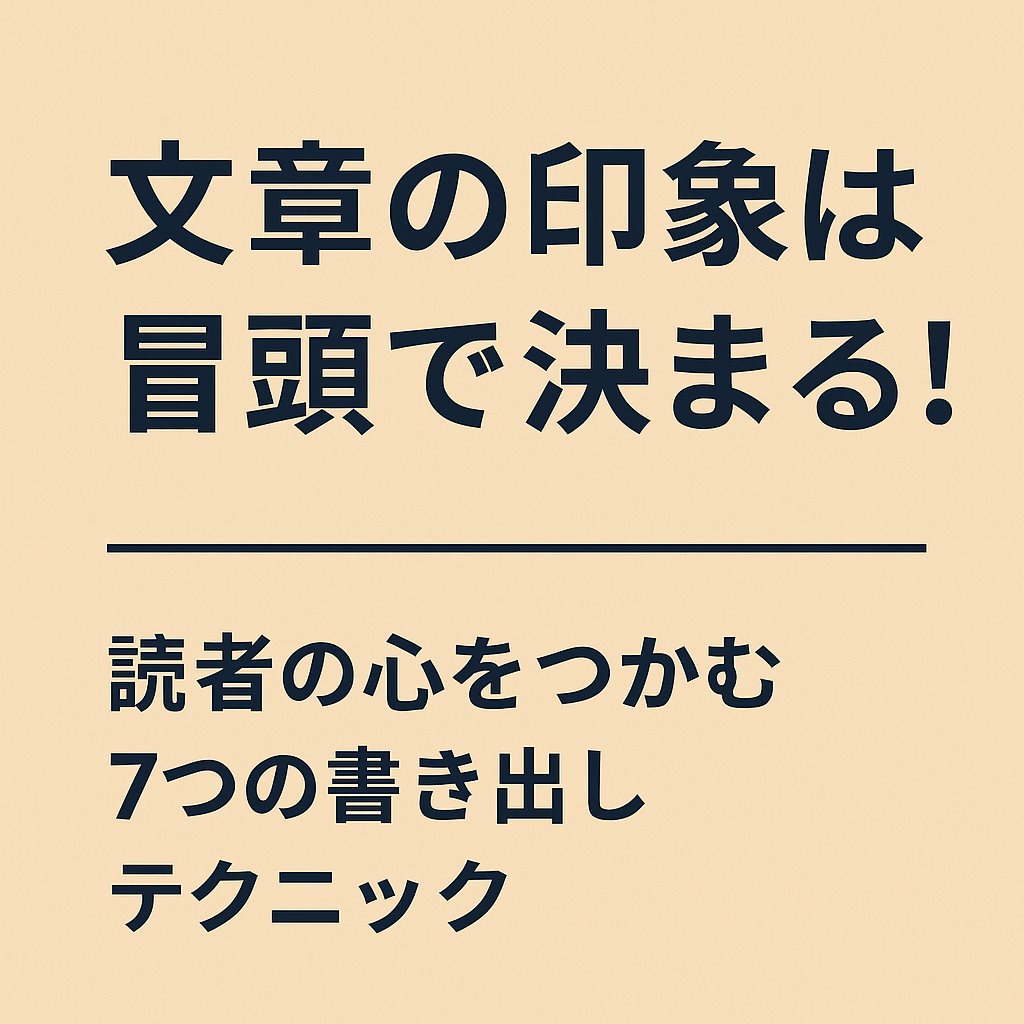
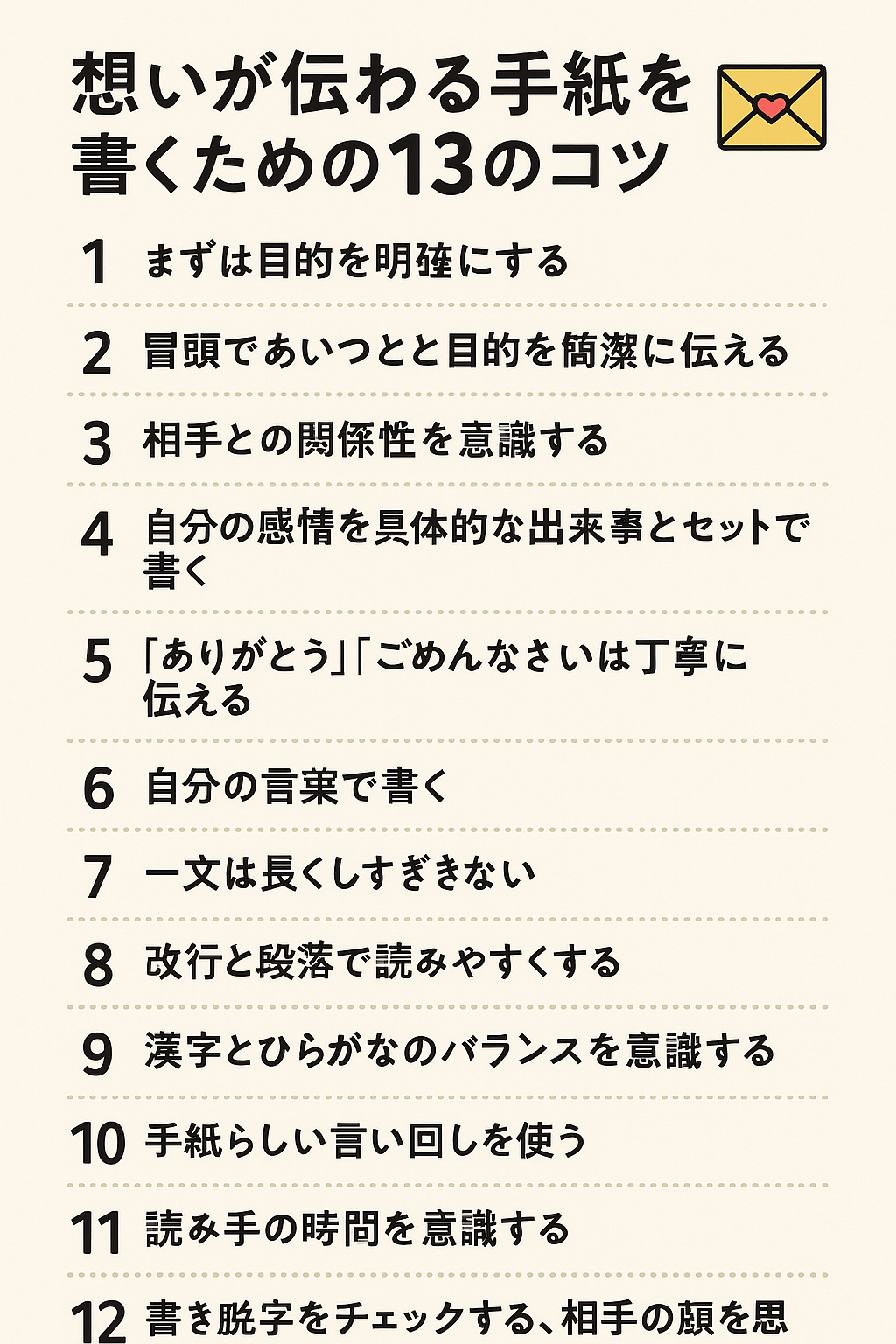
コメント