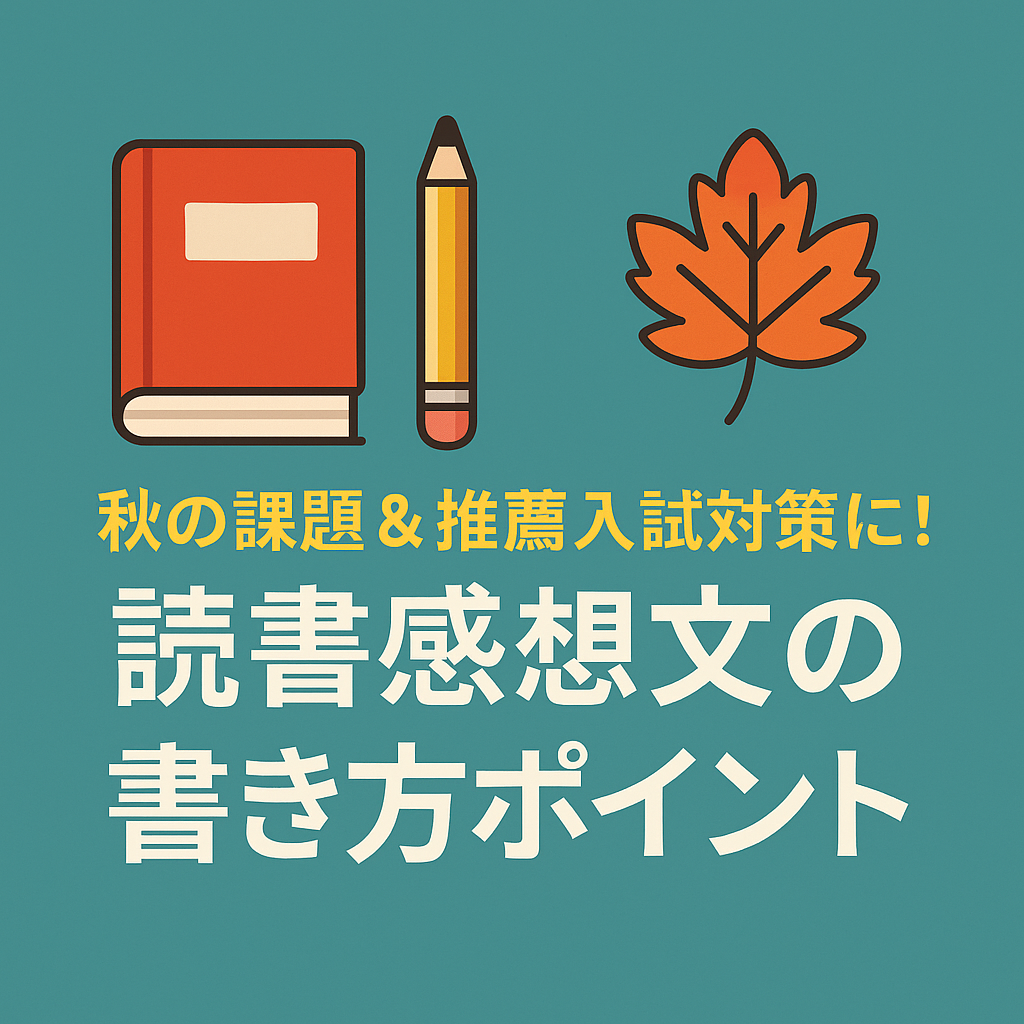
「読書感想文、何を書けばいいかわからない…」その悩み、解決します
秋は推薦入試、AO入試、就職試験のシーズン。この時期になると「読書感想文が書けない」という相談が急増します。
実際、多くの受験生が書く感想文は:
- 本のあらすじをただまとめただけ
- 「面白かったです」「勉強になりました」で終わってしまう
- 自分の個性や考えが全く見えない
でも大丈夫。正しい書き方さえ知れば、誰でも評価される感想文が書けます。
国語教師として10年間、数千本の読書感想文を添削してきた私が、本当に使える書き方のコツをお教えします。この記事を読めば、推薦入試で差をつける「あなたらしい」感想文が必ず書けるようになります。
なぜ読書感想文で差がつくのか?採点者の本音
採点者が見ているのは「文章力」だけじゃない
推薦入試や就職試験で読書感想文が課される理由は、以下の能力を総合的に判断できるからです:
1. 読解力
- 本の内容を正確に理解できているか
- 表面的でなく深い部分まで読み取れているか
2. 思考力
- 読んだ内容について自分なりに考えられているか
- 批判的な視点を持てているか
3. 表現力
- 自分の考えを論理的に文章で表現できるか
- 読み手を意識した分かりやすい文章が書けるか
4. 人間性
- どんな価値観を持っているか
- どんな経験をしてきた人なのか
実際の採点例:なぜこの感想文は高評価なのか?
❌ よくある低評価の感想文
『夜と霧』を読みました。主人公がアウシュビッツで辛い経験をする話です。戦争は怖いと思いました。平和が大切だと感じました。
⭕ 高評価を受ける感想文の例
フランクルの『夜と霧』で最も印象的だったのは「それでも人生にイエスと言う」という言葉でした。私も高校時代、部活動で大きな挫折を経験し、すべてを投げ出したくなったことがあります。しかし、フランクルの「どんな状況でも人は選択の自由を奪われない」という思想に触れ、辛い状況こそが自分を成長させる機会なのだと気づきました…
差がつくポイント:
- 具体的な引用がある
- 自分の体験と関連づけている
- 単なる感想を超えて考察が深い
【STEP1】戦略的な本選び|書きやすい本には法則がある
課題図書がある場合の攻略法
指定された本が「書きにくそう」でも、以下の視点で切り口を見つけられます:
切り口1:時代背景と現代の比較
- 古典作品 → 現代社会との共通点・相違点を探る
- 海外文学 → 文化の違いから見える普遍的テーマ
切り口2:登場人物の心理分析
- 主人公の選択 → 自分なら同じ選択をするか?
- 人間関係 → 現実の人間関係に当てはめて考察
切り口3:社会問題との関連
- 小説のテーマ → 現在の社会課題とのつながり
自由選択の場合:「書きやすい本」の条件
おすすめジャンル:
1. 自伝・エッセイ系
- 『学問のすすめ』(福沢諭吉)
- 『君たちはどう生きるか』(吉野源三郎)
- 理由:筆者の体験談と自分の経験を重ねやすい
2. 社会問題を扱った小説
- 『コンビニ人間』(村田沙耶香)
- 『火花』(又吉直樹)
- 理由:現代の課題について自分なりの意見が書きやすい
3. 心理描写が丁寧な作品
- 『人間失格』(太宰治)
- 『こころ』(夏目漱石)
- 理由:登場人物の気持ちに共感・反発しやすい
避けるべき本:
- ファンタジー・SFは現実との接点を見つけにくい
- 純粋な恋愛小説は深い考察が難しい
- 専門用語が多すぎる学術書
【STEP2】読書の仕方を変える|感想文のための戦略的読書法
普通に読むだけでは感想文は書けない
感想文を書くための読書は、娯楽としての読書とは全く違います。
戦略的読書の5ステップ:
1. 付箋・メモを準備 読みながら以下をメモ:
- 心に残った一文(引用候補)
- 疑問に思ったこと
- 自分の体験と重なる部分
- 反対意見を持った箇所
2. 章ごとに要約 各章を1〜2行でまとめる習慣をつけると、全体構造が見えてきます。
3. キーワード抽出 本のテーマを表すキーワードを5〜10個リストアップ
4. 著者の主張を整理 「この本で著者が最も言いたいことは何か?」を一文でまとめる
5. 自分の立場を明確化 著者の意見に対して:
- 同感する部分
- 疑問を感じる部分
- 新たに気づいた部分
効果的なメモの取り方
メモ例:
【引用候補】p.45「困難な状況こそが、人の真価を決める」
【自分の体験】部活の大会で負けた時→この言葉と同じ気持ち
【疑問】本当にすべての困難に意味があるのか?
【社会とのつながり】現代の就職活動の厳しさにも通じる
【STEP3】採点者の心を掴む構成術
基本の三部構成をマスター
序論(全体の20%)
- 本を選んだ理由
- 読む前の印象や期待
- 簡潔な本の紹介
本論(全体の70%)
- 最も印象的だった場面・言葉
- 自分の体験とのつながり
- 本から得た新しい視点
- 疑問や反対意見
結論(全体の10%)
- この本から学んだこと
- 今後の行動や考え方への影響
さらに差をつける「5段階構成」
上級者向けの構成パターン:
1. 導入(印象的な一文から始める) 2. 本の概要(簡潔に) 3. 共感ポイント(自分の体験と重ねる) 4. 批判的考察(疑問や反対意見) 5. 統合・発展(学びと今後への影響)
具体例:
「人は誰でも、自分だけの物語を生きている」
この一文に出会った時、私は高校3年間の自分を振り返らずにはいられなかった...
【STEP4】「自分らしさ」を表現する7つの技術
技術1:具体的なエピソードで勝負
❌ 抽象的な表現 「主人公の頑張りに感動しました」
⭕ 具体的なエピソード 「私も中学時代、転校先で友達ができずに一人で昼食を食べていた日々がありました。主人公が新しい環境で孤独と向き合う姿に、当時の自分を重ねずにはいられませんでした」
技術2:数字を使って説得力アップ
例: 「この本を読むまで、私は1日平均3時間スマホを見ていました。しかし、『デジタル・ミニマリスト』を読んでから、SNSの利用時間を30分以下に制限するようになりました」
技術3:対立構造で深みを演出
パターン1:過去の自分 vs 現在の自分 「以前の私は〜と考えていましたが、この本を読んで〜という新しい視点を得ました」
パターン2:一般的な意見 vs 自分の意見 「多くの人は〜と思うかもしれませんが、私は〜だと考えます」
技術4:五感を使った描写
視覚:「黄昏時の校庭で一人佇む主人公の姿が目に浮かぶようでした」 聴覚:「母親の子守唄のように優しい文体に包まれました」 触覚:「ページをめくる手が震えるほど、衝撃的な結末でした」
技術5:比喩・例え話の活用
例: 「主人公の成長は、蛹から蝶への変化のようでした。一見すると何も起こっていないように見える日々の中で、確実に内面が変化していく様子が丁寧に描かれています」
技術6:引用の効果的な使い方
基本ルール:
- 引用は必ず「」で囲む
- ページ数を明記
- 引用の後に自分の解釈を加える
良い引用例: 「『人生に意味を見出すのは、私たち自身だ』(p.123)という言葉は、責任の重さと同時に、無限の可能性を感じさせます」
技術7:未来への展望で締める
例: 「この本との出会いをきっかけに、将来は教育の現場で働き、一人でも多くの子どもたちに『学ぶことの楽しさ』を伝えたいと強く思うようになりました」
【STEP5】推薦入試で差をつける「志望理由」との連携術
感想文を志望理由書の「前段」として活用
推薦入試では、読書感想文と志望理由書の内容に一貫性があることが重要です。
連携パターン1:価値観の一貫性
- 感想文:「多様性の大切さに気づいた」
- 志望理由:「国際関係学部で多文化共生を学びたい」
連携パターン2:課題意識の発展
- 感想文:「教育格差の問題を深く考えるようになった」
- 志望理由:「教育学部で平等な教育機会の創出に取り組みたい」
志望分野別・おすすめ本&アプローチ
文学部志望
- おすすめ本:『舟を編む』(三浦しをん)
- アプローチ:言葉の力、表現の可能性について考察
経済学部志望
- おすすめ本:『デフレの正体』(藻谷浩介)
- アプローチ:経済現象の背後にある人間の行動を分析
教育学部志望
- おすすめ本:『学校の「当たり前」をやめた。』(工藤勇一)
- アプローチ:理想的な教育のあり方について自分なりの考えを展開
医学部志望
- おすすめ本:『医者の本音』(中山祐次郎)
- アプローチ:医療従事者の責任と使命について考察
【STEP6】よくある失敗パターンと対処法
失敗パターン1:「あらすじ紹介」で終わってしまう
症状:本の内容説明が全体の50%以上を占める
対処法:
- あらすじは全体の20%以下に抑制
- 「なぜその場面が印象的だったのか」の理由を必ず書く
失敗パターン2:浅い感想の羅列
症状:「面白かった」「感動した」「勉強になった」の連続
対処法:
- 必ず「なぜ?」を3回繰り返す
- 具体的な例や体験を必ずセットにする
失敗パターン3:自分語りが長すぎる
症状:自分の体験談が本の内容より多くなる
対処法:
- 自分の体験は本の内容を深めるための「材料」と位置づける
- 体験談の後に必ず本の内容との関連を明記
失敗パターン4:結論が弱い
症状:「良い本でした」「読んでよかったです」で終わる
対処法:
- 具体的な行動変化や考え方の変化を書く
- 「今度は〜してみたい」など未来への言及を入れる
【STEP7】推敲・チェックポイント|プロの添削術
第1段階:構成チェック
確認項目: □ 序論・本論・結論の比率は適切か? □ 段落ごとに明確な主張があるか? □ 論理的な流れになっているか?
第2段階:内容チェック
確認項目: □ 本の理解は正確か? □ 自分の体験との関連は自然か? □ オリジナリティのある視点はあるか? □ 志望分野との関連は明確か?
第3段階:表現チェック
確認項目: □ 誤字・脱字はないか? □ 一文が長すぎないか?(60字以内推奨) □ 同じ語尾が3回以上続いていないか? □ 敬語の使い方は正しいか?
最終チェック:音読確認
- 声に出して読み、不自然な箇所がないかチェック
- リズムが悪い文章は読みにくい文章
- 詰まるところは必ず修正する
まとめ:読書感想文は「あなた」を表現する最高のツール
読書感想文は、単なる課題ではありません。あなたの思考力、表現力、人間性を総合的に示すことができる貴重な機会です。
今日からできる3つのアクション
1. 戦略的な本選び
- 自分の体験や関心と関連する本を選ぶ
- 志望分野とのつながりを意識する
2. 読書メモの習慣化
- 付箋とペンを必ず用意
- 心に残った箇所と理由をセットで記録
3. 構成テンプレートの活用
- まずは基本の三部構成から
- 慣れてきたら5段階構成に挑戦
最後に:完璧を目指さず、「あなたらしさ」を大切に
採点者が求めているのは、完璧な文章ではありません。あなたにしか書けない、あなたらしい感想文です。
技術も大切ですが、最も重要なのは「この本を読んで、本当にどう思ったのか」という素直な気持ちです。
この記事で紹介したテクニックを参考にしながら、ぜひ自分らしい読書感想文を書いてみてください。きっと、推薦入試や就職試験で差をつけることができるはずです。
【関連記事予告】
あなたの読書感想文作成を応援しています!頑張ってください。

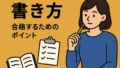
コメント